導入:高市=トランプ会談、あなたには何が見えましたか?
多くのテレビニュースが、来日したトランプ大統領と、高市首相の会談を大々的に報じました。NEWSの映像では、二人が東京・六本木のヘリポートから専用ヘリに乗り込み、横須賀に停泊する原子力空母「ジョージ・ワシントン」の甲板でスピーチを行う様子が映し出されました。多くの人にとって、これは「日米同盟の強固さ」をアピールする、ありふれた政治的風景に見えたかもしれません。
しかし、ジャーナリストの菅野完氏は、この一連の出来事の中に、日本の政治と社会が抱える根深い問題を二つも見出しました。多くの人が「アメリカの属国だ」という表面的な批判に留まる中、菅野氏はその奥にある、見過ごされがちな「本当の論点」を鋭く指摘します。この記事では、その核心的な二つの論点を、誰にでもわかるように丁寧に紐解いていきます。
——————————————————————————–
1. なぜリベラルの批判は「的外れ」なのか?
ここで菅野氏は、政治的焦点を転換させるための、さながら達人芸ともいえる手法を披露します。彼は抽象的で象徴的な批判を退け、具体的で人間的な懸念に基づいた批判へと移行することの重要性を説きます。これは、権力と対峙しようとする全てのジャーナリストや市民にとって、極めて重要な教訓です。
1-1. よくある批判とその限界
高市氏がトランプ氏に寄り添う姿を見て、多くのリベラル派や政権に批判的な人々から、次のような声が上がりました。
「いつから日本はアメリカの属国になったんだ」
しかし菅野氏は、この反応を「ぬるい」「アホらしい」と、政治的な無力さへの苛立ちも露わに一蹴します。彼に言わせれば、このような感傷的で自己満足的な嘆きは、政治闘争の現実からあまりにかけ離れています。菅野氏の怒りの核心は、「そんなことを言っているから、いつまで経っても選挙に勝てないんだ」という一点にあります。それは、勝つための言葉を持たないリベラル陣営への、痛烈な叱咤なのです。
1-2. 菅野氏が指摘する「見るべきだった」もう一つの論点
では、リベラル派は何を言うべきだったのでしょうか?菅野氏は、彼らが見落としたもう一つの重要な視点を提示します。それは、映像の背景に整列していた米兵たちの、極めて現実的な問題です。
「ここで映ってる兵隊さん、連邦政府がシャットダウンしてるから先月から給料もらえてないんです」
菅野氏によれば、単に「属国だ」と感情的に批判するのではなく、「後ろの兵隊さん、給料もらえていないそうですね」と、そこにいる人々の生活に寄り添う言葉をかけることこそ、より効果的な政治的メッセージになり得たと言います。政治の本来の役割は、国民や働く人々の生活を改善することにあるはずです。その姿勢を有権者に示すことこそが、共感と支持を得るために不可欠だ、と菅野氏は力説するのです。
——————————————————————————–
しかし、菅野氏が最も問題視したのは、兵士の給料問題ですらありませんでした。彼の怒りの矛先が向かったのは、映像に映る高市氏自身の姿、そしてそこに象徴される日本社会の深刻な病理だったのです。
——————————————————————————–
2. 最大の論点:高市首相の姿が映し出す日本の「ジェンダーロール」
菅野氏の最も鋭利な分析は、しかし、白日の下にありながら多くの人が見過ごしていた現象に向けられます。彼は、政策や言動の裏に隠された、社会の暗黙のルール――この場合は、社会が女性に強いる有害なジェンダーロール――に目を向けることこそが、その政治家が代表する社会の真実を暴き出すのだと教えてくれます。
2-1. 「キャピキャピする女性政治家」という問題
菅野氏が最も強く、そして深い共感と怒りを込めて批判したのは、高市氏がトランプ氏の隣で見せた、いわゆる「キャピキャピ」した明るく無邪気な振る舞いでした。彼はこれを、高市氏個人の資質の問題として決して片付けません。むしろ、これは**「日本の女性政治家が、男性政治家の隣に来たらなぜかやらなければならない役割」**、すなわち、社会によって無意識に押し付けられた構造的なジェンダーロールの表れだと喝破します。
「これ(この役割)ができるから内閣総理大臣になった。逆に言うとこれをしないと女性は内閣総理大臣になれない」という菅野氏の言葉は、この問題の構造的な暴力を浮き彫りにします。
2-2. それは「すべての女性」の問題である
この問題の根深さは、政治の世界に留まりません。菅野氏は、高市氏の姿が、日本の一般社会で働く多くの女性が日々直面している「地獄」と地続きであると指摘します。
- 「おじさん社会」での生存戦略 男性上司や権力者の隣では、能力や実績とは別に、「女性らしさ」を演じ、少し「ギャルっぽく」明るく振る舞わないと、組織の中で認めてもらえないという空気。
- 成功した先に待つ二重の地獄 その役割をうまく演じて出世すると、今度は周囲の男性たちから「女は媚びを売れば出世できて楽でいいね」と揶揄される。これは、努力を踏みにじられ、人格を否定される二重の地獄です。
- リベラルが言語化すべき「生きづらさ」 この「女性に強いられている生きづらさ」こそ、リベラルや野党が社会構造の問題として言語化し、その根源を批判すべき本質的なテーマである、と菅野氏は魂の叫びのように訴えます。
2-3. 中島みゆきの歌に見る「女性の地獄」
この問題の根深さを象徴するものとして、菅野氏は中島みゆきの楽曲『やまねこ』の歌詞を引用します。
女に生まれて喜んでくれたのは 菓子屋とドレス屋と女衒と女たらし
生まれ落ちて最初に聞いた声は落胆の溜息だった
この歌詞は、女性が生まれた瞬間から、社会的な期待と失望の中で生きることを強いられる現実を歌っています。菅野氏は、高市首相が国際政治の舞台で演じざるを得なかった役割もまた、この地獄の延長線上にあるのだと分析したのです。
——————————————————————————–
このように、菅野氏はリベラルの視点の甘さをジェンダー問題から鋭くえぐり出しました。では、彼らが批判する相手である「右翼」とは、そもそも何者なのでしょうか?菅野氏は、ここにも根深い誤解があると指摘します。
——————————————————————————–
3. 日本の「右翼」の正体とは?― 親米という本質
3-1. 一般的なイメージと菅野氏の定義
「右翼」と聞くと、多くの人は純粋な国家主義を掲げ、アメリカに反発する姿をイメージするかもしれません。しかし、菅野氏はこの一般的なイメージを完全に否定します。彼が語る日本の右翼の、衝撃的な本質は次の言葉に集約されています。
「1945年8月15日の夕方から、日の丸の代わりに星条旗を振るのが日本の右翼」
つまり、日本の右翼とは、戦後一貫して「親米」であり、それが彼らのアイデンティティそのものだというのです。
3-2. なぜ右翼は「親米」になったのか?
戦前の国家主義者たちが、なぜ敗戦を機に親米へと180度転換したのでしょうか。菅野氏は、その背景を二人の象徴的な人物を挙げて解説します。イデオロギーのラベルを剥がし、生々しい人間の動機を暴き出すことの重要性がここにあります。
| 登場人物 | 菅野氏による解説 |
| 児玉誉士夫 | 戦後最大の右翼の大物。彼は自著で「真の親米派は、かつての国家主義者の中から生まれる」と記し、天皇と国家への忠誠こそが親米につながると理論づけた。 |
| 岸信介 | 安倍晋三元首相の祖父。A級戦犯容疑者として収監された巣鴨プリズンで処刑を免れるため、泣いて命乞いをし、CIAのエージェントとなって日本をアメリカに売り渡す道を選んだとされる。 |
3-3. 生き残るための「現実的な選択」とその代償
菅野氏によれば、右翼が親米路線を選んだ動機は、高尚なイデオロギーというより、もっと生々しく、ほとんど哀れでさえある現実的なものでした。
- 反共のため:最大の目的である「天皇制の護持」にとって、共産主義は最大の敵だった。その「敵の敵」であるアメリカと手を組むのは、当然の選択でした。
- 飯を食うため:敗戦後の人々は飢えていました。生きるためには、占領軍であるアメリカに取り入り、食料や仕事を得る必要があったのです。
しかし、この極めて現実的な選択は、大きな代償を伴いました。戦前の「大日本帝国」という巨大な精神的支柱を失った人々の「心の問題」、その精神的な空白を、右翼は埋めることができませんでした。その結果、その役割は創価学会や立正佼成会といった新興宗教が担うことになった、と菅野氏は分析しています。
——————————————————————————–
結論:本当に戦うべき相手は誰か
菅野氏の一連の論考を紐解くと、彼の視点の核心が見えてきます。それは、「属国だ」といった表面的なスローガンで思考停止するのではなく、その背後にある、より根深く、構造的な問題に目を向けることの重要性です。
彼が本当に問題にしているのは、日本社会に深く根付いたジェンダー構造の不平等であり、そして「右翼」「リベラル」といった言葉のイメージに惑わされず、政治勢力の歴史的な本質を見抜くことです。
菅野氏の分析が私たちに突きつける最終的な教訓は、一つの挑戦状です。ニュースを受動的に消費するのをやめなさい。見えない論点を見つけ出し、与えられたラベルを疑い、人々の苦しみを生み出し、永続させる構造そのものに焦点を当てなさい。そこにこそ、社会を動かすための本当の物語が隠されているのです。
人気ブログランキング

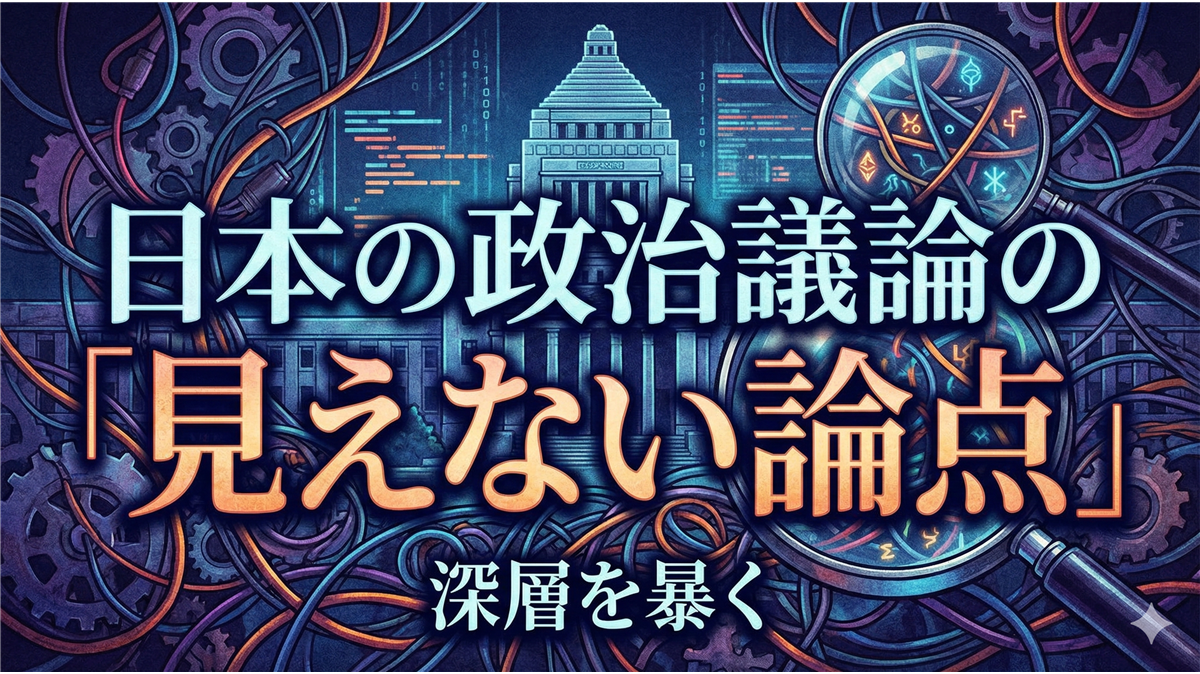
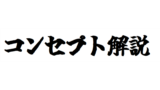
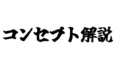
コメント