エグゼクティブ・サマリー
愛国者としては暴支膺懲世論の高まりを座して見過ごすわけにはいかんよね:15分朝刊チェック 2025年11月20日
2025年11月20日の主要メディア報道は、国内外における複数の重大な転換点を示唆している。国内最大の懸案事項として、柏崎刈羽原発の再稼働が新潟県知事によって容認される見通しとなった。これに対し、本件を分析する論者は、放射能の危険性そのものよりも、国、自治体、事業者の間で責任の所在が曖昧になる「日本型の意思決定プロセス」こそが根本的な問題であり、日本の組織的能力では原発の安全な運営は「無理」であると断じている。
国内では、大分県で鎮火に数週間を要するとされる大規模火災が発生し、「激甚災害」級の事態となっている。また、アサヒビールグループへのサイバー攻撃がアスクルや無印良品などのサプライチェーンに深刻な影響を及ぼし、経済活動への新たな脅威を浮き彫りにした。
国際情勢では、トランプ米政権がカリブ海にF-35を配備するなどベネズエラへの圧力を強めているが、これは独創的な政策ではなく、1980年代のレーガン政権の行動をなぞる「典型的な共和党仕草」に過ぎないと分析されている。同時に、エプスタイン事件資料の公開承認やテキサス州のゲリマンダー(選挙区割り)に対する司法判断など、トランプ政権は国内で苦境に立たされている。
特に警鐘が鳴らされているのは、中国による日本産水産物の輸入停止措置を巡る国内世論の動向である。論者は、一部メディアやインターネット上で見られる強硬な論調が、90年前の日中戦争前夜の状況と「そっくり」であると指摘。歴史的教訓を無視したままでは「悲惨な結末」に至る危険性があると、専門家の見解を引用しつつ強く警告している。
1. 国内の重要課題
1.1. 柏崎刈羽原発の再稼働容認:責任の不在という構造的問題
各紙のトップ記事として、新潟県知事が東京電力・柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を近く表明する見通しであることが報じられた。これは福島第一原発事故後、東電が運営する原発としては初の再稼働容認となる。
この決定に対し、論者は原発反対の根拠を「放射能が怖いからではない」と明言し、問題の本質は日本の組織的な欠陥にあると主張する。
- 責任の循環構造:
- 原発の稼働決定において、責任の所在が極めて不明確である点が最大の問題だと指摘されている。
- 知事は「地元の合意があったから」と言い、地元は「東電から要請があったから」、東電は「国から要請があったから」、そして国は「知事から要請があったから」と、責任が関係者間を「ぐるぐる回し」にされる構造を批判。
- この責任の所在が不明確な「日本的な意思決定」のやり方は、万一の事故発生時に致命的な欠陥となると論じられている。
- 運営能力への根本的懐疑:
- 論者は、日本の組織的能力では原発のような高度なリスク管理が求められるシステムの運営は不可能だと断じている。
- この状況を「サザン(3x3)が8って言うてる子が数の微分積分の問題解こうとしてるようなもん」「日本人に能力が寸足らずやから原発は無理です」と痛烈に批判。
- 福島第一原発事故の責任の所在が未だに明確にされていない現状が、その証左であるとされている。
この再稼働決定プロセスは、「今回俺が原発に反対する理由の全てが詰まった意思決定プロセス」であり、2025年における国政の最重要課題であると位置づけられている。
1.2. 大分の大規模火災:広域災害への警鐘
大分県で大規模な火災が発生し、深刻な被害が報告されている。
- 被害状況:
- 焼失家屋は170棟に及ぶ。
- 強風に煽られ、火の手は山林に燃え広がり山火事となっているほか、海を越えて対岸の島にまで延焼する危険性が指摘されている。
- 専門家の見通しとして、鎮火には「2週間かかるのではないか」との報道もある。
- 災害の規模と認識:
- 菅野氏は「過去10年20年で最大の火事になる」「激甚災害に指定してもよいような気がします」と述べ、事態の深刻さを強調。
- 今年は太平洋ベルト地帯では大きな水害がなかったものの、八丈島の台風や今回の大分火災など、日本の「外周」で大規模災害が頻発していることを忘れてはならないと警鐘を鳴らしている。
2. 国際情勢の動向
2.1. 米国の外交政策:トランプ政権の「没個性的」な共和党仕草
日経新聞は、米国がベネズエラへの対抗措置としてカリブ海にF-35を配備し、パナマやトリニダード・トバゴで軍事演習を繰り返していることを報じた。
- レーガン・レガシーの模倣:
- 菅野氏は、これらの動きを「レーガン大統領の真似をしてるようにしか見えない」と分析。特に1983年のグラナダ侵攻を模倣しようとしているのではないかと指摘している。
- トランプ大統領の行動は、一見すると個性的で突飛に見えるが、その本質は「40年50年前の典型的なアメリカ共和党仕草」であり、「没個性的」であると論評。
- 伝統的な孤立主義:
- 「世界は我々のことをほっといてくれ」「大西洋から日付変更線の間だけはアメリカだ」という考え方は、19世紀から続く共和党の伝統的なスタンスの表れに過ぎず、トランプ氏固有の政策ではないとされている。
- 個性的なのは「顔と喋り方だけ」であり、政策自体に新奇性はないとの見方を示した。
2.2. 中東情勢:パレスチナ問題と米国の軍事支援
中東情勢に関する各紙の報道が注目されている。
- 読売新聞の優れた報道:
- イスラエルの入植者によるパレスチナ人への襲撃が10月に月間最多の264件に達したことを報じた読売新聞(福島記者)の記事を「素晴らしい記事」と高く評価。
- 米国のF-35売却:
- 米国がサウジアラビアへのF-35戦闘機売却を決定。これに対し、論者は「サウジに片入れしすぎで、中東の均衡が破れそうで怖い」と懸念を表明。
- 日経新聞の特集記事:
- 日経新聞の「経済教室」欄で始まった高橋先生による特集「パレスチナの過去と未来」について、「この記事を読むためだけにでも今日は日経新聞を買うべき」と強く推奨している。
2.3. トランプ氏の苦境:エプスタイン事件とゲリマンダー問題
毎日新聞の報道を引用し、トランプ氏が国内で直面している困難な状況が解説された。
- エプスタイン事件資料の公開: トランプ氏は世論に押される形で、エプスタイン事件関連の資料公開法案を承認。毎日新聞はこれを「屈服のトランプ氏」と表現。
- テキサス州のゲリマンダー問題: 共和党が有利になるよう意図的に作られたテキサス州の選挙区割り(ゲリマンダー)に対し、州の法廷が「憲法違反」であり「人種差別だ」として差し止めを命じた。白人が多い地域を飛び石のようにつなげて選挙区を形成する手法が問題視された。これにより、共和党の議席増戦略に狂いが生じている。
3. 国内経済・政治の論点
3.1. サイバー攻撃による経済的影響
読売新聞は、経済に直結する重要な問題として、アサヒビールグループが受けたサイバー攻撃の広範な影響を報じた。
- 物流システムの麻痺:
- サイバー攻撃により、アサヒビールと連携する流通会社のシステムに障害が発生。
- 特にアスクルでは、倉庫の台車ロボットが使用不能となり、社員が手作業で出荷作業を行っている様子が公開された。
- 無印良品などにも影響が及んでいる。
- 業界全体への波及:
- アサヒビールの出荷が停止した結果、キリンビールにお歳暮用の注文が殺到。
- この需要急増に対応しきれず、キリンビールは贈答用ビールの販売を中止する事態となった。
- 飲食店ではアサヒビールの供給が滞り、サッポロの「赤星」を扱う店が増えているという現象も起きている。
3.2. N国党・立花孝志氏の書類送検
読売新聞の社会面が、N国党(NHKから国民を守る党)の立花孝志党首らの書類送検を大きく報じた。
- 事件の概要: 7月の参議院宮城選挙区において、立憲民主党の石垣のりこ議員を中傷する選挙ポスターを掲示したとして、立花氏ら3名が名誉毀損容疑で書類送検された。
- 報道内容: 捜査は、石垣議員と菅野完氏が提出した被害届と告発に基づいて進められた。検察に刑事処分の判断を委ねる「相当処分」の意見が付されたとみられる。
- 論者の扱い: 菅野氏は、記事中で「名前が記載された男性」と表記されたことについて触れ、「メディアは僕のことを完全に私人だと思ってるってことですよね」と皮肉を交えてコメントした。
3.3. 企業団体献金を巡る政局と産経新聞の論調
公明党と国民民主党が企業団体献金の禁止法案を共同提案し、政局の新たな焦点となっている。
- 政党連携の動き: 公明・国民民主の共同提案に、立憲民主党も賛成する見通しで、「30年ぶりの新進党みたい」な連携が模索されている。
- 産経新聞への批判: この動きに対し、産経新聞は「定数削減を牽制するために出してきやがった」と報じた。
- 論点のすり替え: 菅野氏はこの産経の論調を強く批判。「違うやん」と述べ、本来は昨年の選挙で自民党が惨敗した原因である「政治とカネ」の問題が先にあり、定数削減こそがその論点をすり替えるためのものだと指摘。産経新聞の報道姿勢を「まるっきりポルノ」と酷評した。
4. 日中関係と歴史認識:90年前との類似性への警鐘
産経新聞が、中国による日本産水産物の輸入停止措置を巡り、強硬な論調を展開していることに対し、深刻な懸念が示された。
- 歴史の繰り返し:
- 産経新聞には「我が代表堂々退場する」といった、昭和初期を彷彿とさせる見出しが掲載された。
- インターネット上では「ホタテなんかアメリカとイギリスとフランスに売ったらええやないか」という意見が散見されるが、論者はこれを「90年前の議論と全く一緒です」と断言。
- かつて中国が「日貨排斥運動」を行った際も、「米国が買ってくれる」といった楽観論が存在したが、その5年後には戦争に突入した歴史を指摘した。
- 専門家による警告:
- 日中戦争研究の第一人者である広中先生が、昨今の高市氏らの発言に関連して述べた以下の言葉が、極めて重いものとして引用された。
- この専門家の発言の重みを「大谷翔平がとある高校2年生を見て彼はすごいって言ったらその子はすごいですわね。それと一緒です」と例え、現状への強い危機感を示した。
菅野氏は、この歴史的類似性を学ぶための読書会を計画していることを明かし、事実を直視する必要性を訴えている。
人気ブログランキング

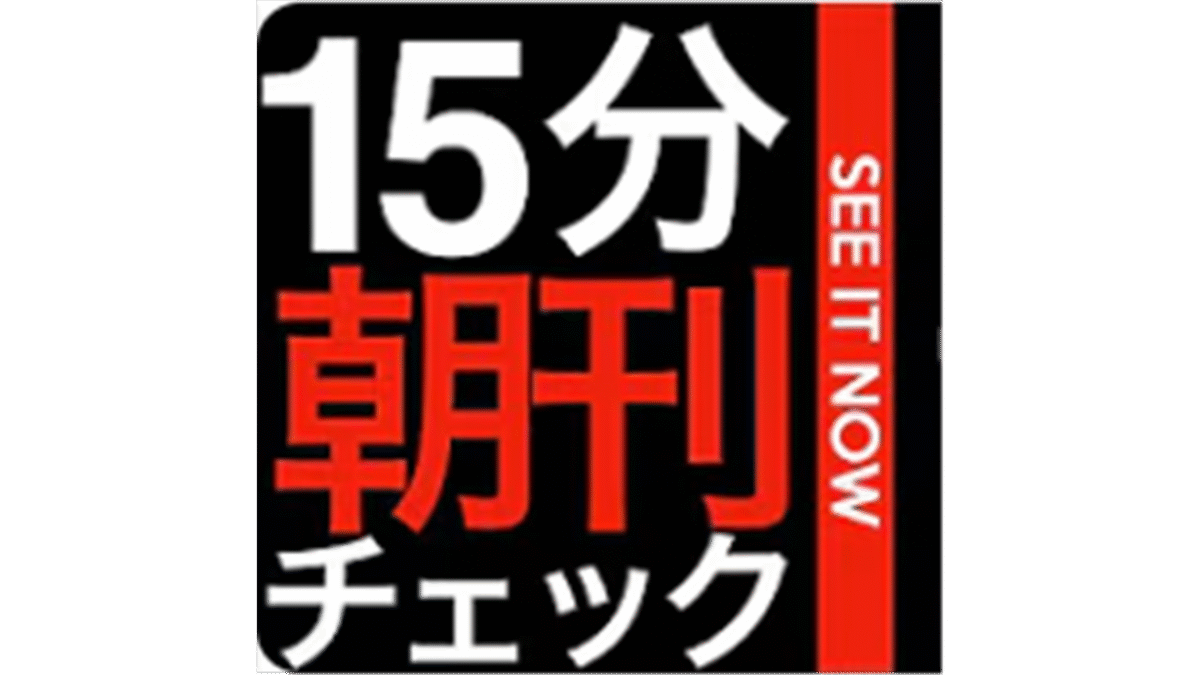




コメント