2025YouTube動画 11/6(木)朝刊チェック:だから立憲民主党は一生選挙に勝てない の情報を基にした記事です
1. 有権者の心理と野党の「必然性」の欠如
野党が選挙に勝てない最大の原因は、有権者が野党に投票する「論理的必然性」がないという基本構造を理解していない点にあります。
- 現職が常に有利なメカニズム: 選挙というものは、政策の是非に関わらず、「行政の安定的な遂行」という観点から、現職(与党)の名前を書く方が合理的かつ心理として素直な判断だからです。選挙は、行政の安定を阻害する「邪魔な存在」でしかありません。
- 野党の使命: この構造の中で、チャレンジャーである野党側は、有権者に**「あえて」自分の名前を投票用紙に書いていただく**というアプローチをしなければなりません。
- 必要なメッセージ: 有権者の頭の中に、「現職だったらダメです。だから私にしてください」というメッセージを入れ込むことが、選挙運動の本質であるとされます。
2. 決定的な戦略の失敗:「並行の戦い」と「正論」の限界
野党が採用している戦略は、勝利に必要な構造を生み出しておらず、結果的に有権者の心に響かない「並行の戦い」に終始しています。
垂直の戦いの放棄
- 多くの野党(立憲民主党、れいわ新選組、共産党)がとるのは、現職の路線を否定しつつも、「一方、僕はこんなことを信じています」と自分の信条や政策を並行的に訴える方法です。
- これは有権者からすると「うん、よかったね、立派なことを言いましたね、素敵素敵」で終わってしまい、投票行動を変える「刺さる」情報とならないと断じられています。
- 勝利に必要なのは、• 相手の「売り」を正面から否定する
- 相手が最もアピールしたい「目玉政策」や「キャラクター」に対し、「それも良いけど、こちらも良いですよ」という代替案ではなく、**「いや、それは完全に間違いです。私はその真逆をやります」**と宣言します。この「真逆」のアプローチが、有権者の「現状維持で良いのでは?」という思考に楔を打ち込み、変化の必要性を鮮烈に印象付けます。
争点設定の放棄
- 野党側は、自分たちで論点設定(争点)をしようと試みてはいけないと強く主張されています。
- 争点は必ず現職や与党側が設定するものであり、野党が独自の争点を作ろうとすると、膨大な労力(市民運動など)を必要とするか、あるいは参政党のようにデマを流すという手法に陥ってしまうため、コストが高すぎるのです。
- 野党は、与党が作った土俵(争点)に乗った上で、その争点を徹底的に否定し、相手の存在そのものを後悔させるほど否定すること(「お前の人生は母の胎内に着床したその瞬間からすべて無駄だったぐらい」)が選挙に勝つ道であるとされます。
有権者に明確な二者択一を迫る
この戦略は、有権者に対して「AかBか」「現状維持か、それとも真逆の変化か」という、非常に分かりやすい選択肢を突きつけます。どちらかを選ぶしかないという明確な対立構図を作り出すことで、有権者の思考を促し、投票所に足を運ばせる強い動機を生み出すのです。
この「垂直に戦う」戦略が、実際の選挙でどのように機能したのか。アメリカの選挙事例を見ていきましょう。
2. 具体例:ニューヨーク市長選挙の戦い方
この戦略の有効性を示す象徴的な事例が、アメリカのニューヨーク市長選挙です。当時、アメリカの政界ではトランプ氏が掲げた「移民ダメ」という排外主義的なアジェンダが、大きな争点として国全体を覆っていました。
この大きな政治的潮流に対し、ニューヨーク市長選の候補者であったマムダニ氏は「垂直に戦う」戦略を完璧に実践しました。彼は、人道的な観点から「移民に優しくしよう」という生ぬるい反論をするのではありません。「移民を減らす」という大きな流れに対して、**「いや、私は移民を増やす」**と宣言し、真っ向から対立する姿勢を示したのです。この戦略は、彼の勝利演説に凝縮されています。
New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. (ニューヨークはこれからも移民の街であり続ける。移民によって築かれ、移民によって動かされ、そして今夜からは、一人の移民によって率いられる街だ。)
この演説が有権者に響いたのは、移民政策の是非を越えて、当時の政治的アジェンダとの対立構図を誰の目にも明らかにしたからです。「トランプが示す道」か「マムダニが示す道」か。有権者にこの二者択一を迫ったことこそが、認知度1%からのジャイアントキリングを成し遂げた最大の要因でした。
この鮮やかな成功例と比べて、日本の野党の戦い方はどうでしょうか。菅野氏が用いた「魚屋」のたとえ話から、その問題点を学びましょう。
正論を述べることの失敗(共産党の例)
- 共産党は常に「正しいこと」(正論)を言っていますが、それは「正しいことを言う活動」になってしまい、選挙には勝てません。例えば、「青魚のDHAは脳にいい影響を与えます」という正論は、聞いている人にとっては「そやね、大人」で終わってしまい、投票行動に繋がる「刺さる」情報ではありません。
3. 具体的な野党への批判:弱腰な「魚屋」の比喩
特に立憲民主党の選挙活動は、「弱腰」で「顧客に媚びた」営業になっており、勝利に必要な強いメッセージを欠いていると酷評されています。
- 立憲民主党の比喩: 立憲民主党の営業は、病気で熱を出して寝込んでいるイワシ(魚)を売ろうとする魚屋のようです。
- 彼らの主張は、「自民党が好きという気持ちもわかるんですけど、たまには僕らのことも思い出してください」というものであり、現職を真っ向から否定せず、「うちのイワシ、ピチピチ」と自らの優位性を誇張する姿勢がありません。
- このような営業方法では、「誰が投票すんねん」と疑問が呈されています。
- 垂直のメッセージ: 勝利する魚屋は、顧客が「肉(現職/与党)を欲しがっている気持ちもわかる」とは言いません。そうではなく、「奥さん、肉なんか食うとあかん!うちのイワシ、ピチピチ!肉よりうまい!」と、現職が売り物にしているもの(肉)を徹底的に否定し、自らの優位性(ピチピチのイワシ)を誇張し、顧客の選択を強制的に変えるような、挑発的で明確な対立軸を打ち出さなければなりません
れいわ新選組の戦略の変質
- れいわ新選組が2019年参議院選挙で盛り上がったのは、当時の自民党の公約が消費税増税だったのに対し、**消費税ゼロ(減税)という「垂直の構造」**を作り出したためです。
- しかし、その後は現職と真っ向から戦う垂直の戦略から逸脱し、「肉あかん、野菜それもあかん…」と全てのものを否定するだけになってしまい、支持率が落ちていると分析されています。
国民民主党の巧妙な営業戦略としての比喩
国民民主党の戦略は、立憲民主党や共産党が陥っている失敗とは一線を画しています。
- 立憲民主党の失敗との対比: 立憲民主党(野田氏や枝野氏)が、病気で熱を出して寝込んでいるイワシ(魚)を売りつけようと、「自民党が好きという気持ちもわかるんですけど、たまには僕らのことも思い出してください」と弱腰に懇願する営業をしているのに対し、国民民主党はそうした戦略的な甘さや消極性を持っていません。
- 看板の使い分けによる機会主義: 国民民主党の巧妙さは、店(党)の看板を固定しない点にあります。
- 魚を欲しそうな客が来たら、「うち魚屋です」と看板を出す。
- 肉を欲しそうな客が来たら、「うち肉屋です」と看板を出す。
- さらには、棚の隅で野菜も売っているように見せかける(なんだったら、野菜も売っている)状況さえあると表現されています。
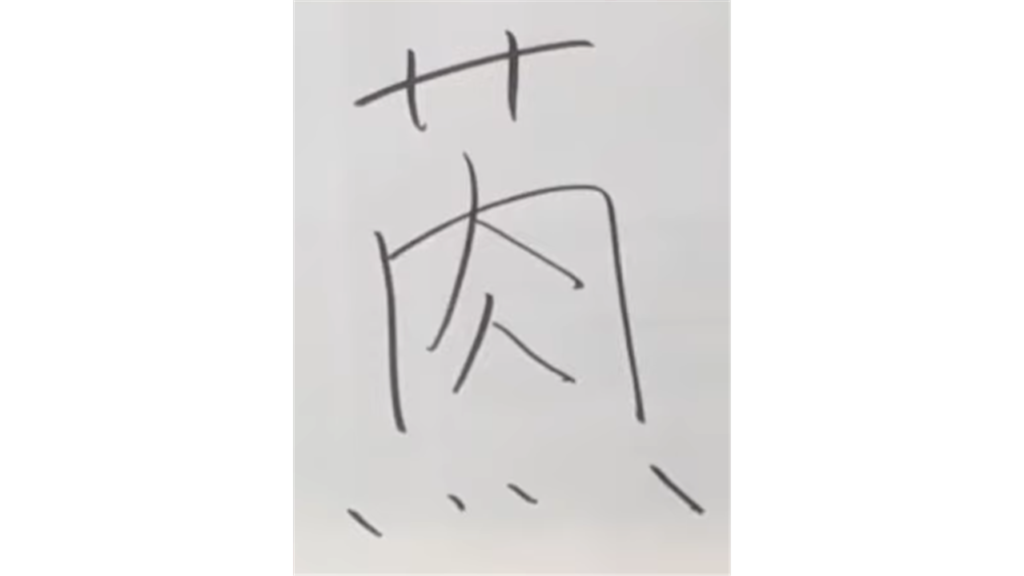
戦略論における国民民主党の位置付け
この看板の使い分けは、特定のイデオロギーや明確な対立軸(垂直の戦い)を放棄し、有権者がその瞬間に求めていると推定される政策やスタンスに柔軟に対応する、という戦略的機会主義を表しています。
野党が選挙に勝つ唯一の方法は、現職(与党)が提示する争点に対して「真逆」のメッセージを「垂直に」ぶつけ、有権者に「現職だったらダメです、だから私にしてください」という必然性を抱かせることだと、この戦略論は主張しています。
しかし、国民民主党の「看板を使い分ける」戦略は、この「垂直の戦い」ではなく、**すべての顧客(有権者層)を取りこぼさないために、その都度姿を変える(多角化・曖昧化する)戦術を示しています。これは、選挙という場において、有権者にとっての「投票する必然性」を明確にするよりも、「どの客にもとりあえず声をかける」**という広範なアピールを優先している状況を表しています。
つまり、国民民主党は他の野党のような「戦い方を知らない魚屋」の失敗は避けつつも、勝利に不可欠な「強烈な垂直のメッセージ」を打ち出す代わりに、「顧客の需要に応じて姿を変える変幻自在の商売人」としての巧妙さを見せていると分析されています。
参政党の「魚屋」戦略
参政党が用いているとされる選挙戦略の特徴と、その比喩が示す内容は以下の通りです。
- 試食品(試食)の配布
- 彼らの戦略は、まず**試食(試食)**を配ることです。
- この「試食」とは、地方議会での議席獲得に例えられています。地方議会での実績や活動を通じて、有権者に「うちの魚は美味しい」と思わせる機会を提供しているのです。
- 購買意欲をそそる手法
- この試食させるという売り方によって、「ここの魚屋さんの魚は美味しいわ」と騙されてしまう人々がいる、としています。
- 具体的には、裏で寝込んでいる魚(実態の伴わない政策や候補者)の鼻くそを丸めて口に入れられたにもかかわらず、「しょっぱくて美味しいわ」と感じてしまう状況です。
- しかし、実際に買って家に帰り焼いてみると、「カスカスやわ」となり、結局お腹を壊してしまう(後で問題に気づく)という結末が示されています。
- 他店(肉屋)への批判
- 参政党は、試食を配るだけでなく、肉屋の悪口を言いながらこの営業活動を行っていると述べられています。
本来理想とされる営業手法は、肉屋でコロッケを買っている客の口の中に焼いたイワシを入れ、「肉より美味いねん、これが本当の油の味や」と積極的に強引にアピールすることであると論じられています。参政党の戦略は、その理想的なアピール方法(試食を通じて購買意欲を喚起する)の一部を実行しているが、その実態に問題がある、という位置づけです。
4. 人事と文化的な問題
選挙に勝てない理由は、戦略の失敗だけでなく、組織の文化的な問題にも根差していると指摘されています。
- 排除の文化の欠如: 立憲民主党は、ゆさみゆき氏のような人物に公認を出している段階で「選挙負けに言っている」と批判されます。
- 提供者は、**「そういうやつを排除しないから立憲民主党は選挙に負ける」**と断じ、このような低俗な要素や人物を明確に「ダメだ」と排除できない文化圏そのものが「腐っている」と述べています。
選挙戦略論の結論
菅野氏が野党に提示する選挙・政治戦略論の結論は、選挙とは「正しいこと」を述べる活動ではなく、有権者に「現職(与党)の選択を後悔させ、あえてリスクを冒して野党を選ぶ」という強い動機付けをさせる行為であるという点に集約されます。
例えるならば、選挙は政策論争という名のフェンシングではなく、相手(現職)が作った土俵に乗り込み、相手の得意な技(争点)を大外刈りで徹底的に倒しにいく格闘技のようなものであると主張されています。相手の攻撃の「真逆」を打ち返す「垂直の戦い」ができなければ、野党はいつまでも「病気の魚」を売る魚屋のままである、というのがこれらの核心的なメッセージです。
人気ブログランキング

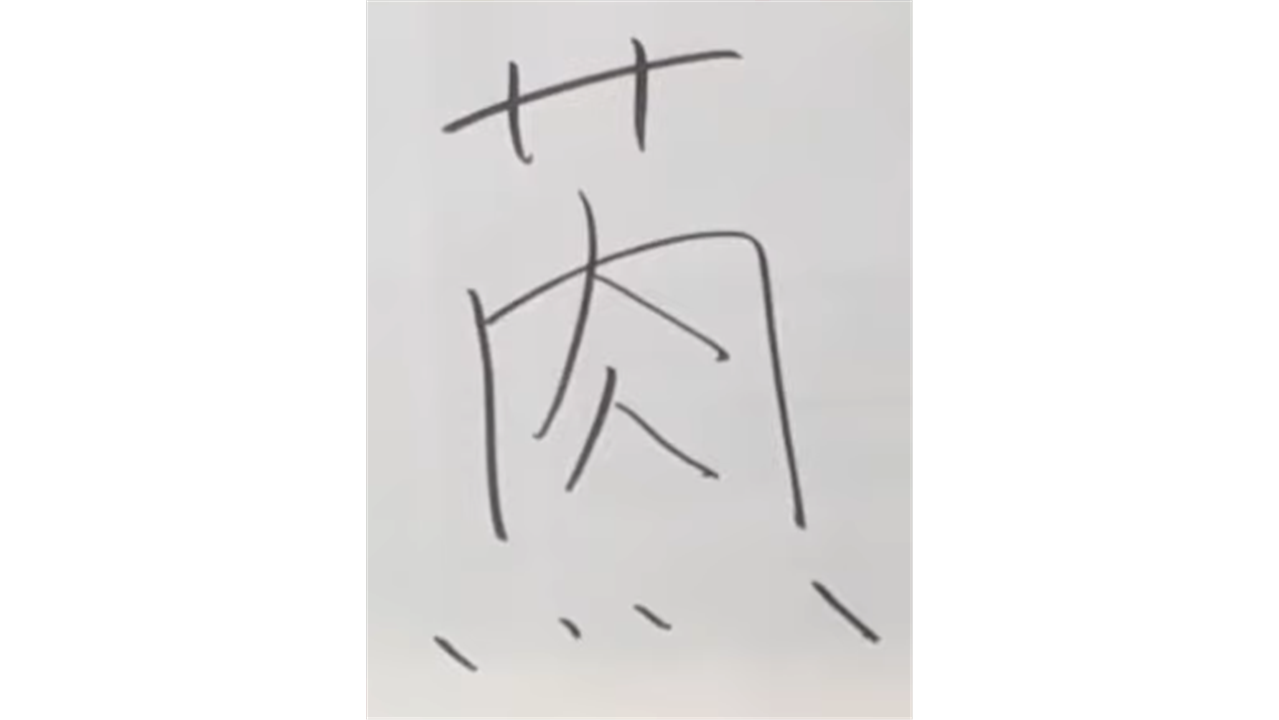


コメント