序論:支持率回復を目指す立憲民主党の迷走
YouTube動画202511/17(月)朝刊チェック:ゆけゆけ高市早苗!憎っくきリベラルどもを蹴散らしてゆけ!!!
立憲民主党が野党第一党としての地位にありながら、なぜ強固な支持を得られないのか。その背景には、単なる政策の不備や個々の議員の問題を超えた、日本社会の特性と党自身の戦略的錯誤に根差した構造的な要因が存在する。本稿では、ある時事解説動画で展開された分析に基づき、その構造的要因を多角的に解明する。
要因1:日本社会に根付く「勝者への追従」という通俗道徳
第一の要因は、日本の有権者、とりわけ地方における投票行動を規定する「通俗道徳」にある。それは、政策の中身よりも「勝者であること」自体を絶対的な価値とする文化である。
野党第一党という「敗者」の宿命
菅野氏は、野党第一党が批判されるのは、その党が立憲民主党であるからではなく、単に「野党第一党」だからだと断言する。これは明治時代から続く日本の伝統的な文化であり、現状の勝者(マジョリティ)を肯定し、それを脅かす可能性のある存在を無条件に否定する傾向に起因する。
「明治時代から日本では通俗道徳の教育が徹底しておりますので、田舎に行けば行くほど野党第一等を批判することが賢いふりだという文化があるんです。…今現状マジョリティでないという段階で何かを間違えてるという風にじゃ考えられない人が、ま、田舎にはいっぱいいるわけです。だからすぐにもうどの政党であれ、野党第一になった瞬間に言われることは『埋没する』『スルー』なんです。それは立憲民主党だからダメじゃないんですよ。野党第一党だからダメなんです」
この文化の下では、野党第一党は「勝っていない」という事実だけで批判の対象となり、何をしようとも「頼りない」「埋没している」というレッテルを貼られ続ける宿命にある。
政策よりも「勝った」という事実
この通俗道徳は、有権者が政策本位で投票しないという現実を生み出している。話者は、日経ビジネスが2021年の衆院選後に行った調査を引用し、衝撃的な事実を提示する。各党の政策を党名を伏せて提示した場合と、「これは自民党の政策です」と説明した場合で、支持率が劇的に変化するのだ。
| 政策分野 | 政策を匿名で提示した場合の支持率 | 「自民党の政策」として提示した場合の支持率 |
| 経済政策 | 共産党の政策が最も高い支持 | 自民党の政策が圧倒的な支持 |
| コロナ対策 | 共産党の政策が最も高い支持 | 自民党の政策が圧倒的な支持 |
このデータが示すのは、多くの有権者が政策の中身を評価しているのではなく、「自民党」という勝者のブランドに追従しているという実態である。
「なんでみんな自民党に投票するか言うたら、自民党が第一党だからですよ。それ別に自民党に対する支持じゃないんです。第一党に対する指示なんです。…これは厳密に言うと、買ってる人に対する(支持)なんです。それが通俗道徳っていうもんです」
高市早苗氏の支持率が高いのも、彼女の思想や政策が支持された結果ではなく、単に「総裁選挙に勝ったから」という極めて単純な力学によるものだと分析されている。この構造を理解しない限り、野党が政策をいくら磨いても支持には繋がらない。
要因2:メディアと時代認識の錯誤
第二の要因は、立憲民主党がメディアの構造変化を全く理解できていない点にある。古いマスメディアの成功体験に固執し、インターネット時代のコミュニケーションの本質を見誤っている。
「1対N」と「1対1」の混同
話者は、テレビやラジオといったマスメディアを「1対N」、すなわち一人の発信者が不特定多数の受け手に情報を一方的に流すメディアであると定義する。一方、インターネット動画配信などのニューメディアは、見かけ上は1対Nに見えても、本質的には発信者と視聴者一人ひとりの間に個別の関係性が存在する「1対1」のメディアであると指摘する。
「ラジオテレビというのはマス メディアという言葉が差し示すように1対Nのメディアなんですね。全く違うもんなんです。で、そこでその1対Nのやり方を1対1のメディアであるインターネットに持ってきてもね、通用しないんですよ」
この構造的な違いを理解せず、旧来のマスメディア出身者をネット担当者に起用する立憲民主党の姿勢は、時代錯誤であり「真逆です」と厳しく批判されている。それは、全く異なるルールで動く新しいプラットフォームに、古い常識を持ち込む愚を犯しているに等しい。
要因3:見当違いのポピュリズムと政権担当能力への疑念
第三の要因として、立憲民主党が打ち出す政策、特に外国人土地所有規制法案に見られる致命的な欠陥が挙げられる。これは、党の理念の混乱、立法プロセスへの無理解、そして政権担当能力そのものへの深刻な疑念を露呈させている。
立法根拠なき「不安」への迎合
この法案は、ネット上の一部に存在する排外主義的な世論に迎合し、「国民の不安や疑念」を立法事実としようとする点において、近代国家の原則を逸脱していると断じられる。
「多く の 国民 が 不安 や 疑念 を 持っ て いる って 成長 会長 が 言う てる ん です けど、すん ませ ん 会長 どの、いつから日本って不安や疑念が立法根拠になる、立法事実になる国になったんです。… なんか知らんけど心配や、は立法根拠にならないですよ。…情緒で立法するなんて。そんな近代国家ないですよ」
これは事実に基づかず感情に訴えかける「ザ・ポピュリズム」であり、本来あるべき立法プロセスを根本から破壊する行為である。
現場を無視した法案が示す能力不足
さらに、この法案は、土地の所有・利用状況を調査する実務を担う地方自治体の現場に、現実的に不可能なほどの過大な負担を強いるものである。このことは、立憲民主党が行政の実態を全く理解していないことの証左とされる。
「すごい負担を、すごい負担を地方自治体の現場に投げるんですよ。…こんな法案出したら地方自治体が『立憲民主党は現場を分かっていない』『立憲民主党には政権担当能力がない』って言われるのが関の山です」
このような現場感覚の欠如は、有権者に「この党に政権を任せられない」という印象を決定的に与えるものとなる。
矛盾した支持層へのアプローチ
この法案で取り込もうとしている支持層は、本来、立憲民主党が掲げる「人権」や「選択的夫婦別姓」といったリベラルな価値観とは相容れない。党内にこれらの価値観を支持する議員がいる限り、排外的な層からの支持を得ることは不可能である。
「この法案でなびくような人々は、選択的夫婦別姓に賛成やとかいう政党を認めません」
これは、誰の支持も得られない、自己矛盾に満ちた戦略であり、「勝っていない人間が勝った人間の真似をするのが一番滑稽です」という痛烈な批判に繋がる。
結論:立憲民主党が進むべき道
これらの構造的な要因を踏まえた上で、話者は立憲民主党が進むべき道を提示する。それは、安易に世論や勝者に迎合することではなく、党の原点に立ち返り、地道な活動に徹することである。
まず、勝者である自民党の真似をすることをやめなければならない。そして最も重要なのは、「語ること」ではなく「聞くこと」に徹することだと強調される。
「立憲民主党に今必要なのは語ることではありません。立憲民主党に今必要なのは耳を傾けることです。…全身を耳にして人民の海に深く潜り込んで、人民が何を求めているか、人民が何を考えているかということを、自分の耳と自分の足で話を聞いて、聞いて、聞いて、聞き倒す行為です」
政治家が何かを主張するのではなく、まず国民の声に虚心に耳を傾け、その中から真の課題を見つけ出すこと。それこそが、支持を失った野党第一党が信頼を回復するための唯一の道であると結論付けられている。
人気ブログランキング



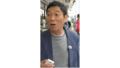
コメント