このモデルは、公明党の選挙活動における**核となる「ビジネスモデル」**として捉えられています。
YouTube動画2025/11/7(金)朝刊チェック: 公明党の怒りが本当によくわかる件から
1. リーダーの人格に基づく運動モデルの核心
公明党が選挙に勝利する際の強さの源泉は、リーダーの人格と熱意に帰依し、それに触発された運動員が活動する点にあると説明されています。
- リーダーの熱意の伝播: 池田大作氏という「巨大な人間」の熱意と情熱(パッション)を運動員が受け取り、それが運動員の体内で熱意と情熱となり、各自が現場で票の集約活動を行うことで、勝利を収めるという構造です。
- 「小さな池田大作」としての活動: 運動員は、それぞれ「小さな池田大作」、あるいは「池田小作」となって活動すると表現されています。例えば、支持拡大のために電話をかける際、運動員たちは皆「小さな池田大作」になって行っている、と説明されています。
- 他の政党との違い: このモデルこそが、公明党が他の政党と異なっている点であると強調されています。
2. リーダーが持つべき「ポテンシャル」
菅野氏は、この運動モデルを機能させるために、特定のリーダーが持つべき人格的・精神的な「ポテンシャル」について言及しています。
- ポテンシャルを持つリーダー: 斎藤鉄夫代表(現職)は、このモデルを機能させられるポテンシャルがあると見なされています。斎藤代表は、その迫力(プレッシャー)が「迷いのない人間が出せる迫力」であると評価されています。また、山口那津男代表(前職)も同様に、高い「徳」(得)と「人間としての位が上」であるという圧倒的な人格的圧力を持ち、そのポテンシャルがあったと述べられています。
- ポテンシャルがなかったリーダー: 一方、石井啓一氏からは、山口氏や斎藤氏のような「ポテンシャル」や「雰囲気」を一切感じなかったと明言されています。
このリーダーの力によって組織のモチベーションが向上し、それが選挙結果に反映されると予測されています。具体的には、斎藤氏の路線によって「組織のモチベーション」が変わり、それによって以前の協力体制時よりも得票率が向上する(例えば、0.6掛けが0.9掛けに戻る)だろうという見解が示されています。
3. 新しい運動方法論との対比
菅野氏は、この伝統的かつ成功してきたビジネスモデルに合わない新しい運動方法論について批判的に言及しています。
- YouTubeサブチャンネルへの懸念: 公明党のYouTubeサブチャンネルは、YouTubeの企画としては成功しているかもしれないものの、公明党のビジネスモデルにはふさわしくないとされています。
- 「池田抜作」の状態: このサブチャンネルは、運動員を「小さな池田大作」にするというプロセスと合致せず、「池田抜作」になってしまったと評されています。
- 運動員のモチベーション: このサブチャンネルは、創価大学の学園祭に孫の顔を見に来るような、組織の核となる信者の「モチベーションに気をつけるとは思えない」ため、得票に結びつかない「逆効果」である可能性が指摘されています。
このたとえ話は、公明党の「サブチャンネル」の企画が、公明党という組織の性質やビジネスモデルに根本的に合致せず、ブランドを損なう行為であるという批判を分かりやすく説明するために用いられています。
トヨタ自動車の閉店セールのの比喩の概要
菅野氏は、公明党のサブチャンネルが、公明党の従来の選挙運動モデル(「小さな池田大作」が熱意をもって活動するモデル)に反していると指摘した上で、このサブチャンネルをやめるべき理由を次のようにたとえています。
- 公明党サブチャンネルの比喩: 公明党のサブチャンネルは、「トヨタがディーラーの壁に閉店大セールって書いてるみたい」なものであると表現されています。
- 「やって良い会社」と「やってはいけない会社」の区別: この比喩の核心は、世の中には「ずっと閉店大セールっていう垂れ幕がかかっている店」が商店街に一件ぐらいあり、そのポップは集客力があり、その店にとっては意味をなしているものの、それを「やって良い会社」と「やってはいけない会社」があるという点です。
- トヨタに不適切な理由: トヨタのような確立された、強力な組織が、ディーラーに「閉店大セール」と書くような行為は不適切であり、**「どうすんねん」**という疑問が呈されています。 (もし日産がやり始めたら、本当に何かあったのかと疑うかもしれないが、トヨタはそうではないという対比も示唆されています。)
- 公明党への適用: 公明党も、トヨタと同様に、その確立された運動方法論から見て、この種の広報戦略(サブチャンネル)は**「やってはいけない会社」**の行為であると結論づけられています。
たとえ話が示す批判のポイント
このたとえ話は、「閉店セール」のような、一時的・扇動的な戦術が、公明党のような**「そんなもんじゃない」**組織(確立された独自の運動方法論を持つ組織)のブランドイメージや、内的な結束力を損なってしまうということを示しています。
具体的には、参政党やれいわ新選組といった他の政党が「そういったレベル」の客層を相手にしているため、同様の戦術を使っても「似合う」かもしれないが、公明党の組織力と運動方法はそれに適していない、という認識が背景にあります。
公明党の運動方法論の観点から見ると、一般の有権者にアプローチすることは難しく、彼らの票は内部の組織力に依存しているため、YouTubeなどの手法が組織内のモチベーションを高めるかどうかが重要であると読み取れます。
人気ブログランキング


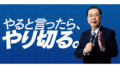
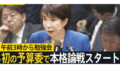
コメント