1990年に発表された中島みゆきの楽曲「やまねこ」。この歌が、30年以上の時を超えて、なぜ今もなお現代社会を生きる私たちの心に深く響くのでしょうか。
菅野完氏が、高市早苗氏とトランプ大統領の会談風景を解説する際にこの曲を引用したことで、その普遍的なテーマ性が改めて注目されました。政治の表舞台で見えた光景と、30年以上前に書かれた歌の言葉が、驚くほど正確に重なり合ったのです。
この記事では、「やまねこ」の歌詞を丁寧に読み解き、そこに描かれた女性の生きづらさと、現代社会に今なお根付くジェンダーロールの問題を結びつけていきます。
——————————————————————————–
1. 歌詞の深層:「やまねこ」が描く“誕生の絶望”
楽曲の冒頭は、女性がこの世に生を受けた瞬間から直面する、社会からの値踏みと期待を衝撃的な言葉で描き出します。
1.1. 「喜んでくれた」人々の正体
歌は、次のような一節から始まります。
女に生まれて喜んでくれたのは / 菓子屋とドレス屋と女衒と女たらし
この4者は、女性の誕生を祝福する人々として描かれていますが、その視線は決して彼女自身の人格に向けられてはいません。それぞれが象徴するものは、女性が社会からどのような役割を期待され、消費されるかという構造そのものです。
- 菓子屋とドレス屋 これらは、女性を「美しく着飾らせ、消費の対象とする」視点を象徴しています。女性であることの価値が、外見的な魅力や、それに付随する経済活動の中に位置づけられていることを示唆します。
- 女衒(ぜげん)と女たらし こちらは、女性を「性的な搾取や、男性の欲望を満たすための対象」と見る、より直接的で暴力的な視点を象徴しています。彼女の存在は、他者の欲望のはけ口として利用される可能性を常に内包しているのです。
これら4者は、女性を主体的な個人としてではなく、それぞれが属する経済圏や欲望のシステムにおける交換可能な「客体」としてしか認識していません。彼女の誕生は、人格の誕生ではなく、新たな市場の誕生として祝福されるのです。
1.2. 聞こえたのは「落胆の溜息」
さらに歌詞は、彼女が最初に聞いた「声」についてこう歌います。
生まれ落ちて最初に聞いた声は落胆の溜息だった
これは、家父長制社会における「跡継ぎ」としての価値を持たない女性の誕生が、必ずしも祝福されないという根深い文化的背景を示唆しています。この「落胆の溜息」は、彼女の自己肯定感の形成に、計り知れない影響を与えたかもしれません。自分自身の存在が、生まれた瞬間から完全には肯定されていないという感覚は、その後の人生における他者との関係性の築き方に、深い影を落とす可能性があります。
このように、歌の冒頭は女性が生まれながらにして社会から押し付けられる価値観と、それによって生じる根源的な疎外感を鮮烈に描き出しています。では、こうした環境で育った女性は、どのようにして世界と向き合っていくのでしょうか。
——————————————————————————–
2. 「傷つけるための爪」:やまねこの生存戦略
過酷な環境を生き抜くため、女性は他者と、そして自分自身と、どのように向き合わざるを得なかったのか。その葛藤が「爪」というメタファーに託されています。
2.1. 「やまねこ」が爪を立てる理由
歌詞の中で、彼女に与えられた唯一の「贈り物」は、皮肉にも他者を傷つけるためのものでした。
傷つけるための爪だけが / 抜けない棘のように光る
この「爪」は、単なる攻撃性や意地悪さではありません。むしろ、自分を消費し、搾取しようとする世界から身を守るための、唯一の自己防衛手段なのです。それは、社会から押し付けられた役割に対する、必死の抵抗の証でもあります。しかし、その爪は「抜けない棘」のように、彼女自身のアイデンティティと分かちがたく結びついてしまい、彼女を苦しめ続けます。
2.2. 愛と支配の「手なずけるゲーム」
彼女を取り巻く人間関係、特に男女関係は、「ゲーム」として描かれます。
手なずけるゲームが流行ってる / 冷たいゲームが流行ってる
この「手なずけるゲーム」とは、社会における男女間の支配・被支配の関係性を巧みに暗喩しています。男性は女性を「手なずけ」、自分のコントロール下に置こうとする。一方で女性は、そのゲームの中で純粋な愛を求めながらも「よそを向かないで抱きしめて」、相手が少しでも自分から目を逸らせば、自己防衛の「爪」を立ててしまう「瞳をそらしたら きっと傷つけてしまう」という、常に緊張をはらんだ関係性の中にいるのです。
このように、「やまねこ」は社会の中で生き抜くための鎧を身につけ、愛を求めながらも常に傷つき、傷つけることを恐れる女性の姿を浮き彫りにします。この構図は、驚くほど現代の私たちを取り巻く状況と重なります。
——————————————————————————–
3. 現代への投影:菅野完氏が指摘した「構造的な地獄」
この歌が描く世界は、決して過去のものではありません。菅野完氏は、高市早苗氏とトランプ大統領の映像を分析する中で、「やまねこ」のテーマが現代社会にどう映し出されるかを鋭く指摘しました。
3.1. 「おっさんに媚びなければ出世できない社会」
菅野氏が問題視したのは、国家間の関係性といったマクロな視点ではありませんでした。彼が注目したのは、日本の女性政治家が、男性政治家の隣で**「キャピキャピした」特定の女性的役割を演じなければならないかのように見える、ジェンダーロールの構造**そのものでした。
高市氏の振る舞いが個人の資質の問題なのではなく、日本の社会構造が、権力を持つ男性の前で女性に特定の役割を強いているのではないか、という問いを投げかけたのです。
3.2. 歌詞と現実が重なる瞬間
菅野氏は、この根深い構造を説明するために、まさに「やまねこ」の歌詞を引用しました。
女に生まれて喜んでくれたのは菓子屋とドレス屋と女衒(ぜげん)と女たらしです…女はこれ(特定の役割を演じること)を強いられてるの。そして政治はその女性を救えていないの。
…おっさんに媚びへつらわなければ女は出世できないという社会の空気を敷いてる…それでのし上がると今度は女は楽でええよね、媚び売ってりゃ出世できるんだからって言われる。そこまでがセットの地獄の中で女の人を生活させてるっていうこと…
トランプという圧倒的な権力者の隣で「キャピキャピした女性」を演じることは、まさに「やまねこ」が歌う、愛と支配が混在する「手なずけるゲーム」への参加を強いられる構造そのものです。そして菅野氏が指摘する「媚び売ってりゃ出世できる」という非難は、ゲームに勝利したやまねこが、その生存戦略そのものを理由に価値を貶められる、二重の地獄を浮き彫りにしています。
菅野氏の指摘は、「やまねこ」の歌詞が単なる過去の物語ではなく、今なお社会の至る所に存在する根深い問題を描き出していることを、私たちに突きつけます。
——————————————————————————–
4. 結論:「やまねこ」の爪は、私たち自身に向けられているのかもしれない
ここまで見てきたように、中島みゆきの「やまねこ」は、女性が生まれながらにして直面する社会の不条理な価値観と、その中で生き抜くための痛みを伴う生存戦略を見事に描き出しています。
菅野完氏の解説を引くまでもなく、この歌が描く「構造的な地獄」は、現代社会で女性が直面するジェンダーロールの押し付けや、成功と引き換えに払う代償の問題に直結しています。1990年の歌が2024年の政治風景を最も的確に切り取るメタファーであり続けるという事実は、日本の社会構造におけるある種の停滞を、そしてジェンダーをめぐる課題がいかに根深く、時代を超えて横たわっているかを雄弁に物語っているのです。
この息苦しい「手なずけるゲーム」は、果たして過去の遺物でしょうか。いや、社会のあらゆる場面に偏在するのではないでしょうか。
「やまねこ」が光らせる爪は、特定の誰かに向けられたものではありません。それは、女性に特定の役割を強いる社会の「空気」そのものへ、そして時には、無自覚にその空気に加担してしまっている我々一人ひとりの内面へと、鋭く向けられています。この歌は、その痛みを伴う自己批判を、今もなお私たちに迫り続けているのです。
人気ブログランキング

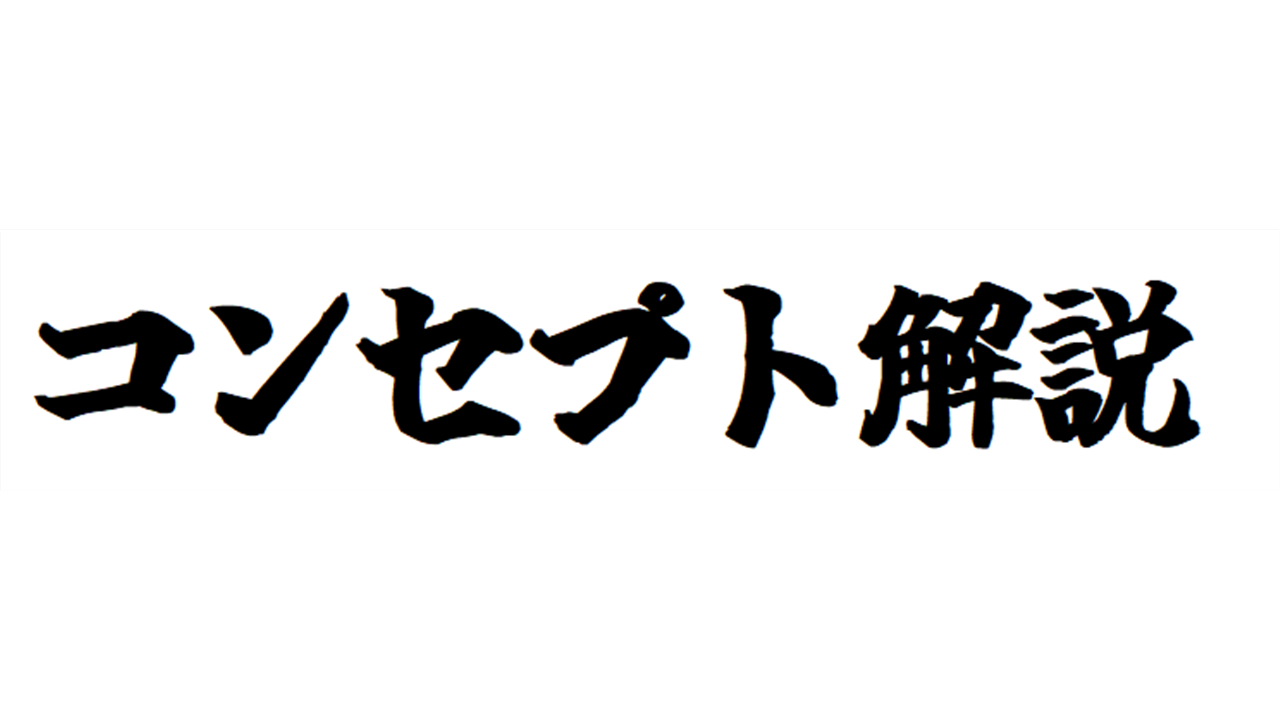


コメント