本書の概要と学術的意義
江口圭一著『十五年戦争小史』は、1931年9月18日の柳条湖事件から1945年8月の敗戦までを一連の「十五年戦争」として捉え、その複雑な過程と全体像をまとめた画期的な通史である。歴史学者の加藤陽子氏が指摘するように、本書は大学の講義資料を基に執筆され、戦争の原因・経過・帰結を平明かつコンパクトに解き明かすことに重点を置いている。特に、各段階において年表、地図、制度説明、組織変遷、人事系統の「5点セット」が周到に組み込まれており、読者が歴史の因果関係を深く理解できるよう配慮されている。
本書の核心は、江口氏が提唱した「二面的帝国主義論」にある。これは、戦前期日本の構造的矛盾、すなわち経済的には英米に大きく依存しながら、軍事的にはそれらの列強に対抗しようとする「二面性」を分析の基軸に据えるものである。この根本的な矛盾が、国内に対立する二つの対外政策路線を生み出したと江口氏は論じる。
- 対米英協調路線: 天皇・元老を擁する宮中グループ、民政党、財界主流などが支持。ヴェルサイユ・ワシントン体制という既存の国際秩序の枠内で国益を追求する路線。
- アジア・モンロー主義的路線: 軍部、民間右翼、政友会などが支持。英米主導の国際秩序を打破し、アジアにおける日本の排他的覇権を確立しようとする路線。
『十五年戦争小史』は、この二つの路線の対立と、最終的にアジア・モンロー主義が暴走していく過程を、国内の権力闘争と国際関係の変動を織り交ぜながら克明に描き出している。
——————————————————————————–
戦争の展開:5.15事件から華北分離工作まで
第1部:満州事変と国際的孤立 (1931-1933)
満州国承認と国際連盟脱退
満州事変後、日本は国際社会からの孤立を深めていく。関東軍の作暴によって建国された満州国を日本政府が承認する方針を固めると、国際世論は硬化した。特に、1932年8月に内田康哉外相が国会で行った演説は、日本の非妥協的な姿勢を象徴している。
「満州国承認に就て日本国民は国を焦土としてもこの主張を徹することに於ては一歩も譲らないと云ふ決心を持って居る」 — 内田康哉外相
リットン調査団の報告書は、満州事変を日本の自衛権の発動とは認めず、満州国も住民の自発的な独立運動によるものではないと断定した。しかし同時に、中国側の排日運動にも紛争誘発の責任があるとし、満州に広範な自治を与える国際管理案を提案するなど、常任理事国である日本に対して融和的な解決策を提示していた。
しかし、国内では朝日新聞や毎日新聞が世論を煽り、軍部の意向も強く働いた結果、日本政府はこの妥協案を完全に拒絶。1933年2月24日、国際連盟総会でリットン報告書に基づく勧告案が賛成42、反対1(日本のみ)で可決されると、代表の松岡洋右は議場から退場し、日本は国際連盟からの脱退を決定した。
この一連の動きは、第一次世界大戦後の国際秩序であるワシントン体制を、常任理事国である日本自らが破壊する行為であった。これは、ヒトラーが台頭し、国際秩序への挑戦を始めるよりも前の出来事であり、世界史的に見て日本がヴェルサイユ・ワシントン体制の最初の破壊者となったことを意味する。
ガバナンスの崩壊と関東軍の暴走
日本のガバナンス崩壊の決定的な転換点、すなわち「ポイント・オブ・ノーリターン」は、満州事変の初期、朝鮮軍司令官であった林銑十郎が独断で国境を越えて関東軍を支援した際、陸軍刑法に基づき死刑とすべきこの行動を昭和天皇が最終的に追認してしまったことにある。この一件により、現地軍が既成事実を作れば中央政府や天皇さえもそれを追認するという前例が生まれ、軍の統帥権は崩壊し、現地軍の暴走に歯止めが効かなくなった。
このガバナンス不在は、関東軍による熱河作戦へと繋がる。この作戦の大きな動機の一つは、熱河省が特産品とするアヘンにあった。岸信介(後の首相)らが主導し、笹川良一や児玉誉士夫が関与する特務機関がアヘンの密売組織を形成し、その利益が関東軍の活動資金となっていた。
1933年5月の塘沽停戦協定は、一般的に満州事変の終結点とされるが、これはあくまで国民党正規軍との戦闘停止を意味するに過ぎなかった。協定後も満州では抗日ゲリラとの戦闘が続き、日本側もこれを「満州事変の死傷者」としてカウントし続けた。むしろこの協定は、満州の支配を既成事実化し、次の段階である華北分離工作への足場を固めるためのものであった。
第2部:国内の混乱と華北分離工作 (1933-1936)
陸軍内の派閥抗争:皇道派 vs. 統制派
満州事変を主導したアジア・モンロー主義勢力の内部では、深刻な派閥抗争が進行していた。
| 派閥 | 主要人物 | 思想・方針 |
| 皇道派 | 荒木貞夫、真崎甚三郎 | 天皇中心の精神主義を掲げ、クーデターによる「昭和維新」を目指す。青年将校グループに支持される。対ソ連主戦論を主張。 |
| 統制派 | 永田鉄山、東条英機 | 第一次世界大戦を教訓に、国家の全てを戦争に動員する「国家総力戦」体制の構築を目指す。クーデターではなく、官僚や財閥と連携し合法的に国家改造を進めることを志向。 |
当初は荒木陸相を中心に皇道派が主流を握るが、その非現実的な精神論は次第に支持を失う。代わって、永田鉄山を中心とする統制派が台頭し、陸軍中央を掌握していく。この対立は、統制派による皇道派青年将校のクーデター計画の摘発(士官学校事件)や、皇道派の相沢三郎中佐による永田鉄山斬殺事件(相沢事件)へと発展し、陸軍内の亀裂は決定的なものとなった。
二・二六事件と準戦時体制の確立
1936年2月26日、満州への転出命令を左遷と受け取った皇道派青年将校らが約1500名の兵力を率いてクーデターを決行。斎藤実内大臣、高橋是清蔵相らを殺害し、永田町一帯を占拠した。
青年将校らは、天皇に直接実情を奏上し「ご裁断」を仰ぐことで「昭和維新」が実現すると考えていたが、重臣を殺害された昭和天皇は激怒し、断固たる鎮圧を命じた。これにより反乱は失敗に終わる。
しかし、この事件を最大の好機として利用したのが統制派であった。彼らはこの反乱を鎮圧する過程で「カウンター・クーデター」を遂行。事件の責任を問い皇道派の将軍らを予備役に追い込む一方、後継の広田弘毅内閣に対しては、軍部大臣現役武官制を盾に組閣へ介入し、自由主義的な閣僚候補を排除させた。
これにより、軍部(特に統制派)の政治的発言力は飛躍的に増大し、政党政治は完全に形骸化。同時に、美濃部達吉の天皇機関説を排撃する国体明徴運動や、大本教、ひとのみち教団(後のPL教団)といった宗教団体への弾圧が激化し、自由主義的な思想さえもが排除される国家総動員への道、すなわち「準戦時体制」が確立された。アジア・モンロー主義路線が、国内政治において完全な勝利を収めた瞬間であった。
第3部:中国の抵抗と戦争前夜 (1935-1937)
華北分離工作と経済的侵略
国内で主導権を握った統制派は、満州の安全保障と資源確保を名目に、華北地方を中国国民政府の支配から切り離す「華北分離工作」を本格化させる。板垣征四郎ら関東軍の現地部隊が中央の方針を無視して暴走し、河北省東部に日本の傀儡政権である冀東防共自治政府を樹立した。
この冀東政権を利用し、日本は「特殊貿易」と称する大規模な密貿易を展開。国民政府が定める関税の1/4から1/7という低関税で日本商品を大量に中国市場へ流入させた。これは米英などが借款を通じて行う投資とは異なり、中国の地場産業や民族資本家と直接競合するものであり、彼らを急速に抗日運動へと向かわせる結果を招いた。
西安事件と第二次国共合作
日本の露骨な侵略は、長らく内戦を続けていた中国国民党と共産党の関係を劇的に変化させた。共産党は「兄弟牆に鬩げども、外その侮りを防ぐ」(兄弟は内輪で争うことはあっても、外からの侮りに対しては共に防ぐ)として、内戦停止と抗日民族統一戦線の結成を呼びかける「八・一宣言」を発表した。
この流れを決定づけたのが、1936年12月の西安事件である。共産党討伐の最前線にいた張学良が、討伐命令を督促しに来た蔣介石を突如監禁。内戦を停止し、一致して抗日に当たるよう説得した。共産党からも周恩来が説得に加わり、最終的に蔣介石はこれを受け入れ、10年にわたる内戦は終結。抗日を旗印とする「第二次国共合作」が成立した。
これにより、日本がこれまで侵略を容易に進められてきた最大の要因であった「中国の分裂」という条件が消滅。日本は、全中国を敵に回すという絶望的な状況に直面することとなった。
石原莞爾の「賢者モード」と統制不能の世論
この深刻な情勢変化を唯一冷静に認識していたのが、皮肉にも満州事変の首謀者である石原莞爾だった。陸軍作戦課長となっていた彼は、中国の統一という現実を前に、これ以上の対中強硬策は泥沼化を招くと判断し、華北での軍事工作を停止する方針を打ち出した。
しかし、石原自身が満州事変で火をつけたナショナリズムの炎は、もはや彼のコントロールを離れていた。軍部内からも、そして大衆世論からも、石原の「弱腰」な方針は猛烈な反発を受けた。林銑十郎内閣はこの方針転換を試みるも、世論の反発で短期に終わり、後継の近衛文麿内閣の下で、日本はついに盧溝橋事件をきっかけとした全面戦争へと突入していく。石原が始めた祭りは、彼自身にも止められない規模にまで拡大してしまっていた。
——————————————————————————–
結論:計画なき暴走としての戦争
『十五年戦争小史』が描き出すのは、緻密な国家戦略や一貫したイデオロギーに基づく戦争ではない。むしろその実態は、国内の派閥抗争、出先機関の暴走、その場しのぎの対策の連鎖であり、行き当たりばったりの行動が更なる状況悪化を招き、泥沼に沈んでいく過程そのものであった。
菅野完氏が指摘するように、「日本はアジア解放のために戦った」という肯定的な見方も、「日本人は邪悪で残虐だった」という否定的な見方も、ある意味では共に「美化」である。なぜなら、どちらの見方も、日本の行動に何らかの一貫した意図や計画があったことを前提としているからだ。
しかし、史実が示すのは、国家的な政策も戦略も欠如したまま、内向きの論理と被害妄想に突き動かされ、破局へと突き進んだ姿である。その本質は、計画性の欠如であり、知性の敗北であったと言える。この戦争の最も恐ろしい教訓は、崇高な理念や邪悪な意図がなくとも、「単なる愚かさ」の連鎖だけで国家が破滅しうるという事実にある。
人気ブログランキング

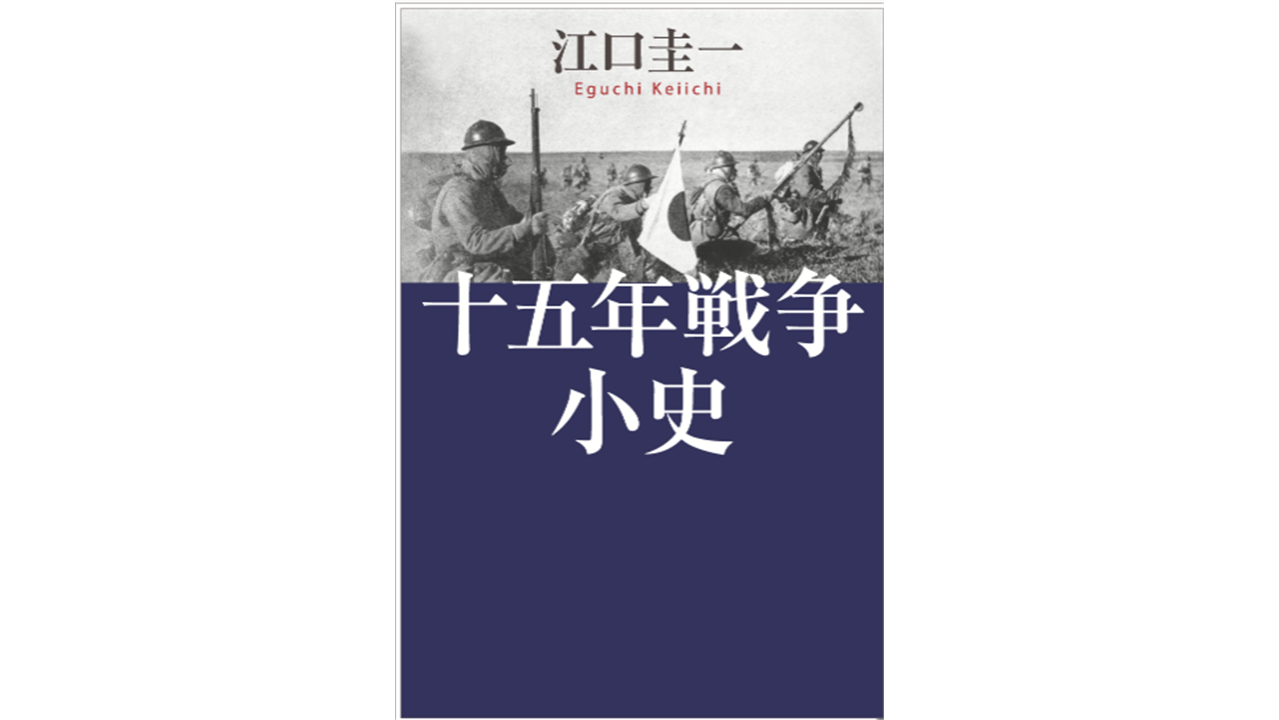

コメント