はじめに:画期的通史としての『十五年戦争小史』
江口圭一著『十五年戦争小史』は、1931年の満州事変から1945年の敗戦までを一連の「十五年戦争」として捉え、その曲折に満ちた過程と全体像を克明に描いた画期的な通史である。本書は、戦争がなぜ、誰によって起こされ、どのような事態がもたらされたか、その原因・経過・帰結を明らかにすることに重点を置いている。大学の講義録を元に平明かつコンパクトにまとめられており、長年にわたり多くの読者に読み継がれてきた。特に、年表、関係地図、制度説明、組織変遷、人事系統の5点を周到に組み込むことで、複雑な歴史事象の因果関係を極めて分かりやすく解説している点が、日本近現代史研究者の加藤陽子氏(東京大学教授)専門家からも高く評価されている。
本稿では、本書の核心的な歴史観を概説するとともに、YouTubeチャンネル「菅野完」の読書会で詳説された日中戦争から太平洋戦争に至る過程の主要な論点を整理・要約する。
第1部:『十五年戦争小史』が提示する歴史の構造
1. 「十五年戦争」の時代区分
江口圭一氏は、この戦争を以下の三つの段階に区分している。
- 満州事変(1931年 – )
- 狭義の満州事変(1931年9月 – 1933年5月 塘沽停戦協定)
- 華北分離工作
- 日中戦争(1937年 – )
- アジア太平洋戦争
この一貫した枠組みにより、個別の事件が全体の中でどのような位置を占めるかを理解することが可能となる。
2. 日本帝国主義の「二面的帝国主義論」
本書の分析の根幹をなすのが、江口氏が提唱した「二面的帝国主義論」である。これは、戦前期日本の構造的矛盾を指摘するものである。
- 経済的脆弱性と対米英依存: 日本は経済的には英米に依存しなければ存立できない脆弱な構造を持っていた。
- 軍事的自立性と対米英対抗: その一方で、経済的依存によって得た力で、軍事的には大国として英米に対抗しようとする自立性も有していた。
この根源的な「二面性」から、第一次世界大戦後、日本の対外政策には相反する二つの路線が生まれ、激しく対立した。
- 対米英協調路線: ヴェルサイユ・ワシントン体制という国際秩序を是とし、英米との協調を重視する。主な担い手は天皇・元老を擁する宮中グループ、民政党、財界主流など。
- アジア・モンロー主義的路線: 国際秩序を無視してでもアジアにおける日本の権益拡大を目指す。主な担い手は軍部、民間右翼、政友会など。
1930年代以降の日本の歴史は、この「アジア・モンロー主義的路線」を支持する勢力が、クーデターや謀略といった実力行使によって「対米英協調路線」を打破していく過程として描かれる。
第2部:日中戦争から太平洋戦争への道程
1. 盧溝橋事件と戦線拡大:偶発から全面戦争へ
満州事変が関東軍による計画的謀略であったのに対し、1937年7月7日の盧溝橋事件は、偶発的な現地での小競り合いであった。しかし、この偶発的事件が全面戦争へと発展した背景には、日本の指導層の構造的な問題が存在した。
- 「新しいおもちゃ」としての国家総動員体制: 第一次近衛文麿内閣のもとで整備された国家総動員体制は、戦争遂行のために作られたというより、むしろ「体制を作ったから戦争をしたくなった」という本末転倒の状況を生み出した。指導者たちは、この新しい権力装置を使いたがっていた。
- 陸軍中央のガバナンス崩壊: 陸軍内部では、中国の戦力を侮り「一撃」で屈服させられるとする拡大派(武藤章ら)と、対ソ戦備を優先し慎重な態度をとる不拡大派(石原莞爾ら)が対立。しかし、かつて石原自身が上官の命令を無視して満州事変を主導した経緯から、陸軍内には下剋上の風潮が蔓延しており、石原の説得は若い将校たちに通じなかった。
- 政府による拡大決定: 現地では停戦協定が結ばれたにもかかわらず、東京の近衛内閣は「重大決意」のもと早々に華北への派兵を決定。満州事変の際に政府が不拡大方針を取ろうとしたのとは対照的に、政府自らが戦争拡大の主導権を握った。
柳条湖事件では現地軍が謀略と独断により戦争を拡大したのに対し、政府はともかくも不拡大方針をとったのであるが、盧溝橋事件では現地での停戦協定成立にもかかわらず、政府は「重大決意」のもと早々と華北派兵を決定し、挙国一致の戦争協力体制をつくりだした。
2. 泥沼化する戦線と南京事件
日本軍は「一撃論」に基づき短期決戦を目論んだが、中国国民政府は首都を南京から重慶へ移し、広大な国土を利した戦略的撤退(時間稼ぎ)で対抗。日本軍は中国大陸の奥深くへと引きずり込まれ、戦線は泥沼化する。
この過程で、日本の戦争指導の無計画性と非人道性が露呈したのが南京事件である。
- 構造的要因:
これらの要因が重なり、軍は「匪賊のような軍隊」と化し、1937年12月13日の南京占領後、捕虜や民間人に対する大規模な虐殺、略奪、暴行が組織的に行われた。第16師団長・中島今朝吾中将の日記には、その実態が克明に記されている。
大体捕虜はせぬ方針なれば、片端よりこれを片付けることとなせりども、これを片付けるに数千人なれば、相当大なる壕を要し、なかなか見当たらず。一案としては100、200に分割したる後、適当の箇所に誘き出して処理する予定なり。
3. 政治と軍部の責任:誰が戦争を望んだか
一般的に「軍部の独裁」によって戦争が遂行されたと理解されがちだが、『十五年戦争小史』は政治家の責任にも厳しく言及する。
- トラウトマン工作の頓挫: 1937年末、ドイツを仲介役とした和平工作(トラウトマン工作)が進められた際、陸軍の一部はこれ以上の戦線拡大に限界を感じ、和平に傾いていた。しかし、これを覆し、より強硬な条件を突きつけたのが近衛文麿首相であった。
- 近衛声明「国民政府を対手とせず」: 和平交渉がまとまらない中、近衛首相は1938年1月、「帝国政府は爾後国民政府を対手とせず」との声明を発表。これにより、日本は自ら交渉の窓口を閉ざし、長期戦への道を突き進むことになった。
これは、軍部だけでなく、近衛文麿をはじめとする政治家たちが、国内の熱狂的な世論に乗り、戦争拡大を積極的に主導した事実を示している。軍部の暴走を政治が追認・扇動した構図が浮かび上がる。
4. 国際情勢への無知と翻弄
日本は、国際情勢のダイナミズムを理解できず、特に同盟国であるはずのドイツに翻弄され続けた。
- ノモンハン事件と独ソ不可侵条約: 1939年、関東軍の一部はソ連の脅威を過大評価し、ノモンハンでソ連軍と衝突。結果は日本軍の惨敗であった。この敗北の衝撃が冷めやらぬうちに、日独防共協定でソ連を敵としていたはずのドイツが、突如ソ連と不可侵条約を締結。日本政府は梯子を外され、平沼騏一郎内閣は「欧州の天地は複雑怪奇なり」との声明を残して総辞職した。
- 日独伊三国同盟: 日本はドイツのヨーロッパでの電撃的な勝利に焦り、1940年に日独伊三国同盟を締結。これにより、アメリカやイギリスから明確に「反民主主義陣営」と見なされ、国際的に孤立した。
- 大東亜共栄圏の虚構: この時期、松岡洋右外相によって「大東亜共栄圏」というスローガンが初めて掲げられた。これはアジア解放という大義を後付けしたものであり、実態は資源獲得のための侵略であった。
5. 経済的破綻:足元からの崩壊
軍事的な侵略とは裏腹に、日本の経済的基盤は極めて脆弱であった。
- 法幣工作の敗北: 中国では、イギリスの支援を受けた幣制改革が成功し、国民政府が発行する「法幣」が安定した通貨として流通していた。日本軍は占領地で軍票(日本円)を流通させようとしたが信用を得られず、中国人だけでなく欧米商人からも取引を拒否された。軍事的に占領しても、経済的には支配できなかったのである。
- 石油の対米依存: 最も致命的だったのは、戦争遂行に不可欠な石油の大部分を、対立を深めていたアメリカからの輸入に頼るという根本的な矛盾であった。
米英と政治的・軍事的に対抗の度を強めながら、経済的には米英に依存しつづけるという日本帝国主義の二面性の矛盾は、ついにその限界を突き破った。
第3部:破滅への最終選択
1. 石油禁輸と「三つの選択肢」
北部仏印進駐などを強行した日本に対し、アメリカは1941年8月、対日石油輸出を全面禁止。これにより、日本の備蓄石油は平時でも2年足らずで枯渇する見通しとなり、帝国は決定的な岐路に立たされた。
- 破滅を賭しても南方へ進出し、資源を確保して米英と全面戦争に突入するか。
- 南方進出を断念し、日中戦争の泥沼の中でジリ貧となって自滅するか。
- これまでの成果を全て放棄し、大転換(全面撤兵)を行うか。
当時の日本の指導者たちは、破滅的であると知りながら、最初の道を選択した。
2. 御前会議と開戦決定
1941年9月6日の御前会議で「帝国国策遂行要領」が決定された。その内容は、「外交交渉の努力は続けるが、10月下旬までに要求が通らない場合は、対米(英・蘭)開戦を決意する」という、戦争準備と外交交渉を並行させる矛盾したものであった。
会議の席上、昭和天皇は日中戦争が短期で終わると述べた陸相(当時)の杉山元に対し、「支那の奥地は広いというなら、太平洋はもっと広いではないか。いかなる成算あって3ヶ月と申すのか」と懸念を示した。しかし、最終的には開戦準備を進める案が承認された。
この決定を覆せるのは陸軍を抑えられる人物しかいない、との期待から東條英機が首相に就任したが、主戦論者である東條にその役割を期待すること自体が、指導層の希望的観測と無責任さの表れであった。
3. ハル・ノートと戦争責任
アメリカとの最後の交渉で提示されたハル・ノートは、満州事変以前の状態に戻すこと、すなわち中国・仏印からの全面撤兵などを要求するもので、日本側には到底受け入れられない最後通牒とされた。
しかし江口氏は、このハル・ノートを「ポツダム宣言の原型」と位置づける。
ハル・ノートを受諾した方が、日本にとってはるかに賢明であり、歴史に栄誉を残す選択であったことは明らかであろう。
結果的に日本は、さらに甚大な犠牲を払った末に、ハル・ノートより厳しいポツダム宣言を受諾することになった。この事実は、日本の戦争指導者たちが、国家国民を道連れに、最後まで合理的な判断を下せなかったことを示している。
結論:『十五年戦争小史』が示す戦争の本質
『十五年戦争小史』は、十五年戦争が壮大な国家戦略や思想に基づいて遂行されたものではなく、むしろその逆であったことを明らかにする。江口氏が本書の結論部で指摘するように、戦争の本質は以下のように要約できる。
- アジア太平洋戦争は日中戦争の延長であった: 日中戦争の「成果」に固執したことが、対米交渉を決裂させ、より大きな戦争へと導いた。
- 陸軍のエゴイズム: 陸軍は、中国から撤兵すれば組織が瓦解することを恐れ、その存在と機構を維持するために国家国民を道連れにした。
- 天皇・宮中グループの無責任: 天皇やその側近は、皇室の安泰を最優先し、国難に際して decisive な行動を取ることを回避した。
アジア解放という「美化」も、日本人の根源的な残虐性という「自己批判」も、的を射ていない。この戦争の実態は、指導者たちの**「見通しの甘さ、場当たり的な対応、メンツ、そして逆張り」**が積み重なった結果であり、無計画なまま破滅へと突き進んだ、単なる愚行の連鎖であった。
人気ブログランキング

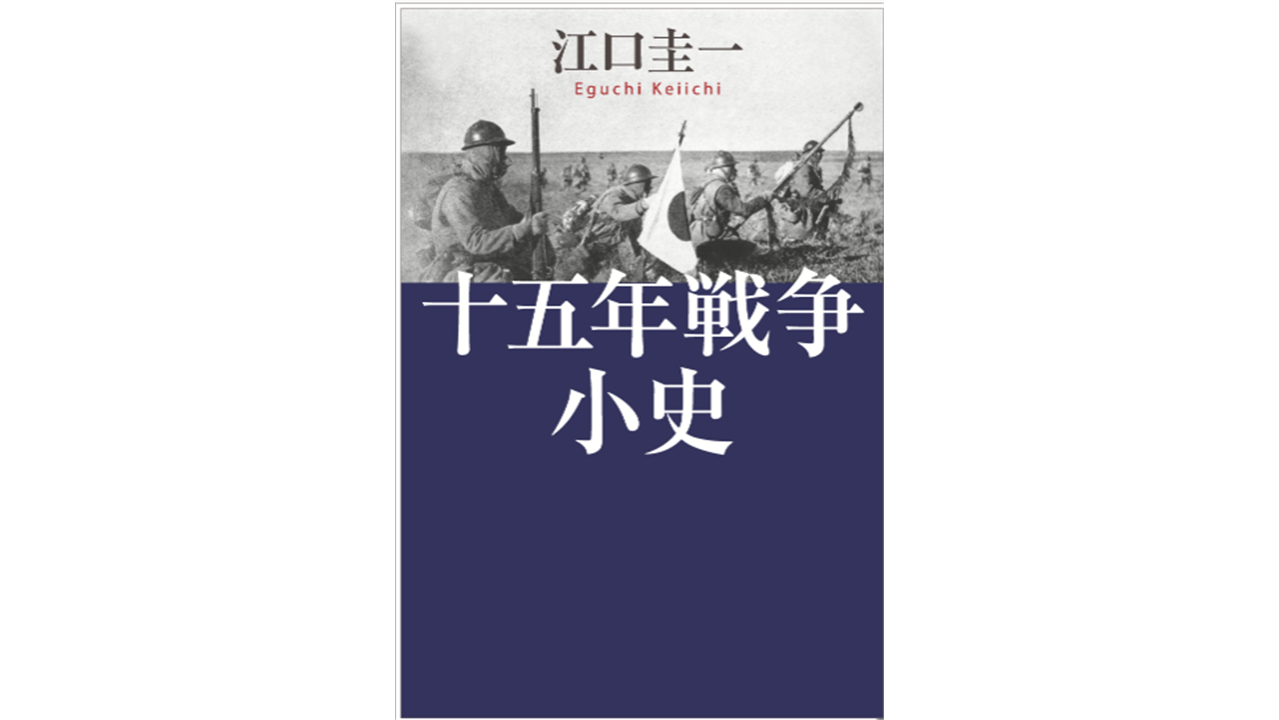

コメント