はじめに:画期的通史としての『十五年戦争小史』
江口圭一著『十五年戦争小史』は、1931年の満州事変勃発から1945年の敗戦までを一連の「十五年戦争」として捉え、その複雑な過程と全体像を描き出した画期的な通史である。本書は、戦争がなぜ、誰によって引き起こされ、拡大していったのかという原因・経過・帰結を明らかにすることに重点を置いている。
日本近現代史研究者の加藤陽子氏(東京大学教授)は、本書が大学の講義用テキストとして極めて優れている点を指摘する。年表、地図、制度説明、組織、人事という「5点セット」を周到に組み込むことで、読者は事実関係の確認で思考を中断されることなく、歴史の因果関係を深く理解できる構成となっている。
本稿では、YouTubeチャンネル「菅野完」で展開された読書会の内容と、加藤陽子氏による解説文を基に、江口圭一が提示した『十五年戦争小史』の核心的な論点を整理・要約する。
第1部:戦争前夜の日本構造 ― 二面的帝国主義
本書の根幹をなす分析視角が「二面的帝国主義」論である。これは、十五年戦争へと突き進んだ大日本帝国の構造的矛盾を解き明かす鍵となる概念である。
経済的脆弱性と軍事的膨張の矛盾
当時の日本は、世界有数の軍事大国としての地位を確立していた一方で、その経済的基盤は極めて脆弱であり、主要な競争相手であるイギリスとアメリカに深く依存していた。
- 資源・貿易面での依存: 軍隊を維持するための不可欠な戦略物資(鉄、石油、ゴム、綿など)のほとんどを、アメリカおよびイギリス植民地からの輸入に頼っていた。この輸入代金を支払うための輸出品は、主に生糸や綿製品であり、これらは代替可能な不安定な商品であった。
- 金融面での依存: 日露戦争の戦費の大部分を外債で賄ったように、帝国主義的な対外膨張は、競争相手である英米からの資本輸入(借金)によって支えられるという「転倒した事態」にあった。1929年末時点で、日本の対外債務は対外投資を約8億円上回る「債務超過」状態だった。
この構造は、「経済的にはアメリカ・イギリスに依存し、その依存によって軍事大国としての自立を維持する」という深刻な矛盾を内包していた。
二つの対外政策路線の対立
この構造的矛盾から、日本の対外政策は二つの対立する路線を生み出した。
| 路線名 | 主張 | 主な担い手 |
| 対英米協調路線 | 経済的な英米依存という現実を直視し、ワシントン体制に順応して国際協調を維持することが国益にかなうとする現実主義的な路線。 | 天皇・元老を擁する宮中グループ、民政党、財界主流など |
| アジア・モンロー主義的路線 | 英米への経済的依存を克服すべき弱点と捉え、アジアにおける自給自足圏を確立し、英米と対峙できる真の自立を達成すべきだとする膨張主義的な路線。 | 軍部、民間右翼、政友会など |
満州事変が勃発する直前までは、対英米協調路線が日本外交の主流を占めていた。
政治体制の二面性:「天皇制立憲主義」
日本の国内政治体制もまた、二面的な性格を帯びていた。「天皇制立憲主義」と称されるこの体制は、近代的な要素と前近代的な要素が同居する不安定な構造であった。
- 一方では、男子普通選挙に基づく衆議院の多数党が内閣を組織する議会政治・政党内閣が「憲政の常道」として定着していた。これは立憲主義的な側面である。
- 他方で、神聖不可侵とされる天皇に直結する軍部が、内閣から独立した「統帥権の独立」を盾に、政治や外交にしばしば介入する強大な権力を持っていた。
この政治と軍部の分裂は、前述の対外政策路線の対立と連動し、日本の進路をめぐる深刻な亀裂を増幅させる要因となった。
第2部:戦争への転換点 ― 満州事変
主流であった対英米協調路線を覆し、日本を戦争へと向かわせた決定的な転換点が、軍部による謀略から始まった満州事変であった。
背景:満蒙特殊権益と中国ナショナリズムの衝突
日露戦争で獲得した南満州の特殊権益は、日本にとって生命線と見なされていた。しかし、中国では辛亥革命以降、民族独立と主権回復を目指すナショナリズムが高揚し、日本の権益と正面から衝突する。当初、日本は軍閥の張作霖を協力者として利用していたが、彼が日本の統制から離脱し始めると、関東軍は不満を募らせた。
謀略の発動:張作霖爆殺から柳条湖事件へ
アジア・モンロー主義を掲げる軍部、特に関東軍は、対英米協調路線を推進する政府の外交方針を破壊するため、現地での謀略という実力行使に打って出た。
- 張作霖爆殺事件(1928年): 田中義一内閣が張作霖の武装解除を条件に中国の北伐を抑制しようとする外交(田中外交)を進める中、関東軍の河本大作らはこれを妨害する目的で張作霖を列車ごと爆殺した。これは現地の問題ではなく、東京における二つの政策路線の対立が引き起こした事件であった。
- 柳条湖事件(1931年9月18日): 関東軍作戦主任参謀であった石原莞爾は、「謀略により機会を作成し、軍部主導となり国家を強引する」という計画を立案。計画通り、関東軍は自ら柳条湖付近の満鉄線路を爆破し、これを中国軍の仕業と偽って軍事行動を開始した。
国家の暴走:独断越境の追認と不拡大方針の崩壊
若槻礼次郎内閣は事件の「不拡大方針」を閣議決定し、軍部の暴走を抑えようとした。しかし、軍部の独断行動は連鎖し、政府の統制を無力化していく。
- 朝鮮軍の独断越境: 朝鮮軍司令官・林銑十郎が、政府の命令を待たずに独断で国境を越え、満州の関東軍への増援を派遣。
- 政府と天皇の追認: この明白な統帥権干犯に対し、若槻内閣は軍部の強硬な態度に屈し、既成事実を認めざるを得なくなる。最終的に昭和天皇も「この度は致し方なきも将来十分注意せよ」とこれを追認した。
この独断行動の追認こそ、軍部の暴走を国家が容認し、破滅への道を歩み始めた「ポイント・オブ・ノーリターン」であった。石原莞爾の謀略は見事に成功し、日本はアジア・モンロー主義路線へと大きく舵を切った。
第3部:孤立と破滅への道
満州事変の成功は、軍部をさらに増長させ、日本を国際的孤立と国内政治の崩壊へと導いた。
国際的孤立の深化:錦州爆撃と日米冷戦の開始
当初、国際連盟は満州事変に対して比較的寛容であった。しかし、関東軍の行動はエスカレートし、国際社会の態度を硬化させた。
- 錦州爆撃(1931年10月): 石原莞爾らは、イギリスの権益にも近い都市・錦州を爆撃。これは第一次世界大戦後初の都市無差別爆撃であり、世界に衝撃を与えた。石原は「これは国際連盟に爆撃しているんだ」と述べ、意図的に国際秩序を破壊しようとした。
- 国際連盟での孤立: この爆撃により、国際連盟理事会で日本は13対1という圧倒的多数で非難され、政治的に完全に孤立した。
- 日米冷戦の開始: アメリカのスティムソン国務長官は、武力によって変更された事態を承認しないとする「スティムソン・ドクトリン」を発表。これは事実上の日米冷戦の始まりを意味した。
国内政治の崩壊:5.15事件と政党内閣の終焉
軍部の暴走は、対外的な侵略と並行して、国内の政敵、すなわち対英米協調路線を支える政党政治の破壊へと向かった。
この事件により、1924年以来8年間続いた政党内閣の時代は幕を閉じた。後継の斎藤実内閣は軍人も閣僚に含む「挙国一致内閣」となり、軍部の政治的発言力は決定的なものとなった。内政・外交の両面で対英米協調路線は完全に駆逐され、日本は軍部主導のアジア・モンロー主義路線を突き進むことになった。
第4部:国民の熱狂と動員
軍部の暴走が成功した背景には、国民世論の熱狂的な支持があった。本書は、国民がどのようにして戦争へと動員されていったかを克明に描いている。
世論の変容:国際的非難が排外主義を煽る
満州事変当初、国民世論は比較的冷静だった。しかし、錦州爆撃後に日本が国際連盟で非難されると、状況は一変する。
国難到来の強烈な危機感が民衆を捉え、中国及び国際連盟に対する敵意・増悪と、日本軍将兵への感謝・激励とが一斉に噴出し、排外主義的・軍国主義的風潮がいちじるしい高まりを見せた。
国際的孤立が、逆に国民の排外主義と国家意識を異常に活性化させるという逆説的な現象が起きた。全国各地で「満蒙権益擁護」「国連干渉排撃」を叫ぶ集会が開かれ、軍への献金や慰問が殺到した。
プロパガンダとメディアの役割
この国民的熱狂は、軍部による巧みなプロパガンダと、それに迎合したマスメディアによって増幅された。
- 軍部による宣伝活動: 在郷軍人会などを通じ、全国で「国防思想普及講演会」を大々的に開催。軍部は満州事変を正当化する主張を国民に直接訴えかけた。
- マスメディアの戦争協力: 大阪朝日新聞、大阪毎日新聞などの大手新聞社は、軍部の虚偽発表を鵜呑みにして報道し、事変の拡大を正当化し、日本軍の戦勝を讃え、中国や国際連盟への敵意を煽った。これはPV数を稼ぐための「インプレ稼ぎ」に他ならず、国民に事変の真相を知らせず、誤った認識を植え付けた。
この結果、国民のほとんどは、満州事変が「中国軍の暴虐に対する日本の自衛行為」であると、敗戦の日まで信じ込まされた。
批判的言論の圧殺
東洋経済新報社の石橋湛山のように、「満蒙放棄論」を唱え、日本の帝国主義的エゴイズムを鋭く批判する冷静な声も存在した。彼は、中国のナショナリズムを力で抑えることは不可能であり、経済的にも満州を放棄する方が日本の利益になると論じた。しかし、こうした理知的な言論は、熱狂的な「満州ブーム」と排外主義の嵐の中では少数意見としてかき消されていった。
このようにして、一部軍閥の謀略から始まった戦争は、国際的孤立、国内政党政治の崩壊、そしてメディアに煽られた国民的熱狂という連鎖の中で、制御不能な破滅への道へと突き進んでいったのである。
人気ブログランキング

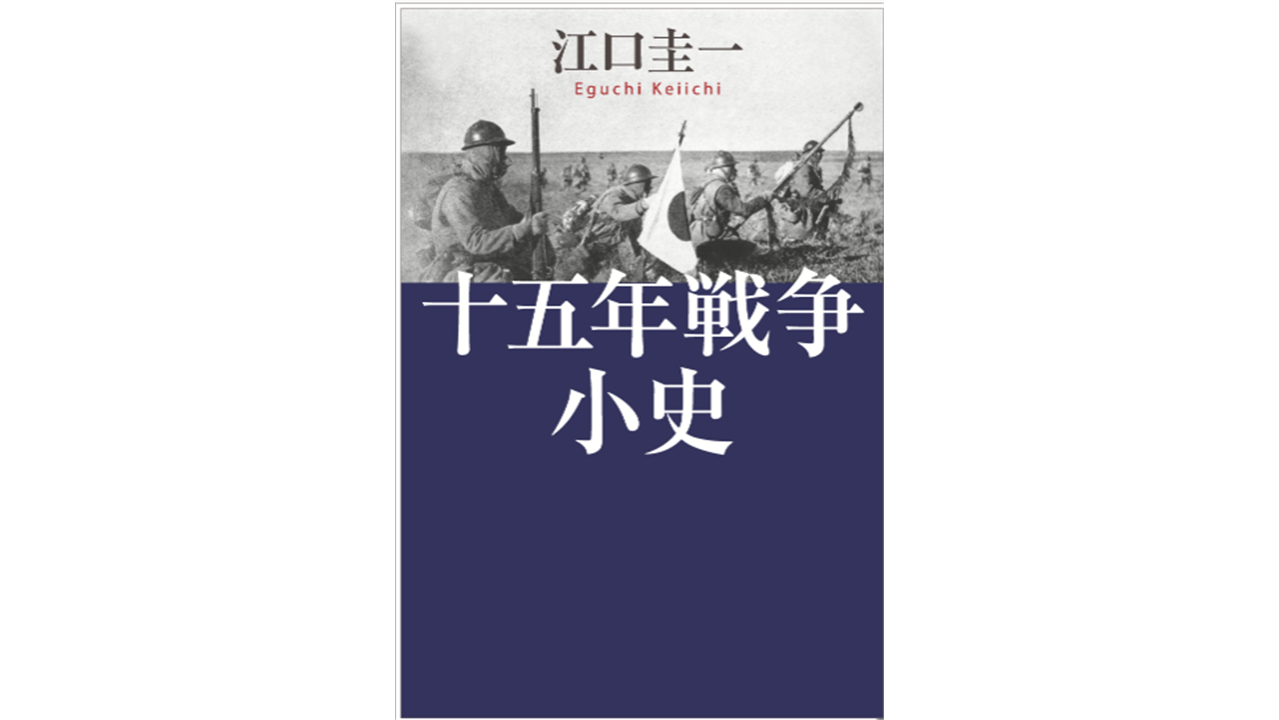
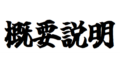

コメント