序論:病理としての「都構想」
2025/11/25(火)朝刊チェック:自ら死にゆくオールドメディア
大阪維新の会が執拗に掲げ続けた「大阪都構想」。二重行政の解消という合理性の仮面を剥ぎ、その衝動の根源を暴くとき、我々は単なる行政改革案という表層を突き抜け、現代大阪が抱える深刻な文化的・心理的病理に直面せざるを得ない。菅野氏が断罪するのは、まさにこの「東京コンプレックス」という病理の醜悪な政治的発露としての「都構想」である。
現代大阪を覆う東京コンプレックスは、もはや健全なライバル意識などではない。それは、常に東京を意識し、その尺度なくして自己を規定できない「共依存」状態へと堕し、ついには「単なるね、植民地支配なんです」と診断されるべき文化的独立性の完全な喪失に至っている。この精神的隷属は、自己肯定感の致命的な欠如と外部への病的な憧憬(しょうけい)を育み、政治的判断能力を根底から歪めてしまうのだ。
菅野氏は、この東京コンプレックスという名の病がいかにして「都構想」という具体的な政治運動に結実したのか、そのメカニズムを解剖する。分析のメスとして、大阪芸能を象徴する藤山寛美・直美親子という二代の存在を用いる。彼らの芸と生き様に見るコンプレックスとの対峙の鮮烈な対比は、大阪の精神史の変遷と、そこからの解放の可能性を冷徹に映し出すであろう。
——————————————————————————–
1. 現代大阪を蝕む精神構造:共依存から「植民地支配」へ
「都構想」という政治現象の本質を理解するためには、その精神的土壌、すなわち現代大阪が抱える東京コンプレックスの病理を徹底的に分析することが不可欠である。なぜなら、このコンプレックスは、過去のそれとは質的に変容し、もはや文化的対抗のエネルギーではなく、自らの文化的アイデンティティを内側から食い破る自己免疫疾患と化しているからだ。
かつて大阪には、「東京ってどこって」と嘯(うそぶ)ける時代があった。東京を意識せずとも、自らの文化と経済に絶対的な矜持を抱いていた時代である。だが現代の大阪人は、その矜持を忘却し、「ずっと東京の話をしてる」異様な状態に陥っている。この強迫的なまでの東京への固執は、「東京コンプレックスなんかあるわけないやないか」という防衛的な激しい自己否定と表裏一体をなす。この矛盾した振る舞いこそ、精神分析における「共依存」の典型的な症状に他ならない。依存対象(東京)を憎悪し否定しながらも、その存在なくしては自己を定義できないという、破滅的な関係性である。
この「共依存」が末期症状を呈したものが、「単なるね、植民地支配なんです」という痛烈な自己診断だ。これは経済的・政治的な支配に留まらない。価値基準、美意識、言語、そして記憶までもが支配者のそれに上書きされ、被支配者が無自覚のうちにそれを内面化する、最も根深い精神的従属を意味する。大阪の人々自身はこの事実を「絶対認め」ようとはしないが、その日常は「朝から晩まで年柄年中 隅から隅まで」東京発の話題で汚染されているのが現実だ。
この文化的消去の動かぬ証拠は、食という最も根源的な文化領域にこそ、悲劇的に刻印されている。現代の関西人の多くが、カツオと昆布の出汁こそ伝統的な「関西の味」だと信じて疑わない。だがこれは、文化的記憶喪失の産物である。本来の大阪のうどんを支えたのはサバやイワシの節が織りなす濃厚な旨味であり、そうめんには干しエビや椎茸の滋味が溶け込んでいた。関東式の価値観の象徴である「カツオ出汁」が、いつしか関西のスタンダードとして君臨し、本来の味覚の体系は駆逐されたのだ。これは単なる味の変遷ではない。ひとつの地域文化が、自らの美意識と知の体系を無意識のうちに放棄し、外部の権威に降伏した「文化的降伏」の記録である。もはや「『文化権として関西というもの』は存在しない」と断言されても、反論の言葉を見出すのは困難であろう。
このような精神的焦土から、いかなる政治的怪物が生まれ出るのか。次章では、この病理が噴出した帰結としての「都構想」を分析する。
——————————————————————————–
2. コンプレックスの政治的噴出:大阪維新の会と「都構想」
前章で解剖した大阪の深刻な精神的病理、すなわち「共依存」から「植民地支配」へと至る東京コンプレックスは、単なる文化的な嘆きに終わらなかった。それは「大阪維新の会」という政治勢力をゆりかごとし、その看板政策である「都構想」という形で、最も具体的かつ醜悪な政治的奇形として噴出したのである。
「都構想」は、大阪人が「ずっと東京の話をしてる」という異常な状況が生み出した「最たる例」と断じなければならない。この政策の根源的な動機を抉り出すならば、それは「東京コンプレックスがなかったら都構想なんてアホなこと言い出すかよ」という一言に尽きる。大阪を「都」に格上げするという、その名称自体が、東京に対する剥き出しの劣等感と、東京の模倣者でありたいという卑屈な願望の証左である。この構想は、都市設計の合理性や未来へのビジョンといった大阪人の「賢い側」から生まれたものではない。これは、理性が感情に、創造が模倣に屈服した瞬間に生まれる政治的怪物であり、積年のコンプレックスを解消したいという感情的衝動、すなわち人間の「アホな側」から吐き出されたものなのだ。
この感情的な政策を熱狂的に支持するのは、どのような人々か。維新の支持層には、「関西人というナラティブ(物語)の中で生きる」人々が少なくないと分析される。彼らは、メディアが量産するステレオタイプな「関西像」を内面化し、その役割を演じることでしか自らのアイデンティティを確認できない。東京を絶対的な基準点とし、それとの対比や模倣の中でしか自己を語れないこの心理構造こそ、単純化された「関西物語」を渇望する精神的基盤である。そしてその渇望は、同じく単純な政治物語である「都構想」へと容易に接続される。彼らにとって「都構想」とは、模倣による自己肯定(validation through mimicry)という悲願を現実世界で達成するための、最後の希望なのである。
しかし、このコンプレックスには歴史的な系譜があり、そこからの解放の可能性もまた存在する。次章では、その歴史的変遷と克復の道を、二人の象徴的な役者の姿を通して探っていく。
——————————————————————————–
3. 象徴としての二代:藤山寛美と藤山直美に見るコンプレックスの系譜
大阪が抱える東京コンプレックスの歴史的変容と、その呪縛からの克復の可能性を理解するために、芸能界の象徴的な親子、藤山寛美と藤山直美の対比ほど、鮮烈な症例報告はない。父・寛美が体現した「対抗意識」の時代から、娘・直美が示す「解放」の姿へ。二人の芸のあり方は、大阪の精神史そのものを映し出す鏡である。
3.1. 父・藤山寛美 ー 「屈折した清い」対抗意識の時代
昭和の大阪を代表する喜劇王、藤山寛美。彼の比類なき芸の深奥には、森繁久弥や渥美清といった東京の巨星に対する「強烈な東京にたいする対抗意識」が、業のように深く刻み込まれていた。それは単なるライバル心ではない。憧れと嫉妬、そして東京での挫折が複雑に絡み合った、悲劇的なパラドックスであった。
彼のコンプレックスは、「東京に行きたい、東京で認められたい」という焦がれるほどの願望と、「東京で失敗した」という冷厳な現実との狭間で醸成された、「屈折した清い」ルサンチマン(怨念)であった。このパラドックスこそが、彼の芸を燃え上がらせると同時に、その可能性を縛り付ける鎖ともなったのだ。東京で頂点を極められなかったという癒やされぬ思いが、彼を「俺は大阪の代表や」と**「言いたがる」**防衛的な心理へと向かわせた。彼の芸は、常に東京という巨大な他者を意識し、それに対抗することで輝きを放った。それは、痛々しくも純粋な、一つの時代の精神の肖像であった。
3.2. 娘・藤山直美 ー コンプレックスからの解放と「維新の匂いがしない」芸
父・寛美の時代とは対照的に、娘である藤山直美の芸には、東京への対抗意識が「全くない」。彼女のスタンスは、「なんで東京のこと考えならんの、ええやん、私は私でこれで」という言葉に凝縮される、健やかで絶対的な自己肯定である。彼女は、父が生涯囚われ続けた東京という名の呪縛から、完全に自由なのだ。
このコンプレックスからの解放こそが、彼女を「初めて大阪の役者になった」と評さしめる所以である。東京を意識しないことで、彼女の芸は逆説的に、より純粋で濃密な「関西臭さ」を香り立たせることに成功した。力みが抜け、外部の評価基準を意に介さないことで、内なる大阪の文化が何のてらいもなく立ち現れるのである。
彼女の存在は、それ自体が維新の政治的・文化的複合体に対する「解毒剤」であり、「生きた反証」である。彼女の芝居には「維新の匂いがしない」と評されるが、それは当然だ。彼女の文化的自立性は、東京コンプレックスをエネルギー源とする維新のイデオロギーとはまさに対極に位置するからだ。ステレオタイプな「関西」の物語に依存し、東京への劣等感から「都構想」を支持する人々にとって、コンプレックスから解放された藤山直美の真の芸は、おそらく「理解できない」だろう。真の自立とは何かを、彼らの価値観では認識することすらできないのだ。
彼女の存在は、大阪が文化的自立を取り戻すための道筋を、静かに、しかし決定的に示している。
——————————————————————————–
結論:文化的自立性の放棄が生んだ政治的帰結
菅野氏が分析してきた通り、大阪の「都構想」は、経済合理性や未来へのビジョンといった理性の産物では断じてない。それは、現代大阪が陥った深刻な「東京コンプレックス」という文化的病理が生み出した、自己破壊的な政治行動であると結論せざるを得ない。
その病理は、父・藤山寛美の時代にあった「屈折した清い」ルサンチマンから、現代の「共依存」、そして文化的アイデンティティを完全に喪失した「植民地支配」状態へと、時代を経て悪性化の一途をたどった。この精神的土壌こそが、大阪維新の会のポピュリズムを育み、東京への模倣願望を政策として具現化させた元凶である。
一方で、娘・藤山直美が体現する「コンプレックスからの解放」は、大阪が本来持つべき健全な文化的アイデンティティのあり方を示している。東京を意識せず、自らの内に宿る文化に深く根差すことで初めて、真の独自性と普遍性を獲得できる。この視点に立つとき、維新の運動がいかに大阪の文化的自立とは逆行するものであるかが、より一層鮮明になる。
結局のところ、「都構想」を巡る一連の狂騒は、こう言い表すことができる。自分たちの家が、歴史と個性に満ち、最高に住み心地が良いにもかかわらず、隣の豪邸の話題ばかりに明け暮れ、その空虚な模倣のために多額の借金をしてまで我が家を破壊しようとする愚行である。その動機は、未来への希望ではなく、過去から引きずる劣等感に他ならない。この政治的選択の先に待つのは、都市の再生ではない。自らの手で文化的な独自性を葬り去るという、静かな「自死」の道である。
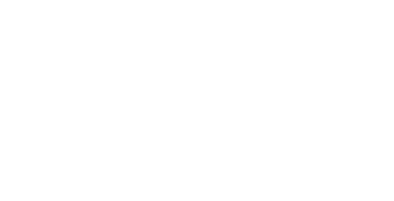

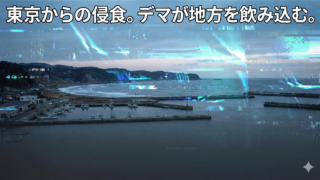

















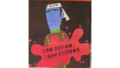

コメント