2025/12/26(金)朝刊チェック:政治が人を殺すとき。
序文:朝刊チェックから始まる現代日本への警鐘
私が菅野完でございます。朝刊チェックの時間がやってまいりました。頑張っていかなあかんなぁ~言うてるところなんですけど
この言葉から始まる日常的な配信の中で、菅野完氏は、鋭利なメスのように文化事象を解剖し、現代日本の政治と社会が抱える深刻な病巣を白日の下に晒す。本稿は、単なるドラマ批評ではない。それは、菅野氏が『阿修羅のごとく』や「クロワッサン症候群」を題材に、日本社会がいまだ「近代」を達成できていない――すなわち、個人の功績や専門性への敬意を確立できず、性の業のような不都合な真実から目を背け、安易な嘘で糊塗する社会――という現実を暴き出す試みである。文化における「本物」の喪失が、なぜ最終的に「政治が人を殺す」状況を必然的に生み出すのか。これは、その痛烈な警鐘の記録に他ならない。
——————————————————————————–
1. 『阿修羅のごとく』の本質――「家族愛」という嘘と「性」という真実
菅野氏の批評において、ドラマ『阿修羅のごとく』は単なる過去の傑作ではない。それは、時代の価値観がどのように変容し、劣化したのかを測るリトマス試験紙として機能している。彼がこの作品に執着するのは、そこに「本物」のクリエイターが到達した、妥協なき表現の凄みが凝縮されているからである。
菅野氏が繰り返し強調するように、脚本家・向田邦子と演出家・和田勉が制作当初に設定した作品の核心的テーマは、紛れもなく「セックス」であった。NHKのゴールデンタイムという厳しい制約の中、彼らはベッドシーンのような直接的な描写を一切用いず、日常風景のディテールと俳優たちの微細な演技の積み重ねによって、人間の根源的な「業」としての性を描き切ったのだ。
その卓越した演出手法は、象徴的なシーンに見て取れる。
- 八千草薫が倒れ、買い物袋から卵が割れて流れるシーン 夫の浮気を確信した妻が、愛人の家の前で失神する。その衝撃で買い物袋から転がり落ちた卵が、地面に叩きつけられて黄身を無残に広げる。菅野氏はこれを、生命の根源や性的な営みを想起させる「明確なセックスの隠喩」であると断言する。言葉にせずとも、視聴者の脳裏に直接的なイメージを焼き付ける、映像表現の極致である。
- 加藤治子と三條美紀の会話における「改革がおよろしいのね」という台詞 何気ない日常会話の中に、嫉妬や欲望、性的な緊張感を完璧に織り込む。この一言の応酬だけで、登場人物たちの隠された関係性や感情の澱みが浮かび上がる様は、まさに「日本テレビドラマ史上に残る」名演出と評されるに値する。
しかし、現代のリメイク版はこの核心的なテーマをいとも簡単に手放してしまった。ドロドロとした人間の業と性は、安易で耳障りの良い「家族愛」や「絆」の物語へと矮小化された。菅野氏が「阿修羅ちゃうやん」と痛烈に批判するのは、まさにこの点だ。本質的な厳しさや醜さから目を背け、誰も傷つけない予定調和の物語へと塗り替えてしまう態度は、心地よい嘘を求める現代社会の欺瞞そのものを象徴している。
本物が持つ、目を背けたくなるほどの厳しさ。そして、それを覆い隠す現代の偽善的な風潮。この stark な対比は、社会の崩壊の次なる階層、すなわち「プロの仕事」そのものに対する侮蔑という問題を暴き出す。
——————————————————————————–
2. 和田勉という「本物のプロ」――敬意を欠いた時代の傲慢
菅野氏がNetflixで配信された是枝裕和監督によるリメイク版を「素晴らしかった」と評価しながらも、同時に激しい怒りを示すのはなぜか。その怒りは是枝監督の技術に向けられたものではない。それは、和田勉というオリジナルの創造主の foundational(基礎的) な天才性を忘却し、優れたリメイクが結果的にその功績を上書きしてしまうことを許容する、文化的記憶喪失に対するものである。これは作品の「所有権(オーナーシップ)」と「歴史への敬意」という、より根源的なテーマへと繋がっている。
「あれは和田勉の作品です」という菅野氏の断言は、その怒りの核心を示す。『阿修羅のごとく』は向田邦子の脚本という設計図があったにせよ、和田勉という稀代の演出家の手腕によって初めて、血の通った傑作としてこの世に生を受けたのだ。それは向田邦子単独の作品ではなく、二人の才能が火花を散らした「共作」であった。
この敬意の欠如は、単にエンターテインメント業界の問題に留まらない。菅野氏は、オリジナルの創造主の仕事が忘れ去られる風潮を、日本が「近代」を達成できていないことの証左として捉える。個人の功績や専門性を正当に評価し、歴史として継承するという近代的な精神が根付いていない社会では、専門知は軽んじられ、表層的な人気や知名度だけが価値を持つ。このプロフェッショナルへの侮蔑という病理が、和田勉の盟友であった向田邦子の遺産を、いかに歪めてきたのか。卓越した創造主への敬意の欠如という問題提起は、我々の視線をそこへと向けさせるのである。
——————————————————————————–
3. 「女性の自立」という幻想――クロワッサン症候群に見る裏切りの構造
ここでは、個人のライフスタイルの選択という私的な領域が、いかにメディアやオピニオンリーダーによって持ち上げられ、そして無慈悲に裏切られるかという「梯子外し」の構造を、菅野氏の視点から解き明かす。
向田邦子は、男女雇用機会均等法が制定される以前の日本で、「男に頼らず、プロの職業人としておしゃれに生きる」というライフスタイルを体現した「最初のモデルケース」であった。彼女の生き方は、過激なウーマン・リブ運動とは一線を画しつつも、多くの女性にとって憧れの的となった。
この流れを社会現象にまで押し上げたのが、1980年代の雑誌『クロワッサン』が提示したライフスタイルであった。ウィキペディアによれば、「クロワッサン症候群」とは、結婚を拒絶し、雑誌が推奨する「自由で前衛的なシングルライフ」を選択した女性たちが、後年、適齢期を過ぎてから自信を喪失し、焦りや絶望を感じる心理的葛藤を指す。バブル経済を背景に理想として掲げられたこの生き方は、バブル崩壊と共にその前提を失い、雑誌自身も「仕事と家庭の両立」を賛美する方向へと変節していった。
菅野氏がこの構造における「最大の裏切り」として断罪するのが、文筆家・桐島洋子の事例である。独身で自立した女性の象徴として多くの信奉者を集めた彼女は、後に年下の資産家と結婚した。この選択は、彼女の言葉を信じ、自らの人生を賭けてその道を歩んだ人々にとって、まさに「梯子を外される」行為に他ならなかった。
この「裏切りの構造」は、政治家が有権者を裏切る構図と構造的に同一である。どちらも、まず「自由なシングルライフ」や「痛みを伴わない改革」といった、魅力的だが持続不可能な理想を提示する。次に、それを信じる支持者を獲得し、最後に現実が厳しくなると、指導者たちは何食わぬ顔でその理想を放棄し、信者だけが置き去りにされる。文化論から始まった我々の旅は、今まさに、具体的な政治批評の領域へと架橋されたのだ。
——————————————————————————–
4. 文化から政治へ――「能力なき者」が人を殺すとき
これまでの文化批評は、すべてこのセクションで論じられる核心的な政治批判へと繋がる伏線であった。ここは本稿のクライマックスに他ならない。文化が「本物」を尊ぶ力を失うことが、なぜ必然的に「政治が人を殺す」社会へと堕落するのか。菅野氏の告発の論理を、我々はここで目撃することになる。
菅野氏は、人間が到達しうる「本物の能力」の輝きを、畏敬の念を込めて語る。
- 和田勉の演出力: NHKのゴールデンタイムという制約の中で、「セックス」という人間の業を、一切の妥協なく描き切った圧倒的な技術。
- これらの高度なプロフェッショナリズムが、人間性の豊かさの証として文化の世界で燦然と輝く一方で、我々が生きる現実の政治はどうか。菅野氏は、そのお粗末さを兵庫県知事・斎藤元彦氏の事例を挙げて弾劾する。災害発生時、トップである知事が「指揮命令系統」という危機管理の基本中の基本すら理解していなかったという事実。これは単なる無知や無能ではない。それは、市民の生命を守るという最も基本的な社会契約を放棄する、生命を否定する行為である。菅野氏の言葉を借りれば、「明確に人を殺しに来ている」ことに等しい。
文化の世界における「本物」の仕事が人の心を揺さぶり、豊かにする一方で、政治の世界にはびこる「能力なき者」は、その無能さゆえに物理的に人の命を危険に晒す。この埋めがたい断絶を直視した時、我々はこの国の病理の深刻さを思い知るのである。
——————————————————————————–
5. 結論:「近代」の挫折と失われたものへの嘆き
本稿で追ってきた議論――『阿修羅のごとく』の本質の改変、「クロワッサン症候群」が露呈した裏切りの構造、そして政治家の致命的な無能さ――は、すべて同じ病根から生じた徴候である。それは、「本物を喪失し、表面的な偽物で糊塗する」という現代日本の病理であり、菅野氏が指摘する「近代の未達成」にその根源を持つ。
菅野氏は、ガルトンボードの比喩を用いて彼の社会観を説明する。本来、社会は多様な人間が自然な分布を形成して落ち着くはずのものだ。しかし、無能な政治家や歪んだ資本主義の論理は、そのボードに歪んだ釘を打ち込むように、社会の健全で自然な分布を暴力的に破壊する。彼らは中立的な存在ではなく、積極的な歪みのエージェントなのだ。
『阿修羅のごとく』が描いた「人間の業」のような深淵は、人間社会が持つ豊かさと可能性を示す「近代」の成果であったはずだ。しかし、現代日本はそうした深みと向き合うことを避け、わかりやすい「家族愛」に物語を書き換え、実務能力のない人物がリーダーとして社会をコントロールしようとする。
したがって、菅野氏の批評は、単なる過去への懐古主義ではない。それは、人間の業や社会の複雑さと正面から向き合う覚悟、そして「プロの仕事」に対する正当な敬意を取り戻すべきだという、未来に向けた痛切なマニフェストである。失われた「本物」への嘆きは、それを奪還するための闘いの第一声なのだ。
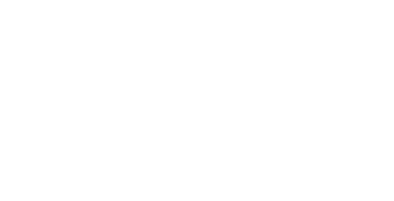



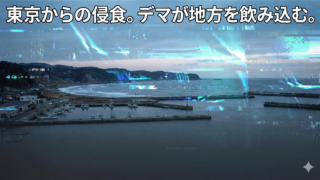
















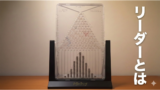



コメント