2026/1/8(木)朝刊チェック:維新とかいう社会のゴミについて
はじめに:朝刊チェックから始まる思考の旅路
私が菅野完でございます。1月8朝日 刊チェックの時間がやってまいりました。頑張っていかなあかんなぁ~言うてるところなんですけど。
50歳を超えた男性は皆「社会的なゴミ」であり、自らを菅野完だと思って生きるべきだ、という痛烈で物議を醸すような議論から始まりました。
しかし本稿では、その暗いテーマから派生した、より人間的な機微に富んだ様々な「余談」にこそ焦点を当てたいと思います。日々のニュースを追いかける中で、ふと心に留まった風景、忘れられない言葉、そして人間の本質が垣間見える瞬間。そうした一見本筋とは無関係に見える雑談や思い出話にこそ、私たちが生きるこの社会の機微や文化的背景、そして人間のどうしようもない愛おしさが隠されているのではないでしょうか。これから語られるのは、そんな余談にこそ宿る本質を探る、思考の旅路です。
第一章:浅草の記憶 — 食文化と江戸の粋
東京という都市は、実に多層的な文化の集合体です。特にその食文化には、この街が歩んできた歴史そのものが刻み込まれています。ここでは浅草という街を舞台に、東京が育んできた特異な「単身者文化」と食の結びつきを、私自身の個人的な記憶と共に解き明かしていきたいと思います。
暦の上ではディセンバー、俺の寿命はジステンバー(ジステンパー)
あれはもう10年ほど前、NHKの朝ドラ『あまちゃん』が人気を博していた頃のことです。私は仕事の合間に浅草の食堂で、サバの味噌煮定食を食べていました。昼の再放送が店内のテレビで流れる中、私の後ろの席では、昼間からすっかり出来上がった老人が一人、あらゆるものに毒づいていました。
「茶を持てこい!俺は酒と一緒に茶を飲むのが好きなんだ!」 「クラクションがうるせえな!根性あるなら中入って鳴らしてみろ、この野郎!」
彼は、まさに江戸弁のべらんめえ口調で、通り過ぎる車から、私のような見知らぬサラリーマン(「味噌煮なんか食ってんじゃねえぞ、ステーキ食え!」)にまで、無差別に絡み続けます。その混沌とした空気の中、テレビから『あまちゃん』の劇中歌「暦の上ではディセンバー」が流れ、司会者が曲紹介をした、その瞬間でした。老人が叫んだのです。
「何が暦の上ではディッセンバーだ、俺の寿命はジステンバーだ、この野郎!」
その場にいた他の客たちから「犬じゃねえんだから」とヤジが飛ぶ中、私はその言葉の持つ見事なライムと、人生の悲哀を凝縮したかのようなユーモアに、ただただ感嘆しました。この一言は、浅草という街が持つ猥雑さと粋、そして人間のおかしみを象徴する、忘れがたい記憶として私の中に刻まれています。
ホッピー通りと縄文時代の狩猟採集民
浅草と言えば、多くの人がホッピー通りを思い浮かべるかもしれません。しかし、私の見立てでは、あの通りは主に東武線に乗ってやってくる群馬、栃木、埼玉からの観光客をもてなすための場所です。特に群馬から来た人々は、あの場所で一種の解放感を味わっているように見えます。
私の冗談めいた分類によれば、彼らは現代に生きる「縄文時代の狩猟採集民」です。イノシシの皮のような服をまとい、「石で掘った穴の開いたやつ」や「貝殻」を使い、一杯1000円もするゴボウの素揚げをありがたがって食べている。ホッピー通りは、彼らから現代の通貨を吸い上げるための、巧みな装置として機能しているのです。
フグと「一人鍋」に見る江戸のDNA
私にとっての浅草の本質は、ホッピー通りではなく、むしろ「フグとすっぽんの町」という側面にあります。大正末期から昭和初期にかけて、天ぷら、洋食、そしてフグといった贅沢品がこの地に集積しました。それが、浅草の食文化の根底を流れる豊かさの源泉なのです。しかし、その文化も今は昔。昔はゴロゴロ会館の裏手といえばフグ屋だらけだったものが、今やほとんどがマンションに変わってしまいました。
東京に出てきて最も衝撃を受けた文化の一つが、**「一人でフグを食う」**という光景でした。大阪では、てっちり(フグ鍋)やすき焼きを一人で食べるなど考えられません。「お前、狂ってるのか」と言われるのが関の山です。しかし、東京の老舗のフグ屋には、お一人様専用のテーブルが設えられ、一人の客が黙々とフグのフルコースを味わっているのです。
この「一人鍋文化」の根源は、江戸が歴史的に**「単身者の町」**であったことに求められます。地方から出てきた男性の一人暮らしが圧倒的に多く、彼らの食生活を支えるために、惣菜屋や一人向けの食事が発展しました。その文化構造の違いは、古典落語の世界にも色濃く反映されています。
例えば、落語の『そこつ長屋』。江戸落語では、登場人物は独身の男同士です。しかし、この噺を上方(大阪)で演じると、物語の構造は全く異なるものになります。壁が薄い長屋でそそっかしい男が釘を打つと、隣の家の阿弥陀様の額から釘が突き出てしまう。すると隣家の「お上さん(妻)」が怒鳴り込み、慌てふためいた亭主が「えらいこっちゃ、明日からほうき、隣の家にかけにこなあかん」と嘆く。個人の失敗が隣人や家族を巻き込む騒動へと発展する、この共同体的なユーモアこそが、上方の文化の産物なのです。
東京の食文化に見られる個人主義的な側面は、単に現代的なライフスタイルの反映ではなく、江戸時代から続く都市の歴史的DNAと深く結びついています。そして、その文化的な機微は、私たちが笑いの中に人間模様を見出す落語の世界へと、深く繋がっていくのです。
第二章:トチリの芸 — 落語に見る人間の愛おしさ
完璧に磨き上げられた芸はもちろん素晴らしいものですが、時として、名人たちが演目中に見せるふとした「トチリ(失敗)」の中にこそ、計算され尽くした芸とは異なる、抗いがたい人間的な魅力や芸の深層が顔を覗かせることがあります。ここでは、名人たちの愛すべき失敗のエピソードを通じて、芸の本質に迫ってみたいと思います。
名人たちの愛すべき失敗
落語の世界には、伝説として語り継がれる「トチリ」がいくつも存在します。
- 桂米朝師匠の『宿替え』 米朝師匠の『宿替え』は、残されている録音のほとんどで何かしらのトチリがあると言われています。この噺のキモは、物理的に不可能な状況を作り出すことで笑いを生むことにあります。しかし師匠は、家財道具を柱ごと風呂敷で包むという重要な描写を忘れてしまうことがありました。その結果、主人公が立ち上がれないはずの場面で「いや、立てるやん」という状況が生まれ、噺の前提が崩れてしまうのです。これは、名人ですら陥る、芸の難しさと人間らしさを示す好例です。
- 桂仁鶴師匠の『くしゃみ講釈』 仁鶴師匠が見せたのは、もはや名人芸の域に達したリカバリーでした。噺の終盤、登場人物が唐辛子を買って帰るはずが、師匠はすっかりそのことを忘れてしまいます。長屋に帰り着き、相方に「こうてきたで」と言うべきところで、買い忘れたことに気づく。しかし、そこで動じることなく、**「こうてきたことにしよう」**と呟き、何事もなかったかのように噺を続けるのです。失敗を瞬時に笑いに転化する、その機転と胆力には凄みすら感じさせます。
- 柳家小三治師匠の『青菜』 私が生で目撃した中で最も衝撃的だったのが、晩年の小三治師匠による『青菜』のトチリです。物語のクライマックス、奥から出てきた女将さんが言うはずの決め台詞、「その名も九郎判官義経、弁慶まで」を、なんと師匠自身が言ってしまうのです。その瞬間、ホールは静まり返り、私自身も「見てはいけないものを見てしまった」と頭が真っ白になりました。
「今日の青菜は良かった」への違和感
しかし、本当に驚いたのはその後のことです。終演後、観客たちが口々に「今日の青菜は良かった」と満足げに語り合っているのです。私は心の中で叫ばずにはいられませんでした。**「何でもええんかお前ら!」**と。あんなに大きなトチリがあったにもかかわらず、小三治師匠が演じたというだけで全てが肯定されてしまう。そのファンの心理は、ある種の気持ち悪ささえ感じさせるものでした。
私の憤りは、この噺への深い愛着から来ています。本来の『青菜』は、見栄を張りたい植木屋の女将さんが旦那の真似をしようとして失敗する、その滑稽さが面白いのです。「お前とこの奥言うたって、押入れしかないやないか」とツッコまれるような狭い家で、汗だくになりながら押入れから出てくる女将さん。そのいじらしさこそが、この噺の真骨頂なのです。私の批判は、単なる揚げ足取りではなく、その本質的な面白さを知っているからこその叫びでした。
名人たちの「トチリ」は、単なる失敗ではありません。それは、彼らが長年かけて築き上げてきた芸と人間性の深さがあればこそ、観客を惹きつける特別な瞬間となり得るのです。それは計算された完璧さとは全く異なる次元の価値を持ち、時に予定調和の芸を超える感動を生み出します。こうした人間の不完全さや、そこから生まれる予期せぬ面白さこそが、私たちが芸や人生に魅了される根源なのかもしれません。
第三章:友との一夜 — 拘置所の寒さと極上のユーモア
「湯気出てる」— 拘置所と鉄板焼き:自由なる者の“性格の悪い”晩餐
人間の精神的な強さとは、一体どこに宿るのでしょうか。それは清廉潔白な正義感だけではなく、長きにわたり巨悪と対峙し続けてきた者だけが持つ、痛烈な皮肉と余裕、あるいはある種の「性格の悪さ」にこそ見出せるのかもしれません。ここでは、長年立花孝志氏と戦い続けてきた友人・ちだい氏との一夜の対話を通じて、その核心に迫ります。
湯気の向こうに見る「敗者の寒さ」
先日、兵庫県知事選に関連する取材を終えた私は、神戸でちだいさんと二人でお好み焼き屋のカウンターに並びました。まずは酒の肴にと注文したのは、彼の好物である明太子の鉄板焼きと、私が頼んだ牡蠣のバター焼きです。ちだいさんは牡蠣が食べられないため、それぞれ別の品を頼んだのですが、明太子は表面をこんがり焼きつつ、中はレアに仕上げられた絶妙な焼き加減で提供されました。
熱々の鉄板に乗せられた料理が目の前に置かれ、もうもうと白い湯気が立ち上ったその時です。ちだいさんはその湯気を指差し、くっくっと笑いながらこう言ったのです。
「湯気出てる」
一見すると何でもないこの言葉の裏には、彼が長年追及してきた相手への強烈な皮肉が込められていました。「神戸拘置所では、こんなあったかいやつは出てこないなと思うと嬉しくって」と彼は続けます。
彼は自分が捕まっているわけではありません。今この瞬間、自分が戦ってきた相手が、冷え切った神戸の拘置所で冷たい食事をしている姿を想像し、目の前の「湯気」に優越感と喜びを見出しているのです。さらに熱燗を一口すするや、「ああ、あったけえ」とまた笑う彼。凍てつくような拘置所の環境と、自分たちが味わっている極上の熱い料理との対比。このブラックユーモアに、私は彼の「性格の悪さ」、言い換えれば、戦い抜いた者だけが許される精神的な勝利の味を見ました。
マイナス4度の天気予報
この徹底した「性格の悪さ」は、先日行われたイベント(カルト新年会)でも遺憾なく発揮されました。
彼は自身の持ち時間15分を使い、**「神戸市北区の拘置所の周りの一週間の気温を、ただひたすら説明する」**という前代未聞のプレゼンを敢行したのです。 マイナス4度、マイナス5度という極寒の数字が並ぶスライドを見せながら、「マイナス1度くらいだと、今日はそうでもないな、と感じる」といった解説を淡々と加える。会場は爆笑の渦に包まれました。自分がそこにいるわけでもないのに、想像力だけで相手の寒さを詳細に語り、それをエンターテインメントに昇華する。その執念とユーモアのセンスには、畏怖すら覚えます。
美味しい食事の湯気を見てニヤリと笑うその姿は、正義の味方というよりは、悪を挫くために自らも毒を喰らうことを厭わない、したたかなリアリストの肖像でした。
鈴蘭台の極寒と平安の残党
彼のジョークが決して大袈裟ではないことを、私は自身の経験から知っています。かつて、神戸市北区の鈴蘭台に住む彼女の家に通っていた時期がありましたが、あの地域の寒さは尋常ではありません。冬場は駅前の水たまりが凍りつき、市街地では雨でも、鵯越(ひよどりごえ)の坂を越えた向こうは雪、ということが日常茶飯事でした。タクシー運転手が「鈴蘭台の奥の方へお客さんを送って行ったら、向こうは雪でね」と語るほど、気候が隔絶されているのです。
源義経が奇襲をかけたという歴史の舞台を越えた先は、まるで別世界。私は「この上には平清盛の残党が住んでいるんじゃないか」と本気で思ったほどです。
この一連のエピソードから導き出される結論は、**「ちだい氏はだいぶ性格が悪い」**というものです。しかし、それは決して非難の言葉ではありません。むしろ、不条理な経験を極上のユーモアへと昇華させた人間の強さに対する、最大限の尊敬の念を込めた賛辞なのです。
結び:縄文人と平安人、そして現代を生きる我々
本日お話ししてきた「余談」—浅草の食堂で出会った酔漢の叫び、名人落語家たちの愛すべき失敗、そして友人が見せた極上のブラックユーモア—は、それぞれが全く異なる文脈を持ちながらも、通底する一つの真理を指し示しています。それは、人間のどうしようもない滑稽さと愛おしさ、そして逆境を笑い飛ばす逞しさです。
講演の途中で、私は群馬の人々を「縄文時代を生きる狩猟採集民」、そして神戸・鈴蘭台の向こうを「平安時代末期で時が止まった場所」と冗談めかして表現しました。これは単なる皮肉ではありません。私たちの生きる現代社会とは、かくも異なる時間軸を生きる人々が奇妙に混在し、共存する、面白くて厄介な場所なのです。
日々のニュースの裏側に隠された、こうした人間臭い風景に目を凝らすこと。そこにこそ、この複雑な時代を生き抜くための、ささやかな、しかし確かなヒントが隠されているのかもしれません。
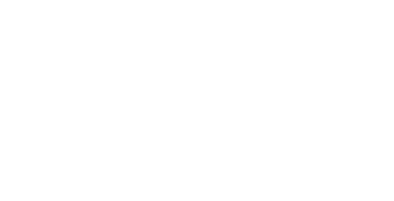










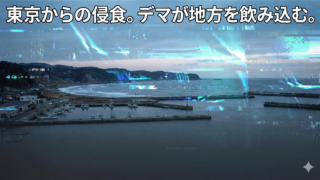











コメント