1. はじめに:単なる「ミス」では済まされない文科省の統計操作
2025/12/2(火)朝刊チェック:かくて社会は差別で腐る。
2024年、文部科学省が大学進学率の統計において、特別支援学校の卒業生を分母から除外していたという事実が発覚した。これは、単なる行政の技術的ミスとして片付けられる問題ではない。日本社会が抱えるより深刻で構造的な病理を映し出す、象徴的な出来事である。本稿は、この統計操作を入り口として、その深層に横たわる日本社会の根深い「未成熟さ」を解き明かす。
毎日新聞の報道によれば、事態の概要は以下の通りだ。
- 文科省は2024年度の大学進学率を「過去最高の59.1%」と華々しく発表した。
- しかし、その計算の土台となる「18歳人口」という分母から、特別支援学校高等部の卒業生約1万9000人が意図的に除外されていた。
- 彼らを分母に含めて正しく計算した場合、進学率は58.6%に低下する。
これは単なる数値の粉飾ではない。自分たちの成果を良く見せるために、特定の人間集団を「最初からいなかったもの」として扱うという、冷徹な意思決定である。この統計上の「抹消」という行為こそ、これから論じる日本社会の「未成熟さ」を理解するための、具体的な入り口に他ならない。
2. 嘘の解剖学:なぜ「分母の改ざん」は人間存在の抹消なのか
文科省による統計操作は、他のデータ改ざんとは質的に異なり、悪質性の次元が違う。問題の本質は、単なる「成果の水増し」ではない。それは、計算の土台から特定の人間を消し去るという**「人間存在の抹消」**であり、この存在論的な暴力の分析こそが、この問題の核心を突く鍵となる。
一般的な嘘と今回の嘘の違いは、「分子」を操作するか、「分母」を操作するかの違いに集約される。
- 通常の嘘(分子の操作): 成果や成功事例といった「分子」の数を水増しする行為。これは成果を誇張する一般的なごまかしである。
- 今回の嘘(分母の操作): 計算の前提となる全数、すなわち「分母」から特定の人間を削る行為。これは、自分たちの都合のために、ある人々を**「最初からいなかったもの」として扱うことを意味する。これは混じり気のない純粋な差別、すなわち「差別のまったき味」**そのものである。
この行為の異常性は、文科省が掲げる理念との対比において一層際立つ。彼らは表向き「インクルーシブ教育(包摂)」というスローガンを掲げながら、その裏で統計上は障害者を「エクスクルーシブ(排除)」するという、致命的な矛盾を犯した。この言行不一致は、彼らの掲げる理念が実体を伴わない空虚な欺瞞であることを暴露している。
この行為の性質は、単なる悪事を越えた、陰湿な「邪悪さ」を帯びている。これは外部の敵による攻撃ではなく、守護者による陰湿な裏切りである。それは、子供が、自分の母親が家族のために丁寧に二度揚げしている唐揚げを、そばからつまみ食いするような行為に近い。信頼すべき身内(国家)が、守るべき対象(国民)を自らの見栄えのために食い物にする。この行為は、社会の信頼と倫理的基盤を内側から腐食させるのだ。
そして、この「存在の抹消」という邪悪な行為は、官僚組織という閉じた世界の問題に留まらない。それは、日本社会全体が抱えるより大きな構造的問題、すなわち「近代国家としての未成熟さ」へと繋がっているのである。
3. 未成熟国家の肖像:マッカーサーの呪いと欠落した「近代の原則」
文科省の問題は、官僚組織固有の腐敗というよりも、日本社会全体が抱える精神的な未成熟さの表れと見るべきだろう。かつてダグラス・マッカーサーは、日本人を「精神年齢12歳」と評した。戦後約80年が経過した今、この言葉は過去の侮辱ではなく、驚くほど的確な現代への診断として響く。
日本社会が理解していないのは、近代社会を成立させるための最も基本的な原則である。
- 近代の原則: 「自分は尊い、ゆえに(自分と同じように)他者も尊い」。これは、自らの尊厳を基点として、他者の存在を対等に認め、尊重するという普遍的な精神である。
- 日本の現状: 自分たちの都合の悪い存在を「いないもの」として統計から抹消する行為は、この原則を根底から否定している。これは、価値は自分たちの部族(イングループ)にしか認めないという、前近代的な精神性への回帰に他ならない。
このような国家運営のあり方は、成熟した統治とは到底呼べない。事実を直視せず、自分たちに都合の良い嘘で塗り固めた世界に安住する態度は、責任能力のない子供の**「ごっこ遊び」**に過ぎない。人間が存在するという現実を無視し、「高い進学率」という虚構の成果に満足する。これは、国家が合理的な統治能力を喪失している証拠であり、構造的な失敗は必然的な衰退を招く。
この精神的な未成熟さは、単なる社会の停滞を招くだけではない。それは、自分たちと異なる他者への不寛容と排除を正当化し、具体的な暴力や悲劇を必然的に引き起こす、危険な土壌となっているのである。
4. 論理的な帰結:行政の「抹消」が物理的な「殺傷」を生むとき
行政による統計上の差別と、現実世界で起こる物理的な暴力。この二つの間には、断絶ではなく、恐ろしいほどの連続性が存在する。2016年に発生した相模原障害者施設殺傷事件は、この社会構造が生み出した「必然的」な帰結であった。
文科省の「行政による抹消」と、植松聖死刑囚の「物理的な抹消」。両者の論理は、その手法が異なるだけで、本質的には同一である。
- 国家の論理: 「成果(進学率)を良く見せる」という自分たちの都合のために、統計という認知の枠組みから障害者を排除する。
- 犯人の論理: 「社会の役に立たない」という自分の都合のために、現実の世界から障害者を排除する。
なぜ植松聖のような人物が生まれたのか。それは彼が特異な狂人だったからではない。効率や手際の良い「結論」を人間性の 厄介な現実よりも優先する社会、そして「人を人と思わないアティチュード「態度」「考え方」「心構え」」が教育を司る国家機関によって公然と実践されている社会。その空気を吸って育った人間が、同じ論理に基づいて凶行に及ぶのは、もはや偶然ではなく**「必然」なのである。彼は決して特殊な怪物ではなく、日本社会が持つ排除の論理が凝縮された「日本社会の縮図」**であった。
国がペンと消しゴムで行った「抹消」を、彼は刃物で実行したに過ぎない。この行政による差別と物理的な暴力の連鎖を断ち切れない限り、この国は再び同様の悲劇を繰り返すだろう。その末路は、果たしてどのようなものになるのだろうか。
5. 結論:「保護観察下」の国家から脱するために
これまでの議論を総括すれば、文科省の統計問題は氷山の一角に過ぎない。その根底には、他者の存在を対等に認めず、都合の悪い事実を直視できない、「精神年齢12歳」のまま時が止まった未成熟な社会構造がある。
この現状は、日本が自律的な主権国家ではなく、実質的な**「保護観察下の国家」であるという痛烈な診断を突きつける。自浄作用を持たず、「放っておいたらまた発狂して人を殺す」**危険性を内包する社会は、自律的に正気を保つ能力を欠いている。日米地位協定のような不平等な枠組みが、この未熟な国家に対する「保護観察」として機能しているのかもしれない、という皮肉は、我々の主権が根底から問われていることを示唆している。
この問題を克服する道は、単なる差別是正のスローガンを唱えることではない。それは、**「人間を人間としてカウントする」**という、近代社会のあまりにも初歩的な原則を、この社会の隅々にまで徹底することに尽きる。これは倫理的な要請であると同時に、国家が正確な自己診断を下し、合理的に機能するための最低条件でもある。統計においても、政策においても、そして我々一人ひとりの意識においても、すべての人間を社会の正当な構成員として認め、数えること。それこそが、この屈辱的な「保護観察」状態から脱し、日本が真の成熟した近代国家になるための、唯一の道である。

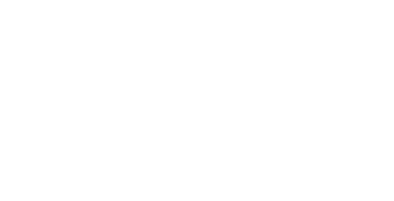














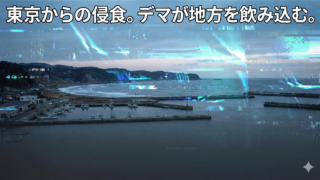






コメント