2025/12/17(水)朝刊チェック:戦争で国は滅びない。バカが調子に乗り、バカが権力を握りバカなことを言い散らかすからこそ国は滅びる。
1. 序論:なぜ今、仲代達矢の「残日録」を語るべきなのか
数多の映像作品が生まれ、消費されていく現代において、過去の傑作が持つ意味を問い直すことは、我々の文化的な羅針盤を再調整する上で不可欠な作業である。本稿が光を当てるのは、1993年にNHKで放送された仲代達矢主演の『清左衛門残日録』だ。この作品は、単なる懐かしい時代劇ではない。それは、現代の映像業界が失いつつある「本物の人間ドラマ」の価値を映し出す鏡であり、その輝きを再発見するための重要な試金石なのである。本稿は、批評家・菅野完氏の鋭い視点を通して、このドラマが持つ不朽の芸術的価値を解き明かすことを目的とする。
菅野氏の論考の核心は、仲代達矢版『清左衛門残日録』を、巷に溢れる「型通りで退屈な時代劇」の対極に位置づけ、役者の魂が宿る「上質なドラマ」として高く評価する点にある。多くの時代劇が様式美や予定調和に安住する中、なぜこの作品だけが特別な輝きを放つのか。
本稿では、菅野氏の批評を以下の3つの視点から忠実に再構成し、その論理を深く掘り下げていく。
- 形骸化する時代劇への批判:他の作品との比較によって「本物」を浮き彫りにする。
- 俳優・仲代達矢の真価:彼のキャリアにおける最高傑作としての位置づけを解明する。
- 「人間ドラマ」としての再評価:「時代劇」というジャンルの枠を超えた普遍的価値を探る。
この分析を通して、仲代達矢版『清左衛門残日録』がなぜ今、改めて語られるべき傑作なのか、その理由が明らかになるだろう。
——————————————————————————–
2. 形骸化する時代劇への痛烈な批判:比較によって浮き彫りになる「本物」
仲代達矢版『清左衛門残日録』が持つ真の価値を理解するためには、まず、菅野氏が現代の多くの時代劇をいかに批判的に見ているか、その背景を把握することが不可欠である。彼の批評は、安易な作品群への失望から出発しており、その厳しい視線こそが、仲代版の特異性を際立たせるための土台となっている。
菅野氏は、松方弘樹の『遠山の金さん』や、北大路欣也の『銭形平次』『御家人斬九郎』といった著名なシリーズを例に挙げ、「再放送されても面白くない」と断じている。その根本的な理由は、主演俳優が「時代劇とはこうあるべきだ」という固定観念、すなわち「型」に囚われすぎている点にある。その結果、どの役を演じても同じような演技に見えてしまい、作品から生きた人間の息遣いが失われてしまうのだ。これは、ジャンルの様式美が、俳優の個性を飲み込んでしまった不幸な状況と言える。
2.1. 決定的な対比:北大路欣也版『残日録』への辛辣な評価
菅野氏の批判が最も先鋭化するのは、同じ藤沢周平の原作を映像化した北大路欣也版『残日録』に言及する場面である。彼はこの作品を「ひどい」「何をやっても一緒」と、容赦なく切り捨てる。この辛辣な評価は、単なる個人的な好悪の表明ではない。それは、仲代達矢版がいかに常軌を逸したレベルに到達しているかを読者に理解させるための、極めて効果的なレトリックとして機能している。同じ原作、同じ役名でありながら、なぜこれほどまでに評価が分かれるのか。その問いこそが、仲代達矢という俳優の凄みへと我々を導くのである。
結局のところ、現代の多くの時代劇は、スター俳優が「お約束」の演技を披露するだけの、ある種の様式芸能と化してしまっている。菅野氏の視点に立てば、こうした形骸化した状況だからこそ、役の魂を掘り下げ、生身の人間として演じきった仲代達矢の仕事が、比類なき輝きを放つのだ。次のセクションでは、その「真価」について、より詳しく見ていくことにしよう。
——————————————————————————–
3. 「真打」仲代達矢の最高傑作:俳優の魂が宿る演技
菅野氏の論評において、仲代達矢は単なる名優としてではなく、時代劇というジャンルにおける「真打」、すなわち他の追随を許さない絶対的な存在として位置づけられている。形骸化した時代劇への批判を経て、彼は仲代達矢の仕事こそが「本物」であると高らかに宣言するのである。
その評価の究極的な表明が、「将来、仲代達矢の追悼番組が組まれるならば、流すべきは仲代達矢版の『清左衛門残日録』だ」という断言である。映画『人間の條件』や黒澤明作品といった輝かしいフィルモグラフィを差し置いてまで、なぜ一介のテレビドラマを挙げるのか。それは、この作品こそが「めちゃめちゃええぞ」と菅野氏が絶賛するほどの圧倒的なクオリティを持ち、仲代達矢という俳優の凄みが最も純粋な形で凝縮されているからに他ならない。
この主張を補強するのが、「ミュージシャンのアナロジー」である。偉大なミュージシャンを追悼する際、最も商業的に成功したキャッチーなヒット曲を流すのではなく、その魂と技術が極限まで込められた「知る人ぞ知るライブの名演」を流すべきだ、という考え方だ。同様に、『清左衛門残日録』における仲代達矢の演技は、表層的な「時代劇ごっこ」ではない。それは、役柄の人生、その喜びも悲しみもすべてを背負った、魂の入った「演技」そのものなのである。これは、商業的な成功と芸術的な到達点が必ずしも一致しないことを示唆しており、『清左衛門残日録』はまさに後者の、魂の記録なのである。
仲代達矢の演技が作品の核であることは間違いない。しかし、南果歩、かたせ梨乃、財津一郎といった実力派が固める脇役陣の存在なくして、このドラマの重厚な世界観は生まれなかった。この作品の価値は、単なる一人の名優の個人的な到達点に留まるものではない。それは、より広い文脈において、「ドラマ」そのものが持つ可能性を我々に示している。次のセクションでは、その普遍的な価値について掘り下げていきたい。
——————————————————————————–
4. 「時代劇」の枠を超えて:再評価されるべき「上質な人間ドラマ」
菅野氏の批評は、単に一つの時代劇を称賛するだけに留まらない。彼の視線は、仲代版『清左衛門残日録』を通して、現代のテレビ業界全体が「上質なドラマ」を見失っているという、より根源的な問題提起へと繋がっていく。この作品の真価は、「時代劇」というジャンルの枠組みの中に押し込めることはできない。
菅野氏は、この作品を高橋英樹主演の『慶次郎縁側日記』と並べて論じ、チャンバラ活劇としての「時代劇」としてではなく、普遍的な「ドラマとしてすごい」と評価している。これは極めて重要な指摘である。つまり、物語の舞台が江戸時代であるという設定を超えて、そこに描かれているのは、老いや家族との関係、過去との向き合い方といった、現代の我々にも通じる人間の普遍的な葛藤なのだ。この作品は、ジャンルの慣習に寄りかかるのではなく、人間そのものを深く見つめることで、時代を超えた強度を獲得している。
この視点から、菅野氏は現代のテレビ局が持つ課題を鋭く指摘する。例えば、国民的子役から実力派俳優へと見事な脱皮を遂げたにもかかわらず、そのポテンシャルをテレビ局が十分に引き出せずにいる安達祐実の例は、その象徴である。安易な企画や視聴率至上主義の中で、じっくりと人間を描く骨太なドラマが作られにくい風潮そのものへの警鐘なのである。
だからこそ、菅野氏はNHKに対して「深夜でも良いからこの仲代版を放送して、本物のドラマを見せるべきだ」と強く主張する。これは単なる一ファンによる再放送の要望ではない。視聴者には「本物」を知る機会を、そして制作者には自らが目指すべきクオリティの基準を再認識させるべきだという、極めて文化的な提言なのである。
この作品が持つ普遍的なドラマとしての価値は、時代劇ファンという狭いコミュニティを超えて、広く共有されるべきものである。最終章では、なぜこの作品が後世に記憶され、語り継がれるべきなのかを結論づけたい。
——————————————————————————–
5. 結論:後世に伝えるべき「本物のドラマ」の灯火
菅野完氏の批評を通して仲代達矢版『清左衛門残日録』を再検討する旅は、我々を一つの明確な結論へと導く。この作品は、単なる優れた時代劇ではない。それは、すべての映像作品を愛する人々にとって、そして未来の作り手たちにとって、記憶され、参照されるべき文化的な遺産なのである。
この作品が持つ核心的な価値は、以下の3つのポイントに集約することができる。
- 形式からの脱却: 型にはまった「時代劇」の様式美に安住するのではなく、俳優の魂と魂がぶつかり合う、生々しい「人間ドラマ」であること。
- 俳優の到達点: 仲代達矢という一人の偉大な俳優のキャリアにおける、商業的な成功とは別の次元に存在する、芸術的な頂点を示す記念碑的作品であること。
- 現代への問い: 商業主義や安易なジャンル分けの中で見失われがちな「本物のドラマとは何か」という根源的な問いを、静かに、しかし力強く現代に投げかける鏡であること。
菅野氏の主張は、決して過去を懐かしむノスタルジーではない。それは、商業的な効率性が優先され、コンテンツが刹那的に消費される現代において、「魂の入った作品」がいかに貴重であるかを訴える、未来の映像文化に対する切実な願いである。我々視聴者に投げかけられているのは、こうした傑作を発見し、その価値を正しく評価し、そして次の世代へと語り継いでいくという、文化的な責務なのかもしれない。仲代達矢版『清左衛門残日録』は、そのための確かな灯火として、今も静かに輝き続けている。
人気ブログランキング
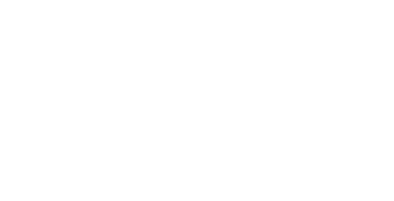

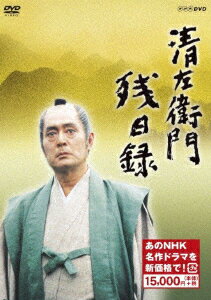


コメント