2026/1/11「統一教会と自民党の癒着がー!」と言いたがるアホリベラルの皆さんが覚えておかなければいけないこと。
序文:文化時評から個人的述懐へ
本稿は、当初、ある高校の校内誌から依頼された、極めて公的な性格を帯びた文化時評となるはずだった。しかし、筆を進めるうちに、それは期せずして筆者自身の個人的な記憶、とりわけ恋愛史に刻まれた屈辱と敗北の歴史を掘り起こす、極めて私的な述懐へと変貌してしまった。一つの楽曲の再流行という現代的な文化現象を追う仕事が、いかにして一個人の癒やしがたいトラウマの告白へと繋がっていったのか。その歪な経緯を、ここに記したい。
——————————————————————————–
1. 時代を超えて響く応援歌:中島みゆき「ファイト!」の再流行
1.1. 執筆依頼の経緯
すべての始まりは、一本の電話だった。筆者は、自身の母校ではない都内のある高校から、校内誌への寄稿を定期的に依頼されている。今回もその常連としての仕事であり、執筆テーマは先方から指定された。正直なところ、ゼロから題材を考える手間が省けるため、この形式はありがたい。そして、今回与えられたお題が、この考察の出発点となったのである。
1.2. TikTokが火付け役となった名曲の復活
そのテーマとは、中島みゆきの不朽の名曲「ファイト!」であった。驚くべきことに、この曲が今、高校生の間で大流行しているというのだ。しかし、その流行の実態は、我々の世代が知るそれとは少し様相が異なる。
- 竹原ピストルによるカバー版の浸透 現在の若者たちが耳にしているのは、中島みゆきのオリジナル音源ではない。彼らが夢中になっているのは、シンガーソングライター・竹原ピストルによる、魂の叫びのような熱量の高いカバーバージョンなのだ。
- 流行の震源地はTikTok そして、その流行を強力に後押ししているプラットフォームが、ショート動画アプリのTikTokである。オリジナルが持つ普遍的なメッセージが、カバーという新たな表現と、TikTokという現代的なメディアを通じて、新世代の心に再び火を灯しているのである。
1.3. カバー曲というプリズム
オリジナル楽曲が、カバーバージョンという一種のプリズムを通して新しい世代に届けられ、全く新しい文脈で消費されていく。この現象は、現代の文化のあり方を象徴しているようで非常に興味深い。だが、この話を担当の先生としていた時、もう一つの「世代を超えた流行」の話題が、私の心の古傷を容赦なく抉ることになるとは、まだ知る由もなかった。
——————————————————————————–
2. 不変の格差:東京スカパラダイスオーケストラと「モテ」の象徴
2.1. 音楽談義から見えたもう一つの流行
「ファイト!」についての原稿を書き上げ、担当の先生と電話で話していた時のことだ。「最近は僕らの若い頃に聴いていたような曲が、色々流行っているんですよ」と、先生は楽しそうに語った。その象徴として挙げられたのが、東京スカパラダイスオーケストラ(以下、スカパラ)だった。時代を超えて若者を魅了し続けるアーティストがいる。その事実は、音楽が持つ普遍的な力を改めて感じさせるものだった。しかし、その魅力の核心に触れた瞬間、私の心には暗い影が差し始めた。
2.2. すべてを奪い去る男、谷中敦
先生は興奮気味にこう続けた。「うちの学校の女子生徒なんて、みんな谷中さんに夢中なんですよ」。


やはり、そうか。理屈ではない。これは生物学的な、抗いようのない序列の再確認だ。いつの時代も、結局、すべてはあの男、谷中敦が持っていくのか。
谷中敦。その名は、私にとって単なるミュージシャンの名前ではない。彼は、いわば「菅野完の対極にいる存在」である。マトリックス図を描いたとしたら、座標軸の正反対の場所にプロットされるべき人間だ。
- 天を衝くほどの身長
- ありえないほどの顔の小ささ
- 異次元的な足の長さ
これらの要素が組み合わさって形成される圧倒的な存在感は、ごく限られた身体的理想を神格化する現代社会において、彼のような人物を、我々その他大勢の男性に対する無自覚な大量破壊兵器へと変貌させる。それは、私という存在が依って立つすべての基盤を根底から揺るがす、絶対的な格差の象徴なのだ。
2.3. 個人的な因縁への序章
読者の皆さんは、菅野氏がなぜこれほどまでに一人のミュージシャンに対して過剰な反応を示すのか、不思議に思うかもしれない。だが、これは単なる僻みや嫉妬ではない。この感情の背後には、私の人生における決定的な敗北の記憶、決して消えることのない苦い個人的な因縁が横たわっているのである。
——————————————————————————–
3. ある音楽フェスでの惨劇:私的敗北の記憶
3.1. 恋愛史に刻まれたトラウマ
あれは、若き日のある音楽フェスでの出来事だった。音楽がもたらす祝祭的な高揚感は、時に残酷な舞台装置へと変貌する。共に音楽を楽しむという幸福なはずの空間が、一瞬にして個人の尊厳を打ち砕き、生涯忘れ得ぬトラウマを刻み込む場と化した、あの日のことを。
3.2. 悲劇の顛末
当時、付き合い始めてまだ日の浅い彼女と、そのフェスを訪れていた。確か、交際3ヶ月ほどの、最も浮かれている時期だったと思う。
- お目当てのスカパラのステージが始まると、僕らは胸を躍らせながらステージ近くへと向かった。
- ステージ上で躍動する谷中敦氏の姿が目に飛び込んできた、まさにその時。彼女は私の顔をじっと見つめた。ステージの照明に照らされた彼女は、一切の感情を排したような目で私を見つめ、そして、はっきりとこう告げたのだ。「菅野君ごめん、やっぱり別れよう。谷中さん見てたら、菅野君の顔見れなくなっちゃった」
- この一言は、私の心に深々と突き刺さった。あの日、あの瞬間から、谷中敦は私にとっての個人的な「敵」となった。ユーモアで語るにはあまりに悲しく、悲劇として語るにはあまりに滑稽な、私の完膚なきまでの敗北の記憶である。

3.3. 結論:音楽と人生の不条理
この個人的なエピソードを振り返る時、音楽という文化が持つ残酷な二面性を思わざるを得ない。中島みゆきの「ファイト!」のように、それは時にどん底にいる人間を励まし、立ち上がる力を与えてくれる。しかし、スカパラのステージがそうであったように、音楽は時に、残酷なまでの現実と、決して乗り越えることのできない絶対的な格差を個人の眼前に突きつける装置ともなりうるのだ。
世代を超えて愛され続ける名曲がある一方で、個人が決して超えることのできない「モテ」という名の不条理な壁が存在する。結局のところ、いつの時代も、すべては谷中敦が持っていく。ただ、諦観とともに、このどうしようもない事実を受け入れるしかないのだろう。
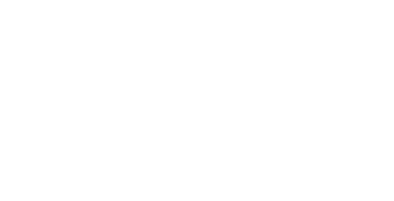















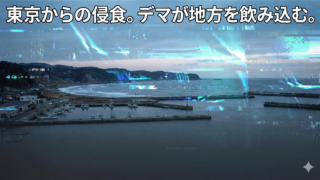





コメント