序論:見せかけの議論を超えて
2025/12/1(月)朝刊チェック:沖縄を見よ。
日本において、スパイ防止法の制定を巡る議論は、政治的な季節風のように定期的に吹き、そして消えていく。しかし、菅野氏が提起するのは、この議論そのものが根本的に焦点を誤っており、より深刻で構造的な国家的危機――すなわち、日本の主権が静かに、しかし確実に侵食され続けているという現実――から国民の目を逸らすための、壮大な茶番劇になっているのではないかという問いである。この問題を解き明かすため、菅野氏は「愛国心はパンツである」という、一見すると挑発的な比喩を分析の道具として用いる。このレンズを通して、現代日本における真の愛国心のあり方を問い直し、主権なき国家においてスパイ防止法がいかに機能不全に陥るかを論証していく。
1. 「愛国心はパンツである」という比喩の解体
いかなる国家安全保障法制の是非を問う以前に、我々はその基盤となるべき「愛国心」という概念を理性的に定義する必要がある。「愛国心はパンツである」という比喩は、本質的で私的な信念と、感情的で誇示的なパフォーマンスとを峻別するための、極めて有効なフレームワークを提供する。
この比喩は、二つの核心的な性質を明らかにしている。
- 私的で普遍的なもの : 愛国心とは、文明国の市民であれば誰もがごく自然に、そして私的に有している感覚である。それはパンツと同じで**「みんな持ってるんです」、「みんな履いてるんです」**。特別に声高に叫ぶものではなく、内に秘められた当然の帰属意識なのだ。
- 公的な「振り回し」という異常行為 : 一方で、その私的な感情を公の場で過度に誇示する行為――例えば**「日の丸振ったりとか」する行為――は、パンツを衆人環視の中で振り回したり、頭にかぶったりする行為に等しい。それは理性を欠いた「キチガイ」**の振る舞いであり、健全な精神の表れとは到底言えない。
この比喩をさらに敷衍すれば、他者の愛国心を問う行為の暴力性もまた、明確になる。誰かに「お前愛国心あんの」と問い詰めることは、「あんたパンツ履いてるか」と尋ねる変態的な行為と何ら変わらない。そのような問いを発する者は、他者の内面という最もプライベートな領域に土足で踏み込む**「性犯罪者」**にも等しい。
理性的な愛国心とは、このように静かで私的なものである。では、その静かな眼差しは、本来、国家が直面するいかなる危機に向けられるべきなのだろうか。
2. 真の国家的危機:米軍による「警察権の凌駕」という現実
表面的な愛国心が国旗や国歌といったシンボルに向けられる一方で、真の愛国心は国家の根幹、すなわち主権と法の支配に向けられる。そして今、日本の主権が最も深刻かつ継続的に侵害されている現場こそ、米軍による「警察権の凌駕」という、多くの国民が目を背ける現実である。
「警察権の凌駕」とは、文字通り、日本の法執行機関が持つべき排他的な権限が、外国の軍隊によって踏みにじられている状態を指す。国内の治安を維持し、法を執行する権利は、その対象が誰であろうと、本来**「日本の警察にしかあるはずがない」。しかし、現実には米軍の憲兵隊が日本の街を闊歩し、警察権を行使するという「異常」**な事態が常態化している。
その決定的な証拠が、沖縄で撮影された映像である。米軍の憲兵隊が、日本の公道でアメリカ人観光客を取り押さえる――この光景こそが、**「アメリカ軍の警察権力が日本の警察権力を凌駕した」**瞬間である――文字通り、日本の権力がアメリカの権力にその『格』と『実質』において完全に凌駕され、無効化された瞬間である。この構造は、かつて日本が戦争への道を突き進む一因となった「ゴーストップ事件」のそれと酷似しており、その歴史的な危険性を我々に警告している。
この国家の無力さの根源には、「昭和憲法とほぼ同じぐらい重たい」「逮捕どころか取り調べすることさえできない」。
この法的な無力さがもたらす悲劇は、決して抽象的な話ではない。米兵が日本人歩行者を車で轢き殺しても、日本の司法制度で裁かれることなく本国へ帰国し、数ヶ月後には家族との再会を祝う写真をFacebookに投稿する。これが、主権の不在がもたらす、正義の死である。自国の法を自国の領土で執行できないこの動かぬ現実を前にして、新たな「法律」を論じることの虚しさは、もはや明らかではないだろうか。
3. 主権なき国家のスパイ防止法――構造的に破綻した法案
日本の主権がこれほどまでに深く傷ついているという現実を踏まえたとき、スパイ防止法の制定を巡る議論は、その論理的基盤そのものが崩壊していると言わざるを得ない。核心を突く問いは、極めてシンプルである。
「この現状でアメリカのスパイ取り締まれるんですか」
この問いを起点に、法案が抱える構造的な破綻を分析すると、その矛盾は火を見るより明らかである。
- 日米地位協定という「壁」: 最大の矛盾は、日米地位協定の存在である。仮に米軍関係者が日本の機密情報を盗むスパイであったとしても、日本の警察は彼らを捜査・逮捕する権限を持たない。日本にとって安全保障上、最も重要な関係を持つ外国の諜報活動に対して、全くの無力。これでは、法律の体をなさない。
- 差別的運用という矛盾 : もし「アメリカ人だけは例外」として法律を運用すれば、それは法の支配の根幹である「法の普遍性」を自ら破壊する行為に他ならない。法の下の平等を著しく侵害するだけでなく、アメリカを例外とすれば、英国、韓国、シンガポールといった他の同盟国も同様の特権を要求するだろう。その結果、指定された国々の関係者は**「スパイし放題」となり、この法律は一部の国を対象とした恣意的な人権弾圧の道具に成り下がる。それはもはや法ではなく、権力者の都合を書き記した法的擬制(リーガル・フィクション)**に過ぎない。
- 「いらん法律」への帰結: これらの構造的欠陥により、スパイ防止法は必然的に、その目的を達することのできない、単なる政治的パフォーマンスのための**「いらん法律」**(いらない法律)となる。
そもそも、この議論の欺瞞性は、かつて高市早苗氏が国会で答弁したように、情報の「漏洩をすることで盗む行為」自体は、既存の刑法等で既に取り締まりが可能であるという事実によっても裏付けられる。にもかかわらず、あえて「スパイである」という存在・身分そのものを罰する新たな法律を求める動きは、それが法的な欠陥を埋めるためではなく、特定の政治的意図を達成するための道具であることを示唆している。主権侵害の最大要因には目をつぶり、対処可能な問題のために新たな悪法を求める――これこそが、議論全体の倒錯した本質なのである。
4. 思考停止の正体:「正常化バイアス」と「名誉白人」という病理
これほど明白な主権侵害と論理的矛盾を前にして、なぜ多くの人々は沈黙し、あるいは現状を容認してしまうのだろうか。その構造的欠陥が自明であるにもかかわらず議論が続く理由は、もはや論理ではなく、日本社会に根付く集団的な心理的病理に求めなければならない。
第一の病理は**「正常化バイアス」**である。自国の警察権が外国軍隊に凌駕されるという屈辱的な現実を前にしても、多くの人々――菅野氏が「田舎者」と揶揄する、隷属を現実主義と勘違いする層――は、「安全保障上重要だ」「仕方がないんだ」という決まり文句で自らを納得させ、思考を停止させてしまう。
そして、この正常化バイアスの土台となっているのが、より根深い**「名誉白人」という病理である。これは、多くの日本人が「自分たちのことをアメリカ人やフランス人やイギリス人と同じような名誉白人だと思っている」という「大きな勘違い」に他ならない。強者(アメリカ)の横暴を肯定することで、自分も強者の側に立ったかのような錯覚に陥るのだ。まさにこの「名誉白人」という自己欺瞞こそが、日米地位協定という法的異常性を許容し、主権侵害という屈辱に対して、日本国民が年間4兆円**もの巨費を投じて耐え忍ぶことを可能にしている精神構造である。
皮肉なことに、この異常な状況に対する健全な感性は、当のアメリカの市民から発せられている。日本の街を米兵がパトロールする映像に対し、アメリカのSNSでは**「白人の感性」**から「めっちゃ悪魔的」「アメリカってテロリスト国家やんけ」といった厳しい批判が巻き起こる。自国民でさえ「悪魔的」と評する行為を、当事者である日本人が「仕方がない」と受け入れている。この倒錯こそが、日本の病理の深刻さを物語っている。
結論:真の愛国心とは、主権への問いである
スパイ防止法を巡る喧騒は、見せかけの議論に過ぎない。真の国家的危機は、日米地位協定という制度に具現化され、「警察権の凌駕」という日常風景に露呈する、主権の不在そのものである。
本稿が「愛国心はパンツである」という比喩を通して明らかにしてきたように、真の愛国心とは、日の丸を振り回すことでも、他者に忠誠を強要することでもない。それは、静かで、理性的で、そして粘り強い問いかけの中にこそ宿る。その問いとは、これだ。
「なんで日本の警察権力がアメリカの警察権力に凌駕されなきゃいけないの」
この根源的な問いを、一人ひとりが自らに投げかける勇気。それこそが、内に秘めたパンツを履くように、全ての主権者が持つべき静かな誇りであり、本物の愛国心の発露である。旗を振るという安易な自己満足に逃げるのか、それとも主権という不都合な真実と向き合うという、屈辱的だが国家にとって不可欠な責務を果たすのか。日本の安全保障に関する、あらゆるまっとうな議論は、そこからしか始まらない。

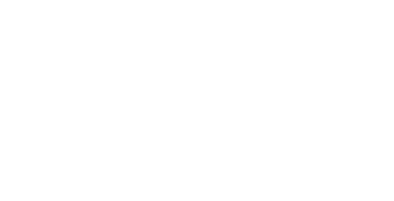















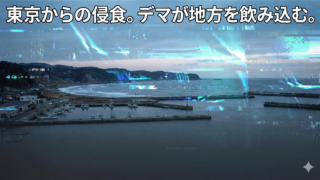






コメント