2026/1/10土曜雑感:高市首相、衆院解散を検討
序文:死者を送る儀式の変質
近年、葬儀のあり方がおかしくなっている。故人の好きだった音楽を流す「音楽葬」だの、その人柄を反映した「ユニークな葬式」だのが、ひとつのトレンドとして蔓延り始めた。しかし、この風潮に対し、俺は極めて批判的な視点を提示する。一見、故人への愛情表現と見なされがちなこれらの新しい儀式が、いかにその本質から逸脱し、唾棄すべき自己満足に堕しているか。その腐臭を暴き出してやろう。
俺の主張の核心は、驚くほどシンプルだ。「葬式は死んだ人間のためではなく、生き残った人間のためにある」。この思想は、葬儀を個人の自己表現の場と勘違いしている現代の軽薄な風潮に、冷徹な一撃を加える。
本稿ではまず、俺がいかにこの問題を深刻に捉えているかを、ある独特な比較から解き明かす。次いで、葬儀が本来持つべき社会的な機能について論じ、なぜユニークな葬式がその機能を破壊するのか、その背景にある世代的なエゴイズムと、理想とはかけ離れた実践的な失敗を白日の下に晒していく。
——————————————————————————–
1. ホモ・サピエンスとして最も劣悪な三つの行為
「ユニークな葬式」がいかに唾棄すべきものかを理解するには、まず俺が提示する衝撃的な比較から始めるのが手っ取り早い。これは単なる比喩ではない。葬儀という儀式の根幹を揺るがす行為に対する、最大級の軽蔑と警鐘が込められている。
「人間としてやってはいけないこと」、すなわちホモ・サピエンスとして最も劣悪な行為には序列がある。
- 一番やってはいけないこと:兄貴のくせに妹を殴ること。
- 次にやってはいけないこと:親が揚げている唐揚げの、二度揚げの合間につまみ食いをすること。
- そして、それらに続く悪行が:ユニークな葬式を挙げたがること。
最初の二つが、家族という共同体の信頼を根底からぶっ壊す、倫理的に許されざる人間のクズの所業であることは言うまでもない。ユニークな葬式をやりたがる連中は、これらと同列の、最低の行為に手を染めているのだ。この比較は感情的な非難などではない。葬儀という儀式が持つ社会的・文化的な重みを無視し、個人的なエゴイズムで汚す行為がいかに罪深いかを、最も分かりやすい形で突きつけているに過ぎない。
では、なぜ葬儀はこれほどまでに重要な意味を持ち、その形式は守られなければならないのか。その答えは、葬儀の本質的な目的にある。
2. 葬式の真の目的:「生き残った者」のための儀式
多くの人間が葬儀を「故人を偲び、送るための儀式」だと勘違いしているが、それは違う。葬儀の真の目的は、死者ではなく「生き残った者」の側にあるのだ。
葬式は死んだ人間のためになんかしてない。生き残ってる人間のために葬式してる。
人間は年を重ねるにつれ、葬式に参列する頻度が加速度的に増していく。若い頃は数年に一度だったものが、やがて年に数回、ついには月に数回という現実が訪れる。この経験こそが、生きている人間に「死」という絶対的な現実を受容させるための、極めて重要なプロセスなのだ。
この社会的装置が機能するためには、絶対的な条件がある。
- 葬儀は常に「ワンパターン」であるべきである。 どの葬儀も同じ形式、同じ流れで執り行われる必要がある。読経が響き、焼香の煙が立ち上り、誰もが同じ作法で手を合わせる。この反復性こそが、とてつもなく重要なのだ。
- 定型化された儀式は、死を受容するための装置として機能する。 何度も同じ形式の他人の葬式に参列することによってのみ、生きている人間は「次はわし(私)の番やで」と、自分自身の死を少しずつ、しかし確実に受け入れることができる。友の死を悼み、手を合わせながら、自らの死を予感する。つまり、画一的な葬式とは、残された我々が他人の死に繰り返し直面することで、いずれ来る自らの死に備えるための、実に巧妙な仕掛けなのだ。それが葬式の全機能だ。
しかし、この重要な社会的装置が、特定の世代の歪んだ価値観によって、今まさに破壊されようとしている。
3. 「団塊の世代」のエゴイズム:自己顕示欲が儀式を汚す
このユニークな葬式という悪趣味な流行の背景には、特定の世代――すなわち「団塊の世代」の精神性がある。俺は、このトレンドを牽引する70代から80代の「クソじじいたち」の振る舞いを、容赦のない言葉で断罪する。
「ビートルズを流せ」「ギターを弾いてくれ」
これらの要求は、死という厳粛な場面において、あまりにも場違いな「かっこつけ」であり、究極の自己顕示欲の発露に他ならない。死という人生最後の舞台でさえ、自分という存在を特別なものとして演出しようとする、浅ましいエゴの表れだ。
俺が参列した、セックス・ピストルズの曲を流した葬儀の例は、この批判の核心を鮮明に描き出す。その葬儀では、香典返しの挨拶状にこう書かれていたという。
亡くなった夫の好きなセックス・ピストルズの曲を流せというのが遺言でした。これからもどこかでピストルズの曲を聴いたら、彼のことを思い出してください。
ふざけるな。「なんでピストルズの曲にお前を結びつけんねん」。これは、音楽という普遍的な文化遺産に対し、「お前という存在の手垢がつく」 行為だ。参列者に対して故人の記憶を永続的に強制する、醜悪極まりない「エゴ」なのである。本来、生き残った人々が自らの死と向き合うための儀式が、死者の自己愛を満たすための個人的なステージへと変質させられてしまうのだ。
だが、この問題は哲学的な領域に留まらない。こうした自己満足に満ちた理想は、現実の葬儀の現場で、無惨な技術的失敗として結実している。
4. 理想と現実の乖離:音楽葬の技術的・実践的失敗
理念として唾棄すべき音楽葬は、その実践においてもほとんどが悲惨な失敗に終わる。その原因は、理想と現実の致命的な乖離にある。
音響の問題 : そもそも葬儀場のPA(音響)システムなど、普段お経や弔辞といった人間の声を明瞭に届けるために設計された代物だ。大抵はTOAのスピーカーだ。そこにレッド・ツェッペリンの「天国への階段(Stairway to Heaven)」なんぞを流せばどうなるか。アコースティックギターの繊細な高音、あの「キュン」という音が鳴る瞬間に、「必ず割れる」。故人を偲ぶはずの荘厳な空間は、耳障りなノイズによって台無しにされる。
運営の問題 : 音楽の再生を担当するのは、音楽の専門家であるDJではない。葬儀屋のスタッフだ。彼らは葬儀のプロではあっても、音楽演出のプロではない。その結果、曲の繋ぎは**「むちゃくちゃ」**になり、素人感丸出しの気まずい時間が流れるだけだ。
ここで、かつて上岡龍太郎が映画『アルマゲドン』を評した際の有名な逸話が頭をよぎる。
「穴掘りのプロに宇宙飛行を教えるより、宇宙飛行士に穴掘りを教える方が早い」
これは音楽葬が抱える根本的な「見当違い」さを見事に言い当てている。音楽のプロであるDJに葬儀の段取りは組めず、葬儀のプロである葬儀屋は音楽の扱いが絶望的に下手なのだ。この構造的な欠陥により、ほとんどの音楽葬は、故人の自己満足すら満たせない、ただの滑稽な茶番劇に終わる。
しかし、ごく稀に、その例外も存在した。その成功と失敗を分かつ境界線は、一体どこにあるのか。
5. センスという名の境界線:唯一評価された音楽葬
俺の批判は、音楽葬という形式そのものへ向けられているわけではない。俺が軽蔑するのは、それを自己顕示欲の道具として利用する人間の「センス」や「教養レベル」である。そのことを証明するのが、俺が唯一「センスええな」と評価した音楽葬の事例だ。
その葬儀には、いくつかの際立った特徴があった。
- 故人は「とんでもない金持ち」であり、圧倒的な教養と見識を兼ね備えた人物だった。
- 葬儀自体は、臨済宗の伝統的な形式に則り、極めて厳粛に執り行われた。自己顕示の要素は一片たりともなかった。
- 音楽が使用されたのは、たった一度きり。出棺という、他の音が何もない静寂のタイミングで、オーティス・レディングの「ドック・オブ・ベイ((Sittin’ On) The Dock of the Bay)」が静かに流された。
この演出がなぜ肯定的に評価されたのか。それは、音楽が故人のエゴを押し付けるための道具ではなく、計算され尽くした演出として完璧に機能していたからだ。葬儀全体の厳粛な空気を壊すことなく、出棺という最も感動的な瞬間に、故人の人柄を象徴する一曲が添えられる。それは自己顕示欲の発露ではなく、故人の持つ圧倒的な教養レベルとセンスに裏打ちされた、芸術的な行為であった。
**「結局はセンスなのよ」**という俺の結論は、この問題の本質を突いている。センスのない人間が背伸びをして個性を演出しようとすれば、それは滑稽で醜悪な自己満足に終わる。真のセンスとは、いつ、何をすべきで、何をすべきでないかをわきまえる知性そのものなのだ。
結論:死ぬ時ぐらい自己愛を忘れろ
「ユニークな葬式」というトレンドは、現代社会が抱える根深い病を浮き彫りにする。それは、本来「生き残った人々」のためにあるべき社会的な儀式を、故人の最後の自己愛を満たすための私的な舞台へと変えてしまっているという事実だ。
伝統的で画一的な葬儀が持つ、参列者に「死」を受容させるという極めて重要な社会的機能は、安っぽい個性の主張によって無残にも破壊される。他人の死を通して自らの死と向き合うべき厳粛な場は、故人の個人的な趣味や思い出を強制される不快な空間へと成り下がる。
この倒錯した現状に対し、俺が突きつけるメッセージはただ一つ。それは、人間として守るべき最低限の礼儀であり、死者と生者が共有すべき最後の作法でもある。
死ぬ時ぐらい自己愛を忘れろ。

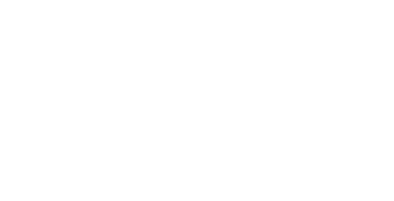















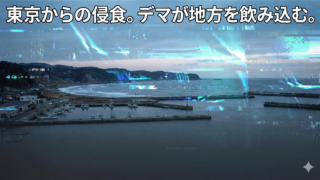





コメント