2026/1/5(月)朝刊チェック:潜在的売国奴
序文:朝刊チェックの時間
私が菅野完でございます。朝刊チェックの時間がやってまいりました。頑張っていかなあかんなぁ~言うてるところなんですけど
菅野完氏の分析を通じて本稿が試みるのは、現代日本社会が直面している根深い病巣――すなわち「知性の劣化」と「精神性の退行」――を解き明かすことである。一見すると無関係に見える、兵庫県政の混乱、お好み焼きをめぐる食文化論、そして台湾情勢への無理解。これら個別の事象は、実は一本の線で繋がっている。それは、物事の複雑な細部を捉える「解像度」を失い、安易な物語に逃避し、近代市民としての美学と責任を忘却した、この国の知性と精神の惨状である。本稿は、その構造を一つひとつ丁寧に解きほぐしていく。
——————————————————————————–
1. 「粋」と「野暮」:失われた美学をめぐる闘争
現代社会、とりわけ兵庫県政に見られる精神的な「ダサさ」を論じるにあたり、いきなりその醜悪さを糾弾するだけでは不十分である。まず評価の基準となる「美学」、すなわち何が「かっこいい」のかを提示しなければ、批判は単なる悪口に堕してしまう。菅野完氏の分析の巧みさは、まず評価軸となる「ものさし」として、植木等と小松政夫の師弟関係にまつわるエピソードを戦略的に配置する点にある。
その物語はこうだ。かつて小松政夫は、トップセールスマンとして月給12万円(当時の大卒初任給の実に6倍)を稼ぐ成功を収めていた。しかし彼はその地位を捨て、月給わずか数千円で喜劇王・植木等の付き人になる道を選ぶ。当然、生活は困窮する。ある日、師弟で蕎麦屋に入った際、金のない小松は遠慮して一杯の「かけそば」だけを注文した。それを見た植木は、自身のために「かけそば」と「天丼」を注文する。そして、いざ食事が運ばれてきたその瞬間、彼はこう呟いた。
「いけねえ、医者に揚げ物止められてたの忘れてた。お前食え」
このエピソードが単なる「芸能界のいい話」で終わらないのは、菅野氏の論理において、これが以下の三つの重要な機能を担っているからだ。

- 美的基準としての「粋」 植木等の行動は、単なる優しさではない。彼は「お前、金ないんだろ。俺がおごってやるよ」といった直接的な言葉は決して使わない。それでは相手のプライドを深く傷つけてしまうからだ。「医者に止められた」という絶妙な嘘をつくことで、相手の尊厳を守りながら、腹一杯食べさせる。この、相手の心情を深く「察し」、洗練された振る舞いで目的を達する姿勢こそ、成熟した大人の美学である**「粋」**の極致なのである。 これに対し、兵庫県の斎藤元彦知事が参拝した際に「知事参拝」などという看板を嬉々として掲げてしまう神社の振る舞いや、それを許容する知事の態度は、まさしくこの対極にある。権力者との繋がりをひけらかし、何の配慮も美学もないその様は、菅野氏の言葉を借りれば「野暮」で「クソ田舎臭い」精神性の発露に他ならない。
- 精神的浄化装置としての物語 斎藤知事周辺の「能力が低く、教養がなく、ダサい」現実を見続けることは、精神的な汚染を伴う。菅野氏は、そうした「汚いもの」を見た夜、布団の中で必死に「何かかっこいいことはなかったか」と記憶を探り、この植木等の物語にたどり着いたと述懐する。これは、優れた文化や物語が、現実社会の腐敗に対する**「解毒剤」**として機能することを示している。「美しいもので上書きしないと、やっていられない」という言葉は、文化芸術が我々の精神衛生を守るための不可欠な装置であることを物語っている。
- 「覚悟」の提示 この物語は、小松政夫の生き様を通じて、もう一つの重要な基準を提示する。彼は年収数千万円に相当する安定した生活を捨て、芸の道に人生を賭けた。この経済合理性を超えた**「人生を賭けた潔さ」**は、権力にしがみつき、長いものに巻かれる現代の政治家やその周辺の人々の浅ましさとは鮮烈な対比をなす。ここに描かれるのは、単なる美学に留まらない、プロフェッショナルとしての「覚悟」なのである。
この植木等の天丼が示す「粋」の美学は、単なる過去の美談ではない。それは、次に論じる、より深刻な日本の知的・精神的な劣化を測るための、失ってはならない基準点なのである。
——————————————————————————–
2. 「解像度の低い知性」:お好み焼きが暴く日本の知的怠慢
ここで菅野氏が繰り出すのが、彼の論理構造の真骨頂とも言える「お好み焼き」という名の解剖刀である。彼はこのありふれた食文化をメスに、日本社会、特に中央のメディアや東京の言論空間が抱える知的怠慢という病巣を、四つの階層にわたって鮮やかに切り開いてみせる。彼の提示する「お好み焼き論」は、我々の知的怠慢を映し出す鏡なのである。
その核心は、以下の四つの階層構造で解き明かすことができる。
- 第一階層:東京中心主義による単純化 全ての出発点は、東京の人間が西日本の文化を捉える際の圧倒的な「解像度の低さ」にある。彼らにとって、名古屋より西の食文化は「みんなお好み焼き」という雑なイメージで一括りにされ、そのバリエーションも**「大阪風か広島風か」**という、極めて安易な二元論でしか認識されていない。これは、複雑な現実を理解しようとせず、単純なステレオタイプに押し込めて満足する知的態度の典型である。
- 第二階層:無視される具体的細部(リアリティ) 現実の文化的多様性は、その二元論を嘲笑うかのように豊かで複雑だ。文化の差異は、京都、奈良、大阪、兵庫で全く異なり、兵庫県内ですら神戸の東側と西側、加古川、姫路で細分化され、最終的には**「中学校の校区単位」**で変容するほどのリアリティを持つ。その違いは、以下の具体例にこそ宿っている。
- キャベツの切り方: ふわっとした食感を生む「みじん切り」か、歯ごたえを残す「親指の爪サイズ」か。
- 魚粉の種類: 香り高い「カツオ」か、濃厚な旨味の「サバ」か、あるいは独特の風味を持つ「ウルメ」か。
- 生地と焼き方: 生地そのものの分厚さや、それをどのように焼き上げるかという技術。
- これらの物理的実体(マテリアリティ)を無視した時点で、それは批評ではなく、ただの無知の表明に過ぎない。
- 第三階層:文化侵略としての均質化 この豊かな文化的多様性を破壊しているのが、全国的な流通網を持つ特定ブランドの存在だ。菅野氏は、広島発祥のオタフクソースを「文化の侵略者」「ブラックバス」と呼び、その普及を痛烈に批判する。かつて関西の町々には、オリバー、バラ、イカリといった地元のソース会社があり、それが地域固有の味を育んできた。しかし、商業主義の波に乗った「侵略者」が市場を席巻し、何も知らない人々が「お好み焼き=オタフクソース」と短絡的に結びつけることで、文化の均質化、すなわち多様性の死が進行しているのである。
- 第四階層:偽のナラティブへの逃避 さらに根深い問題は、人々が歴史的事実よりも心地よい「物語」を好む傾向にあることだ。お好み焼きのルーツを丹念に辿れば、実は東京の浅草周辺にあった「文字焼き」や「どんどん焼き」に行き着くという事実がある。しかし、世間で流布しているのは「戦後、お母ちゃんが子供たちのためにありあわせの材料で焼いた」といった、情緒的で郷愁を誘う**「偽のナラティブ」**である。人々は、複雑な事実よりも、分かりやすく感動的な物語に安易に飛びつき、それを真実として消費してしまう。
この知的怠慢は、単なる食文化への無関心ではない。それは、複雑な現実を前に思考を放棄し、安易な二元論に逃げ込むという精神の「型」そのものである。そしてこの「型」が、隣人の生存がかかった国際問題に適用されるとき、その無邪気さは罪へと転化するのだ。
——————————————————————————–
3. 台湾問題に見る「当事者意識」の欠如
「お好み焼きの解像度」という、一見すると些細な食文化の問題が、なぜ台湾という国家の存亡に関わる国際情勢の理解に直結するのか。この論理の飛躍こそが、菅野氏の分析の核心であり、我々日本人が目を背けてきた不都合な真実を突きつける。お好み焼きを雑にしか語れないその知性が、隣人の苦悩をも雑に扱っているのだ。
日本の台湾理解における「解像度の低さ」は、まさにお好み焼きのメタファーで完璧に説明できる。多くの日本人は、台湾の世論を「独立か統一か」、あるいは「親日か反日か」といった単純極まりない図式でしか見ていない。これは、西日本の複雑な食文化を「大阪風か広島風か」でしか語れない知性と全く同質である。現実の台湾社会には、独立、統一、現状維持といった選択肢の中に無数のグラデーションがあり、人々は複雑な歴史認識と生活実感に基づいて自らの立場を形成している。しかし、日本のメディアや言論は、そのリアリティを捉えようとせず、外部から見た分かりやすいレッテル貼りに終始しているのだ。
そして、本稿が指摘する最も核心的な批判は、日本の**「第三者のふりをする罪深さ」**にある。
- 問題の起源 そもそも、なぜ台湾の政治状況はこれほどまでに複雑なのか。その根源を辿れば、日本の植民地支配に行き着く。台湾という土地に、後の政治対立の種を蒔いたのは、紛れもなく100年前の日本なのである。我々こそが、この問題を作り出した紛れもない**「当事者」**なのだ。
- 無責任な態度 この歴史的事実を忘却し、「あの人ら、なんで揉めてんの?」と、まるで無関係な隣家の火事を眺めるかのように高みの見物を決め込む。この態度は単なる無責任ではない。自らが引き起こした悲劇の舞台で、その歴史を忘却し、批評家気取りで野次を飛ばすに等しい。それは倫理的な怠慢を超えた、知性への裏切りであり、歴史への冒涜である。ソース内で示されるアナロジーは、この無責任さを的確に言い表している。これは、**「親戚の家の複雑なトラブルの原因が、実は自分の祖父が遺産相続をめちゃくちゃにしたことにあるのに、その事実を忘れて『あそこは大変だねえ』と無邪気に批評している」**ようなものだ。これほど無責任で恥ずべき態度はない。
では、当事者である日本は、台湾とどう向き合うべきなのか。菅野氏が提唱するのは、観光地としての「文化消費」や感情的な「親日」論からの脱却である。魯肉飯や故宮博物院を楽しむだけでは不十分だ。今、日本が果たすべきは、中国の脅威に晒される台湾の言論人や知識人が、何を考え、何を議論しているのかを、可能な限り高い解像度で取材し、日本語による「知的記録」として後世に残すことだ。それは、かつて戦争を引き起こし、台湾を苦境に追いやった国の言論人が果たすべき、最低限の「戦争のけじめ」なのである。
この知的怠慢と歴史的無責任さは、単なる国際問題への無理解ではない。それは、我々自身の足元を崩壊させている、より広範な社会全体の劣化そのものの症状なのだ。
——————————————————————————–
4. 結論:教養の瓦解と「田舎者」への退行
これまで論じてきた美学の喪失、解像度の低下、そして歴史認識の欠如は、それぞれが独立した問題ではない。これらはすべて相互に連関し、最終的には**「近代国家の国民としての基盤(OS)の崩壊」**という、日本の国家存亡に関わる一つの巨大な危機を示している。美意識(粋)の欠如が、知的怠慢(解像度の低さ)を許容させ、その知的怠慢が、歴史的責任の忘却を可能にする。この悪循環の果てに、我々は国際社会で通用しない、前近代的な「田舎者」へと退行しつつあるのだ。
この日本社会が直面する「教養の瓦解」は、以下の二つの側面から具体的に論証できる。
- 絶望的な体験格差 日経新聞が報じたように、現代日本では上位2割のエリート層と残り8割の一般層との間で、「文化体験」の格差が決定的に開いている。富裕層の子供たちが美術館や劇場に通い、欧米のエリートと対等に渡り合える教育を受ける一方で、大多数の子供たちはそうした機会に恵まれない。菅野氏が挙げる**「5歳までにプロコフィエフの『ピーターと狼』を生演奏で聴いたことがあるか」**という指標は、単なる音楽鑑賞の有無を問うているのではない。それは、近代的な教養資本を社会全体で継承するシステムが、もはやこの国で機能不全に陥っていることの証左なのである。この体験格差は、国民を回復不可能なレベルで分断している。
- 国際社会からの孤立 この教養の欠如は、日本のエリート層ですら国際社会の対話から弾き出されるという悲劇的な事態を招いている。リムパック(環太平洋合同演習)のような国際的な場では、各国の将校たちがシェイクスピアやディケンズを引用しながら、高度な知的会話を繰り広げる。しかし、日本の自衛官は、その教養の文脈(コンテキスト)を共有していないため、会話に入ることができない。これは単なる英語力の問題ではない。欧米の近代社会が共有する**リベラルアーツ(基礎教養)**というOSがインストールされていないため、そもそも対話が成立しないのだ。この構造的欠陥は、日本を国際社会における孤立へと追いやっている。
そして、この日本全体の知的・精神的退行の「象徴」として、兵庫県知事・斎藤元彦氏をめぐる一連の事象が再び浮かび上がる。

- 歴史的退行: 100年前、兵庫県民は孫文の「大アジア主義」という高度な思想に共鳴できた。しかし現代の兵庫県民が熱中しているのは「斎藤元彦と立花孝志」である。百条委員会でその無様を晒した知事が繰り広げる、お粗末な政治ショーなのだ。この知性の墜落は「文化程度の低下」という言葉ですら生ぬるい。
- 近代的規律の崩壊: 四宮神社の「知事参拝」看板問題は、憲法が定める政教分離という近代的規律をいとも簡単に無視し、権威に擦り寄る精神性の表れだ。これは法治国家の市民としてのリテラシーが欠如した、まさに「田舎者」的な振る舞いである。

菅野氏の論考全体を貫く警告は、一つの鮮烈なアナロジーに集約される。現代日本社会は、いわば**「悪臭を放つゴミ屋敷」と化している。そして最も恐ろしいのは、ゴミ屋敷の住人そのものが悪臭に鼻を麻痺させ、自らが発する腐臭に無自覚であることだ。だからこそ、植木等の「粋」のような「一輪の薔薇の香り」**に意識的に触れ、失われた嗅覚を叩き起こし、まずは自らの惨状を自覚することから始めなければならない。それによってのみ、我々はこの知的・精神的なゴミ屋敷から脱出する一歩を踏み出すことができるのである。
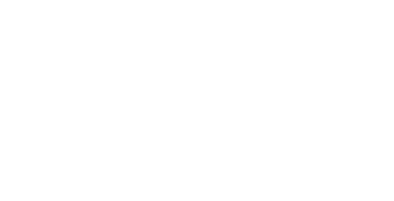









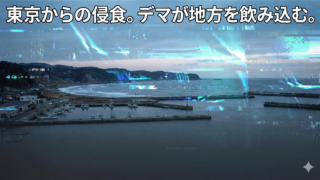











コメント