菅野氏は、「その他(システムと社会論)」というより大きな文脈において、日本の政治システム、特に官僚制度と学力が果たす役割、およびそれらがどのように機能不全に陥っているかについて、非常に明確な主張を展開しています。
官僚制度と学力に関する菅野氏の主張
1. 官僚制度の性質と役割
官僚制度は、身分保障という原則に基づいて成り立っています。公務員は一度就職すれば、よほどのことがない限り解雇されない安定した立場にあります。キャリア官僚約5,000人が霞ヶ関で勤務しており、彼らは国家の予算を編成する役割を担っています。
- 予算編成の主体: 官僚は、国民から徴収した税金(みんなから吸い取った税金)を予算化し、「こうやって使わせてほしい」と要求します。
- チェック機能の必要性: 国民の代表である国会議員は、この予算案をチェックし、官僚が「嘘をついていないか」を確認する役割があります。議会(国会、都道府県議会、市町村議会)は、会社でいう会計や監査部の機能(予算の審議や決算のチェック)を担っていると説明されています。
- 権力バランスの維持: 身分保障のある官僚と、選挙により常に不安定な立場にある国会議員が予算について対峙(たいじ)する際、健全なシステムを保つためには、議員の給料が高い方が健全であると論じられています。これは、仕事として対等な立場で議論するために必要であり、給料が同等であれば不健全であると指摘されています。
2. 学力の重要性
菅野氏は、官僚制度や政治家といった知的な活動を行う者に求められる能力として、学力、特にペーパーテストで測られる能力を強く擁護しています。
- 「ペーパーテストは無意味」という批判への反論: 「ペーパーテストができるだけではダメだ」という批判は、「田舎者」がよく言う嘘であると断じています。
- 学力と実力の関連性: ペーパーテストができない人間は、テストで実力を発揮できるはずがない。また、学校の勉強ができない人間に、学校の勉強以外の知性的な仕事が求められるはずがない、とも述べています。
- 学力の必要条件性: 学校の勉強は、十分条件であるだけでなく、必要条件であると強調されています。点数で問われる勉強さえできない人間が、点数で問われない問題に取り組めるはずがない、という論理です。
「システムと社会論」のより大きな文脈
これらの官僚制度と学力の議論は、日本社会における**「税金の使途チェック」**というシステムの根幹をめぐる問題として提示されています。
- 国家予算の巨大さとチェックのコスト: 日本の一般会計予算は115兆円という莫大な額であり、1万円札で積み上げると国際宇宙ステーション(ISS)よりもさらに高く、横に並べると東京から種子島までの距離に匹敵します。
- システムの危機としての議員定数削減論: この途方もない予算(115兆円)の使途をチェックするシステムとして議会が存在しますが、国会議員の数を減らす(例:700人から350人へ)という提案(特に維新の「身を切る改革」)は、予算チェックの機能そのものを弱体化させる暴論であると厳しく批判されています。
- 効率性と合理性: 115兆円という規模の予算に対して、チェックの経費の割合は現在たったの0.01%程度しか使われていないと推定されており、これをさらに削減することが、より良いチェックにつながるとは言えない、と指摘されています。国会議員を全員解雇したところで浮く金額は500億円にも満たないのに対し、予算の監視を厳しくして10兆円を削減することの重要性が対比されています。
- 「身を切る改革」の私利私欲: 議員定数削減は、国家全体や税金削減を考えているのではなく、吉村洋文氏(維新)らの私利私欲に基づいていると断言されています。定数を削減すると、地方の議席が減少し、東京や大阪のような人口の多い都市部の議席はかえって増える傾向にあるため、これは「身を肥やす改革」であり、「売国奴」の行為であると主張されています。
結論として、菅野氏は、巨大な国家財政を適切に管理し、税金の無駄遣いをなくすためには、国民が選んだ代表(国会議員)が、身分保障を持つ優秀な官僚が作成した予算案を厳しくチェックするシステムが不可欠であると論じています。このシステムを機能させる前提として、チェックする側の人間(議員)とチェックされる側の人間(官僚)の**知性や能力(学力)**は必須であり、また、議員の地位と報酬を確保して権力バランスを保つことが、納税者の利益を守るために極めて重要であると訴えかけています。議員定数削減や給与削減を主張することは、このシステムを破壊し、結果的に役人天国を招き、納税者を裏切る行為であると強く批判しています。
「この記事が少しでも役に立った、面白かったと感じていただけたら、ぜひ下のバナーをポチッとクリックして応援をお願いします!
いただいた1クリックが、私のブログを続ける大きな励みになります😊

人気ブログランキング にほんブログ村
にほんブログ村
人気ブログランキング



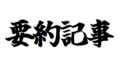
コメント