序論:乱世に問われる「天下の器」
自民・公明両党による連立政権の崩壊は、日本政治を未曾有の激動期へと突入させた。わずか一週間余りの間に、政治の風景は一変し、明日をも知れぬ不確実性が永田町を覆っている。このような先行き不透明な時代にこそ、指導者の真の資質、すなわち「天下を取る器」が問われる。それは単なる政策知識や弁舌の巧みさではない。混沌の中から秩序を生み出し、国家を導くための根源的な力が試されるのだ。
本稿は、この激動の渦中にいる政治家たちの行動を歴史的な視座から比較分析し、現代日本における「天下人」の条件を考察するものである。特に、石破茂氏、野田佳彦氏、そして過去の安倍晋三氏のキャリアに見られる共通点と、対照的な動きを見せる高市早苗氏の事例を通じて、一つの問いを立てたい。それは、天下を制する者の条件とは、必ずしも個人の才覚や周到な戦略だけでなく、むしろ「巡り合わせ」とでも言うべき運の流れを味方につける、特有の資質にあるのではないか、という問いである。
——————————————————————————–
第一章:「天下人」と幸運の巡り合わせ――石破茂氏の事例
政治の世界における成功は、しばしば緻密な戦略と意図的な行動の積み重ねの結果として語られる。しかし、歴史を紐解けば、偉大な指導者のキャリアが、予期せぬ幸運や偶然の産物によって大きく左右されてきた例は枚挙にいとまがない。意図せざる出来事が追い風となり、凡庸な一手が一躍、歴史を動かす神の一手へと昇華される。この偶然性を味方につける能力こそ、戦略と同様、あるいはそれ以上に重要な資質なのかもしれない。
この「幸運の巡り合わせ」を体現しつつあるのが、石破茂氏ではないだろうか。自公連立が崩壊し、高市早苗氏の動きが政局に大きな混乱を巻き起こしていた10月10日、まさにその裏で、石破氏は「戦後80年所管」を発表した。もし平時であれば、この所感は一つの見識を示すに過ぎず、「床屋政談」の域を出なかったかもしれない。しかし、高市氏が巻き起こした喧騒があったからこそ、石破氏の静かな発信は、まるで鏡のように対置され、政局に対する「綺麗なカウンター」として機能した。菅野氏がこの巡り合わせに畏敬の念を込めて語ったように、「高市さんがあれをやってなかったら単なるね、あの床屋政談やったんです。…偶然の産物なんですけどね、あの、いや、俺ね、ここ数日ね、天下ってすごいなと思うんです」。
この絶妙なタイミングは、石破氏自身が仕組んだものではない。まさに「偶然の産物」である。だが、こうした偶然がプラスに働くことこそ、「天下人」が持つ特有の力学なのかもしれない。
さらに、この「巡り合わせ」は、過去の不遇の時代にまで遡ることができる。安倍晋三氏が権勢を誇った時代、石破氏は党内で「冷や飯を食って」いた。自身の派閥「水月会」は「安倍の弾圧」に遭い、崩壊寸前にまで追い込まれるなど、政治家としてのキャリアは停滞しているかに見えた。しかし、その雌伏の期間に彼が手掛けてきた一つ一つの事柄が、時を経て、意図せずして現在の石破政権を構成するプラスの材料に転じている。それは「着せずして」起きた転換なのである。過去の地道な種まきが、予期せぬ形で実を結ぶ。これもまた、「天下人」だけが享受できる「巡り合わせ」の一例と言えよう。
石破氏のキャリアに見られるこの力は、決して彼一人の特異な現象ではない。他の政治家たちの軌跡にも、同様のパターンを見出すことができるのである。
——————————————————————————–
第二章:過去の伏線――失敗に見えた一手がいかに道を拓いたか
政治的決断は、その時点での合理性や勝算によって評価されがちだ。短期的に見れば失敗、あるいは不可解と断じられた一手も、時間の経過とともにその真価を現し、後の大成功への布石となることがある。一見、無関係に見えた過去の行動が、数年後、数十年後に巡り巡って好機を呼び込む。この長期的な因果の連鎖を見極めること、あるいは無意識のうちにその種を蒔いていることこそ、指導者の深慮遠謀を示す証左と言えるだろう。
この「巡り合わせ」の好例が、野田佳彦氏のキャリアに見られる。記憶に新しいのは、昨年の衆議院選挙だ。当時、立憲民主党の執行部は、八王子選挙区における萩生田光一氏の対立候補として、有田芳生氏を擁立した。この決断は党内外から「勝てるはずのない選挙」「何を考えているんだ」と激しい酷評を浴びた。戦略性の欠如を指摘する声が大勢を占めていたのである。
しかし、「結果論」として見れば、この一手は驚くべき効果を発揮した。あえて困難な選挙戦を仕掛けたことで、萩生田氏には「札付き」という強烈なイメージが付与された。そして一年後、このイメージが、公明党が自民党との連立を離脱する際の格好の「言い訳の材料」として使われることになったのだ。当時の批判を思えば、まさに想像を絶する因果関係であり、失敗に見えた一手が、政権の枠組みを揺るがす遠因となったのである。
同様の事例は、2012年の自民党総裁選で劇的な勝利を収めた安倍晋三氏にも見られる。彼が、当時まだ派閥も異なっていた菅義偉氏と強固な連携を結ぶに至った背景には、単なる政策の一致以上の、運命的な賭けがあった。総裁選で敗北すれば、安倍氏と菅氏は自民党を割り、橋下徹氏と合流して新党を結成するという密約まで交わしていたのだ。この土壇場での生死を共にする覚悟の源泉は、総裁選の数年も前に遡る。安倍氏が参加したある「教科書問題」のイベントが、菅氏との結びつきを生んだのだ。その時点では誰も想像しえなかったであろうこの小さな繋がりが、巡り巡って5年後、日本の政治を10年近く規定することになる決死のクーデターを支える信頼の礎となった。これもまた、意図せざる過去の行動が未来の成功を手繰り寄せた「巡り合わせ」に他ならない。
これらの事例が示すように、「天下人」とは、過去の行動が予期せぬ形で実を結び、幸運の歯車が回りだす人物と言えるのかもしれない。一方で、この資質を全く持ち合わせず、対照的な軌跡を辿る政治家も存在する。その典型が、高市早苗氏である。
——————————————————————————–
第三章:天下人の対極――「巡り合わせ」を持たぬ指導者、高市早苗氏
指導者に求められる資質とは何か。それは、過去の成功体験に固執せず、失敗から学ぶ能力であることは論を俟たない。しかし、それ以上に重要なのは、同じ過ちを繰り返さない一貫性と、自らの行動が周囲にどのような影響を及ぼすかを俯瞰する冷静さである。この基本的な資質を欠いた指導者は、どれほど高い能力や情熱を持っていたとしても、組織を混乱させ、支持者の信頼を失っていく運命にある。
高市早苗氏は、これまで見てきた石破氏や野田氏とは対照的に、「巡り合わせがない」人物として位置づけられるだろう。彼女の行動様式は、常に同じパターンの失敗を繰り返し、好機を潰し、周囲を疲弊させるという特徴を持つ。これは単なる不運ではない。彼女自身の行動が一貫して招いている結果なのである。
その典型的な証拠が、昨年の奈良県知事選挙を巡る一連の行動だ。その経緯は、彼女の政治手法の問題点を浮き彫りにしている。
- 性急な候補者擁立: 当時、5期目を目指すかどうかの態度を表明していなかった現職の自民党籍知事を待つことなく、「しびれを切らした」高市氏は、総務大臣時代の部下であった官僚を新たな候補者として性急に擁立した。
- 党内分裂の誘発: 事前の根回しが決定的に不足していたため、この動きは自民党奈良県連の深刻な分裂を招いた。現職側と新人側で党の票が割れるという最悪の事態に陥り、さらに現職が「へそを曲げ」てしまったことで、結果的に日本維新の会に「漁夫の利」を与える形で、自民党は知事の座を失った。
- 繰り返される失敗: それから2年。高市氏が引き起こした混乱を乗り越え、奈良の自民党はようやく一つにまとまり、維新から県政を奪還しようと結束を高めていた。まさにその瞬間に、高市氏は今度は国政の舞台で、その宿敵であるはずの維新と連立を組むという行動に出た。これは、地元の2年間にわたる努力と感情を根底から踏みにじる行為に他ならない。
この一連の行動は、「段取りの悪さ」と「間の悪さ」の典型例である。前章で論じた、過去の行動が未来の好機に繋がる「天下人」の資質とは、全く逆の特性を示している。同じ失敗を、スケールを拡大して繰り返しているのだ。
この行動様式は、もはや個人の能力やセンスの問題ではない。菅野氏が、彼女の破壊的な影響力を森友学園問題で知られる籠池諄子氏になぞらえ、「そっくりです。あらゆるものが破壊されていきます」と評したように、これは指導者としての「適性」そのものに関わる、より根源的な問題である可能性を示唆している。
——————————————————————————–
結論:野心ではなく「適性」――現代政治における天下の器
本稿では、石破茂氏、野田佳彦氏、そして安倍晋三氏のキャリアに見られる、意図せざる過去の行動が未来の好機に繋がる「巡り合わせ」の力学を分析した。一方で、高市早苗氏の行動パターンには、同じ失敗を繰り返し、好機を自ら潰してしまう「巡り合わせのなさ」が際立っていることを明らかにした。
この対比から浮かび上がるのは、現代の「天下人」に求められる資質が、我々が一般的に想像する知性や才能、戦略性といった個人の能力だけではない、という事実である。それ以上に重要なのは、過去の行動が、本人すら意図しない形で未来の幸運へと繋がっていく「徳の巡り合わせ」とも呼べる一種の「適性」ではないだろうか。それは、お笑いの世界で言う「キャラ」に近い。個人の器の大きさや小ささというより、政治という複雑な生態系の中で、プラスの連鎖を生み出すことに根本的に「向いている」かどうかの資質なのである。
政治の不確実性が極限まで高まる今、我々は指導者を選ぶ新たな基準を持つ必要があるのかもしれない。野心や弁舌の裏に隠された、その人物が持つ「巡り合わせ」の本質を見抜く眼が求められている。果たして、この乱世の日本が真に必要とするリーダーは、どのような「器」を持つ人物なのだろうか。その答えは、有権者一人ひとりの冷静な洞察に委ねられている。
人気ブログランキング


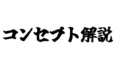

コメント