序章:25年続いた「当たり前」の終わり
最近、日本の政治を揺るがす「大事件」が起きた。それは、25年間も続いてきた自民党と公明党の協力チーム(連立政権)が、突如として解散してしまったことだ。
なぜこれが「大事件」かって? それは、これまで日本の政治を動かしてきた、いわば「最強の協力チーム」が崩壊したことで、次に誰が総理大臣になるのか、全く分からない白紙の状態が生まれたからなんだ。
普段はニュースを観ていても、なかなか見えにくい「政権が作られるプロセス」。しかし、この大事件のおかげで、その裏側がくっきりと見えてきた。まさに、日本の政治の仕組みを学ぶ、絶好の機会が訪れたんだ。
では、なぜこの強力なチームは解散してしまったのだろうか?その理由から見ていこう。
——————————————————————————–
1. なぜ?連立政権が崩壊した理由
自民党と公明党が、長年の協力関係を解消した「表向きの理由」は、「政治と金の問題」だった。 具体的には、自民党の高市総裁が、政治資金の問題が指摘されていた萩生田氏を党の重要な役職である「副幹事長」に任命したことが、公明党が離脱する直接の引き金になったとされている。
しかし、この連立解消が持つ最も重要な意味は、そこじゃない。それは、
自民党が、国会で単独では法律を通したり、総理大臣を選んだりするのに必要な「過半数」の議席を失ってしまったこと
これなんだ。これこそが、全ての混乱の始まりだった。
多数派でなくなった自民党。ここから、新しい政権を作るための、各政党による必死のチーム作りが始まる。
——————————————————————————–
2. 次の政権は誰が作る?2つの有力チーム
政治のニュースでよく聞く「過半数」。これは、国会というクラスの中で、何かを決めるときに半分以上の賛成票を集める力のことだと思ってほしい。この「過半数」がなければ、総理大臣を選ぶことも、法律を作ることもできない。
自民党が過半数を失った今、新しい「過半数チーム」を作ろうとする動きが活発化している。現在、有力視されているのは次の2つのチームだ。
| チーム名(仮) | 参加メンバー | 特徴 |
| 自民・維新チーム | 自民党、日本維新の会 | あと一歩で天下!過半数まであと2議席という、まさにギリギリの状態。 |
| 野党連合チーム | 立憲民主党、公明党、国民民主党 | こちらも過半数を取れるかどうか、瀬戸際での激しい交渉が続いている。 |
この表を見ると分かる通り、どちらのチームも「過半数」を確保できるかは微妙なライン。 そして、この状況でカギを握っているのが「日本維新の会」だ。彼らがどちらのチームに参加するかによって、次の政権が決まる。まさに「キングメーカー」ともいえる、非常に重要な立場にいるんだ。
こういう政党同士の駆け引きは「数合わせ」と批判されることもある。でも実は、これこそが議会制民主主義の重要なルールなんだ。
——————————————————————————–
3. 「数合わせ」こそが民主主義の仕事
政治家たちが過半数を作るために交渉する「多数派工作(数合わせ)」。これは決して悪いことじゃない。むしろ、日本が採用している**「議員内閣制」という政治システムの、根本的なルール**に基づいた正しい行動なんだ。
昔の日本の政治には「憲制の常道」という考え方があった。これは、「選挙で与党が過半数を失った場合、それは国民の意思が『今の政権では嫌だ』と示されたことを意味する」というものだ。
この考え方に従うなら、選挙で過半数を失った今、政治家たちがやるべき最も重要な仕事は一つしかない。それは、国民の意思に従い、これまでとは違う新しい政権のチームを作ろうと必死に努力すること。今起きている各政党の動きは、まさにそのプロセスそのものなんだ。
理論は分かったけど、実際の政治はもっと複雑だ。ある地方の出来事が、国全体の政治にどう影響したのか、具体的な事例を見てみよう。
——————————————————————————–
4. 具体例:奈良の知事選挙が国政に与えた影響
現在、国のトップである総裁として、自民党の高市氏が日本維新の会との連携協議を進めている。しかし、この連携には大きなドラマと皮肉が隠されている。その鍵は、政治家が持つ「巡り合わせ」という不思議な力だ。
天下を取る政治家、つまり「天下人」と呼ばれる人には、この「巡り合わせ」があると言われる。昔、何気なく蒔いた種が、全く関係ないところで芽を出し、何年も経ってから自分を助けてくれるような幸運のことだ。逆に、この「巡り合わせ」がない政治家は、いつも間が悪く、やることなすこと裏目に出てしまう。
高市総裁にこの「巡り合わせ」があるのかどうか。それを象徴する出来事が、昨年の「奈良県知事選挙」だった。
一体何があったのか、物語形式で見ていこう。
- 高市氏の独断 高市氏は、現職の知事とは別に、自分の側近である官僚を新しい知事候補として強引に立てた。根回しが不十分だったため、一枚岩だった奈良県の自民党は真っ二つに分裂してしまった。
- 維新の「漁夫の利」 自民党の支持者の票が2人の候補者に割れてしまった。その結果、ライバルである日本維新の会の候補が「漁夫の利」を得る形で選挙に勝利し、奈良県知事の座をかっさらっていったんだ。
- 現在の皮肉と裏切り 想像してみてほしい。奈良の自民党員たちは、維新に知事の座を奪われ、2年間も悔しい思いをしてきた。「いつか維新から県政を取り戻そう!」と、ようやく団結しかけた、まさにその瞬間だ。国のトップである高市総裁が、その憎き維新と手を組むと発表した。これは単に「複雑な思い」じゃない。地元で戦う仲間からすれば、政治的な裏切りに等しい。
この事例から学べる教訓は、「政治は国会の中だけで動いているのではなく、地方での一つの出来事や人間関係が、国全体の政権の形を左右することもある」ということ。そして、どんなに権力があっても、「巡り合わせ」のない政治家の行動は、周りを混乱させ、思わぬ結果を招いてしまうということだ。
最後に、ここまでの話をまとめて、私たちがこのニュースから何を学べるのかを確認しよう。
——————————————————————————–
結論:政治ニュースは「公民」の生きた教材
今回の一連の出来事から、私たちは日本の政治について、大切な3つのことを学ぶことができる。
- 政権はチーム作り 総理大臣を選ぶには、国会で「過半数」という多数派のチームを作ることが不可欠である。
- 選挙結果がスタートライン 選挙で与党が過半数を失うと、国民の意思を反映して新しい政権を作るための「多数派工作」が始まる。これは議会制民主主義の正常なプロセスである。
- 政治は複雑な人間ドラマ 国のトップを決める大きな動きも、奈良の例のように、地方での出来事や、政治家が持つ「巡り合わせ」といった人間的な要素が複雑に絡み合って生まれる。
今の政治の混乱は、一見すると分かりにくいかもしれない。しかし、視点を変えれば、日本の政治がどのように動いているのかをリアルタイムで学べる、またとない「生きた教材」だ。ぜひこの機会に、政治ニュースの面白さに触れてみてほしい。
人気ブログランキング

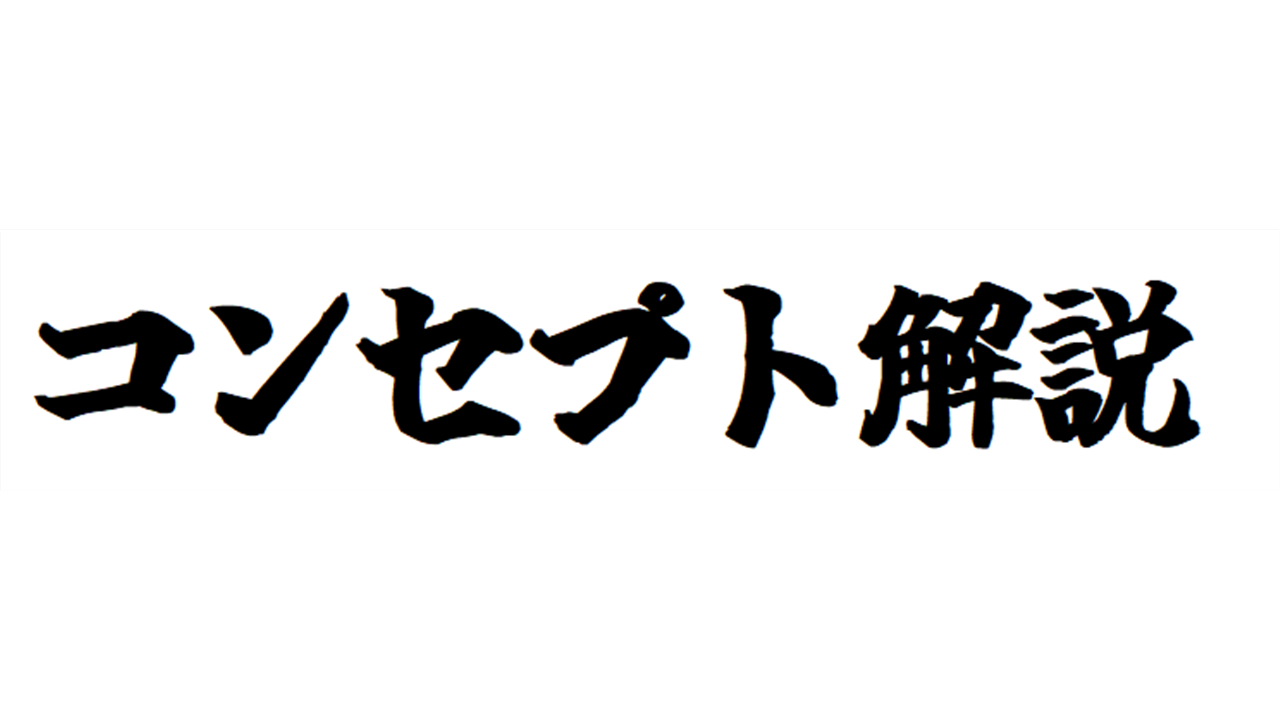
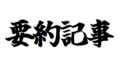

コメント