導入:女性リーダーへのフェミニズムからの批判、その「なぜ?」
女性初の総理大臣を目指す政治家、高市早苗氏。彼女の存在は、一見すると女性の社会進出の象徴であり、祝福されるべき出来事のように思えます。しかし、フェミニズムの視座からは、歓迎とは程遠い、厳しい批判の声が上がっています。
高市早苗という「初の女性総理」候補は、フェミニズムにとって祝福か、それとも最大の脅威か?
この一見、矛盾しているように見える問いは、現代社会が抱えるジェンダーの問題を深く理解するための鍵を握っています。この文書は、この問いを解き明かすことを通じて、「フェミニズム」や「家父長制」といった、少し難しく聞こえるかもしれない重要な概念の基本を学ぶためのガイドです。
1. よくある誤解を解く:フェミニズムの本当の目的
「フェミニズム」と聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。まず、フェミニズムが何を目指していないのかを明確にすることから始めましょう。
- フェミニズムが目指していないこと
- 単に女性の社会進出を応援する思想ではありません。
- 女性に優しくしたり、大切に扱ったりすることそのものでもありません。
では、フェミニズムが真に目指していることは何でしょうか。それは、社会構造そのものの変革です。
平易な言葉で言えば、フェミニズムとは、女性を「女性だから」という理由で特定の役割に固定化し、その可能性を狭めている社会の仕組み、考え方、慣習を根本から破壊しようとする思想です。
重要なのは、個人の生物学的な性別(女性か男性か)ではありません。フェミニズムの視点は常に、個人を縛り付けている社会の構造そのものに向けられているのです。
2. 「家父長制」とは何か?
フェミニズムが闘う相手、すなわち女性を社会的に抑圧する構造的暴力の正体こそが「家父長制」です。
これは単に「父親が偉い家族制度」といった単純な意味ではありません。社会学者の上野千鶴子氏は、名著『家父長制と資本制』の中で、このシステムを**「女性の労働力を『女性である』という属性だけで安く買い叩く資本主義の共犯関係にあるシステム」**として鋭く分析しました。つまり、社会全体に根ざした、性別による不平等な力関係の構造なのです。
この家父長制的な思考パターンは、私たちの身近な人間関係にも現れます。臨床心理士の信田さよ子氏は、高市氏が公明党との連立解消に際して見せた反応について、非常に示唆的な指摘をしています。
公明党との連立解消に対する高市氏の反応(「突然言い出された」「もっと話し合えば分かってもらえるはず」「一方的に離別宣言された」「直接会って話せば分かり合える」など)が、DV被害者の妻から別居を切り出された夫の反応と酷似していること。
このアナロジーが浮き彫りにするのは、相手を対等なパートナーとして尊重するのではなく、自分のコントロール下に置くべき存在と見なす思考です。これは、自分の意に沿わない相手の意思決定を受け入れられない、典型的な家父長制的思考の現れと言えるでしょう。
3. 事例分析:なぜ高市氏はフェミニズムの視点から批判されるのか
ここまで見てきた「フェミニズム」と「家父長制」の基本的な考え方を踏まえると、最初の問いの答えが見えてきます。
高市氏がフェミニズムの観点から批判される核心的な理由は、彼女が家父長制という古い仕組みを破壊するのではなく、むしろその仕組みを温存し、強化する側に立っているからです。
| 観点 | 高市氏の政治姿勢 | フェミニズムの視点 |
| 社会構造 | 旧来の家父長制的な価値観や制度を維持・強化しようとする。 | 女性を固定化するあらゆる構造(家父長制)を破壊することを目指す。 |
| 評価基準 | 生物学的な性別が「女性」であること。 | 政治的な姿勢や政策が、社会構造の変革に資するかどうか。 |
つまり、高市氏の政治姿勢は、彼女自身の生物学的な性別が何であるかに関わらず、フェミニズムが乗り越えようとしている構造そのものを守ろうとするものであるため、フェミニズムの立場からは「敵」と見なされるのです。
この問題を、「彼女は女性の心を持たない名誉男性だ」といった安易な言葉で片付けてはいけません。重要なのは、個人の内面を憶測することではなく、あくまで社会構造と個人の政治的態度の関係性から問題を捉える視点です。
4. 批判の作法:リベラル派が陥りがちな「間違った」批判
高市氏の政策や政治姿勢を批判することは重要ですが、その方法を間違えると、全く逆効果になってしまいます。特に、リベラルを自認する人々が陥りがちな、絶対にしてはならない批判があります。
- ジェンダーに基づいた個人攻撃
- 「あの女は」といった、女性であることを揶揄するような言葉遣い。
- 容姿について言及し、人格と結びつけること。
これらの批判は、一見すると高市氏個人に向けられているように見えますが、その根底には**「女性はこうあるべきだ」という差別的な視点(ミソジニー)**が潜んでいます。このような批判は、結局のところ家父長制的な価値観を再生産するだけであり、フェミニズムの理念とは全く相容れません。
私たちが真に批判するべき対象は、以下の点です。
- 政策の内容:彼女が推進しようとしている具体的な政策が社会に何をもたらすのか。
- 政治的姿勢:彼女が守ろうとしている旧来の社会システムそのもの。
個人の女性性を攻撃するのではなく、その人物が代表するシステムと政策を冷静に分析し、批判することこそが、建設的な議論への第一歩となります。
結論:なぜ今、この視点が重要なのか
現在、高市氏を支持する自民党や日本維新の会などによる政権は、歴史の時計の針を巻き戻そうとする「反動政権」となる可能性があります。このような時代において、対抗する側が掲げるべき旗は、シンプルに**「平和と人権」**です。
そして、その「平和と人権」の旗を正しく、力強く掲げるためには、まず私たち自身の内にある女性差別的な考え方や無意識の偏見を自己批判し、フェミニズムへの理解を深めることが不可欠です。
約40年前に放送されたテレビドラマ『阿修羅のごとく』の脚本が、2025年の現代において、ほぼ一言一句変えずにリメイクされ、通用してしまうという事実は、私たちの社会の進歩に対する痛烈な告発です。それは、フェミニズムが指摘する家父長制的構造を意識的に解体する努力なしには、数十年が経過しても女性を取り巻く環境に本質的な変化は訪れない、という厳しい現実を突きつけています。
したがって、私たちの課題は、高市氏のような個人を批判することに留まりません。彼女が守ろうとしている、半世紀近くも停滞したままの社会システムそのものを見抜き、それに挑戦することです。今、この視点を学ぶことこそが、より公正で平等な社会への道を切り拓くために、私たち一人ひとりに求められているのです。
人気ブログランキング

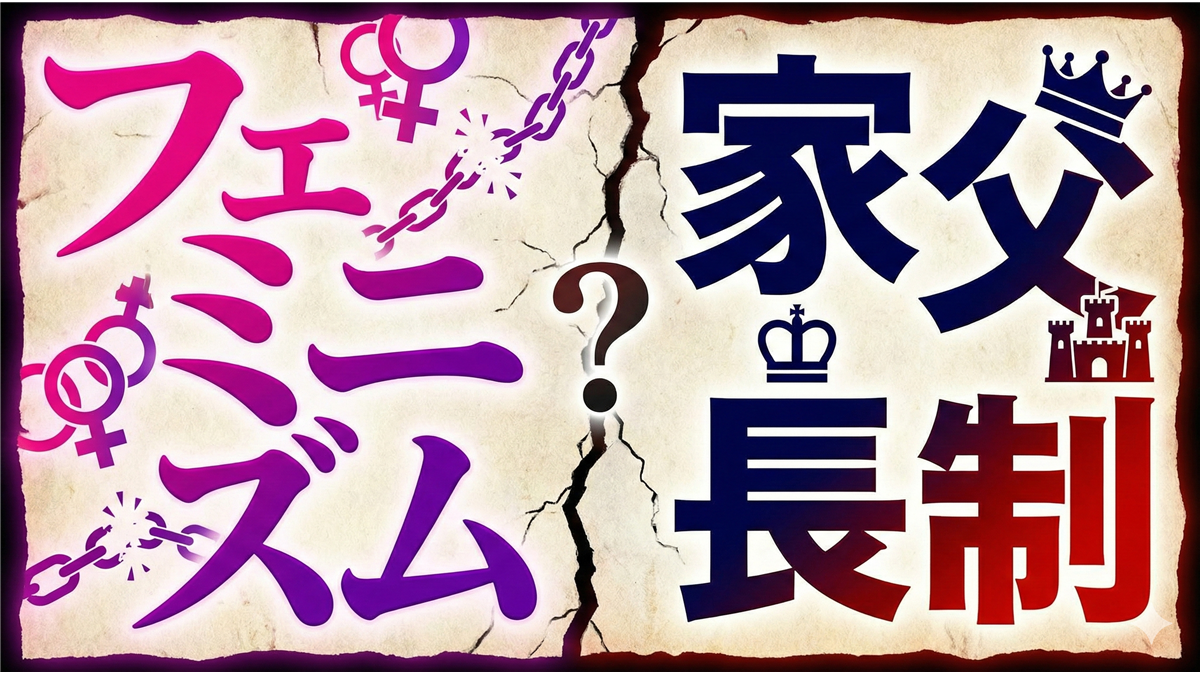


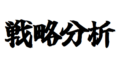
コメント