はじめに: 常識の罠
「日本の政治家は多すぎる」「数を減らせば税金の無駄遣いがなくなる」――これは、多くの人が疑いなく信じている「常識」です。議員定数の削減は、政治家が自ら「身を切る」健全な改革であり、国民のためになる、と。しかし、もしこの一見すると正論に聞こえる考えが、単なる間違いであるだけでなく、日本の民主主義そのものと、私たち自身の利益を静かに蝕む毒だとしたら、どうでしょうか。
この耳障りの良いスローガンは、実は巧妙に仕組まれた罠かもしれません。本記事では、「国会議員の数を減らせ」という大衆迎合的な主張の裏に隠された、驚くべき5つの不都合な真実を、徹底的な分析に基づいて一つずつ解き明かしていきます。
——————————————————————————–
1. 「身を切る改革」の正体は、地方を切り捨て都会が潤う仕組み
「議員定数削減」は、政治家が自らの待遇を削る「身を切る改革」という美名のもとに語られます。しかし、その実態は、都会に強固な地盤を持つ政党が、自らの政治的影響力を最大化するための、極めて自己中心的な政策に他なりません。
国会全体の議席数が削減されると、そのしわ寄せは人口の少ない地方の選挙区に不均衡に集中します。これは単なる推測ではありません。日経新聞が報じた図表が示すように、過去の定数削減では、人口の多い東京都(10議席→12議席)、兵庫県(4議席→6議席)、福岡県(4議席→6議席)といった都市部で議席が増える一方、徳島県と高知県、鳥取県と島根県といった地方の県は、2つの県を1つの選挙区にまとめる「合区」を強いられ、有権者の声は実質的に半減させられました。
この政策がもたらすのは、地方の声を政治の中心から排除し、権力を都市部に一極集中させるという歪な構造です。これは決して政治家全体の「身を切る改革」などではなく、地方の身を切り刻み、自分たちの身を肥やすための策略なのです。
身をきる改革ではなくて身をこやす改革です。
2. 115兆円の予算を監視するには、国会議員は「少なすぎる」
国会議員の最も重要な職務は、国民から集めた税金が正しく使われているかを監視することです。日本の一般会計予算は約115兆円。この途方もない金額の規模を、私たちは具体的に想像できるでしょうか。
もし115兆円を1万円札で積み上げると、その高さは約1,000kmに達します。これは、国際宇宙ステーション(ISS)が周回する高度400〜500kmの実に2倍以上という、成層圏をはるかに突き抜ける高さです。横に並べれば、東京から種子島までの約1,000kmに匹敵します。
国会議員は、この天文学的な金額をチェックする「国民の監査役」です。しかし、衆参合わせて約700人の議員のうち、半分近くは自分たちの政府を厳しく追及しないであろう与党議員。つまり、実質的な監視の目は、野党議員を中心とした約350人に限られます。この人数で、東京から種子島まで並ぶ1万円札の束を隅々までチェックできるでしょうか。「監査役の数を減らせば、より良いチェックができる」という理屈は、どう考えても破綻しています。税金の無駄遣いを本気でなくしたいのであれば、監査役は多ければ多いほど良い、それは自明の理です。
350人で東京から種子島までの1万円札をチェックするシステムと600人でチェックするシステムやったら600人でチェックするシステムの方がええに決まってるじゃないですか。
3. 国会議員の「高給」は幻想?先進国で唯一「給与」がない日本の実態
「国会議員は高給取りだ」という批判は根強いですが、この通説は日本の特殊な制度への無理解から生じる完全な誤解です。
日本の国会議員が受け取っているのは「給与(Salary)」ではなく、「歳費(Legislative Expenses)」です。これは個人の手当というより、事務所の賃料、複数の秘書の人件費、その他すべての政治活動費を賄うための「事業収入」であり、議員は個人事業主のような立場に置かれます。ここから諸経費を差し引いた議員個人の実質的な手取りは、年間400万円程度に過ぎないという指摘もあります。さらに、彼らは手厚い厚生年金ではなく、基礎的な国民年金にしか加入していません。
この状況は、他の先進国と比較して異常です。例えばアメリカでは、国会議員一人あたり、国の経費で年収2000万円クラスの高度な専門知識を持つスタッフを約15人も雇用できます。彼らは官僚になりうるほど有能な人材であり、議員の政策立案能力を支えています。日本の政治家がいかに脆弱なリソースで戦っているかは火を見るより明らかです。
ちなみに先進国で日本だけ国会議員に給与を払ってません。
4. 官僚 vs 政治家、本当に強いのはどちらか?
この慢性的なリソース不足は、単に政治家個人の困難にとどまらず、国家の恒久的な権力である官僚機構に対するチェック機能そのものを、構造的に麻痺させるのです。
国家の運営を担うキャリア官僚は、一度採用されれば定年まで身分が保障されています。この絶対的な安定性が、官僚組織の強固な権力の源泉です。対照的に、政治家は常に次の選挙で落選するリスクに晒される、極めて不安定な立場にあります。
国民の代理人である政治家が、この強大な官僚機構と対等に渡り合い、彼らが「嘘をついていないか」を厳しく検証し、予算に対して「対治」するためには、最低でも対等な土俵に立つ必要があります。しかし、議員の数や歳費を削減し、政治家を弱体化させることは、官僚機構の力を一方的に強め、民主主義の根幹であるチェック機能を完全に形骸化させることに直結します。
身分保障のある役人と身分保障のない議員が予算の話をする時にどっちの給料が高い方が健全よ。
5. 「議員を減らせ」と叫ぶ人の心理にある「嫉妬」という感情
これほど多くの欠陥を抱えながら、なぜ「議員を減らせ」という主張が熱狂的に支持されるのでしょうか。その根底にあるのは、合理的な政策判断ではなく、より原始的な感情、すなわち「嫉妬」です。
これは、自分の給料が上がることよりも、他人の給料が下がることの方に喜びを見出してしまう「田舎根性」とも呼べる心理です。資本主義社会では、高い能力には高い報酬を支払うのが原則ですが、この主張の根底にあるのは「覚悟」や「根性」といった精神論で物事を解決しようとする、前近代的な思考です。政治家を特権階級とみなし、その地位や待遇を引きずり下ろすことに快感を覚える。それは、より良い統治を目指す建設的な政治参加ではなく、単なる破壊的衝動に過ぎないのです。
——————————————————————————–
結論: 常識の “再評価”
見てきたように、「議員を減らせば国が良くなる」という「常識」は、地方を切り捨て、行政監視機能を弱め、官僚支配を強めるという、極めて欺瞞に満ちたプロパガンダです。シンプルなスローガンは常に魅力的ですが、その裏に隠された複雑なパワーゲームを見抜く知性こそ、今求められています。
最後に、自らに問いかけてみましょう。「議員を減らせ」というシンプルなスローガンを耳にした時、私たちが本当に求めているのは、より健全な政治なのでしょうか?それとも、知らず知らずのうちに、民主主義という私たち自身の監視塔を、自らの手で解体しているのでしょうか?
人気ブログランキング


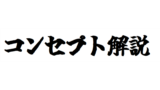

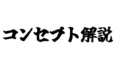
コメント