政治家の不可解な言動や、かつての協力者を切り捨てるような「裏切り」。私たちはそれを、冷徹な計算や権力闘争の駆け引きの結果だと考えがちです。しかし、もしそれらの行動が、私たちの想像をはるかに超えた、奇妙で無意識的な心理的防衛メカニズムの産物だとしたらどうでしょうか?
この記事では、兵庫県の斎藤元彦知事の言動をケーススタディとして、政治家が極度のストレス下で見せる驚くべき心の働きを分析します。これは単なる政治批判ではありません。一人の人間の内面で起こっているかもしれない、驚くべき「自己防衛」の物語です。
——————————————————————————–
1. 「裏切り」ではなく「記憶の消去」? 都合の悪い事実を”本気で”忘れる自己防衛メカニズム
斎藤知事の行動を分析する上で最も衝撃的な仮説は、彼の「裏切り」が決して計算されたものではなく、自己防衛のために都合の悪い記憶を”本気で”消去してしまう「解離性健忘」に近い心理状態から生じているのではないか、という点です。
自分にとって不都合な真実や、かつて近しかった協力者の存在を突きつけられた瞬間、彼の心は自分を守るために、その記憶そのものを消し去ってしまう。これは意図的な嘘ではなく、文字通り「なかったこと」にしてしまう無意識のメカニズムだと考えられます。
このパターンは一度や二度ではありません。万博を巡る発言で暗に突き放した吉村洋文大阪府知事をはじめ、立花孝志氏、YouTuberのふくまろ(氏、中島ゆみ子氏、新田哲史氏など、これまで彼が「売り渡した」とされる人物は枚挙にいとまがありません。しかし、本人の認識の中では、彼らは本当に「知らない人」になっている可能性があるのです。
この人ね 嘘ついてるんじゃないと思ったの。この人ね ほんまやね ほんまにそう思てんねん。この人のの中では ほんまにほんまに知らん人になってんねん。
私たちが「裏切り」と見る行為が、本人にとっては自己の精神を守るための必死の防衛行動であり、その過程で本当に記憶が抜け落ちている——にわかには信じがたいですが、この可能性を念頭に置くことで、彼の不可解な言動の数々が、恐ろしい一貫性をもって見えてくるのです。
2. 裏切りのサインは「声量アップ」。人を売り渡した瞬間に楽になる心理
心理的な仮説を立てたところで、次はその仮説を裏付ける、観察可能な物理的証拠に目を向けてみましょう。この無意識の「記憶の消去」が作動した瞬間を捉える、具体的な兆候があります。それは「声のボリュームが上がること」です。
困難な質問をかわしたり、かつての協力者を突き放すような発言をした直後、知事の声量は目に見えて大きくなる傾向が見られます。具体的には、以下の2つの事例が挙げられます。
- 万博の成果を問われた際 兵庫パビリオンの成果について問われた際、彼は「万博そのものも数値目標を達成できていない」と問題をすり替えました。この責任転嫁の発言の後、彼の声のボリュームは明らかに上がっています。
- YouTuberのふくまろ氏について問われた際 ふくまろ氏を知っているかと問われ、知らないと答えた際、2回目の否定の言葉は1回目よりも明らかに声量が大きくなっていました。
この現象は、心理的な分析では次のように説明されます。「人売り飛ばして我が楽になったから腹から声出るようになってんねん」。つまり、不都合な存在や事実を精神的に切り離すことでストレスから解放され、安堵感から声が大きくなるというのです。これは、彼の言動が計算されたポーズではなく、その場その場でのストレス反応と解放のサイクルによって突き動かされていることを強く示唆しています。
——————————————————————————–
3. なぜ、あの一言を? 関西中が「万博大成功」ムードの直後に放った禁句の背景
知事の政治的センスを疑わせる象徴的な出来事が、万博に関する発言でした。この一件は、彼の心理が長期的戦略よりもいかに「その場の心地よさ」を優先するかを如実に示しています。
まず、あの記者会見が行われた時の関西の空気を理解しなければなりません。「関西のテレビ見てみや この土、日、月、の万博フィナーレ万歳万博万博万博ってずっと朝から万博万博万博万博言うて開けて火曜日の記者会見やで」。まさにメディアは「万博大成功」の祝祭ムード一色。そんな雰囲気の中で、斎藤知事は記者から成果を問われ、「万博そのものも数値目標達成できてない」と発言したのです。これは、関西全体の雰囲気に冷や水を浴びせる、政治的に極めて配慮を欠いた「禁句」でした。
なぜ彼は、こんな「アホの子」のような対応しかできなかったのでしょうか。それは、長期的な政治的計算よりも、その瞬間のストレスから逃れることを最優先する心理が働いた結果だと分析されています。目の前の「兵庫パビリオンの成果」という厳しい問いから逃れるため、より大きな主語である「万博全体」を盾にしたのです。
普通の政治家、いや普通の「大人」であれば、いくらでもやりようはありました。
皆さんおっしゃる通りで定量的的な評価ってのはせなあかんと思うんやけど、ちょっとね、定量的な評価にまだちょっと追いついてないんですよ。もう終わったばっかりなんでね、ちょっと待って…お祭りでも鉢払いが終わった後会計しめるでしょと。鉢払いも終わってないとこなんでもうちょっと待ってくださいねって言うたしまいのはだけの話ですよ。
あるいは、もっとシンプルに「大きなミスもなく無事終わったことをまず喜びましょうよ」とでも言えば済んだ話です。この対比から浮かび上がるのは、政治的展望よりも、その場しのぎの自己防衛を優先せざるを得ない、極度に追い詰められた精神状態です。
——————————————————————————–
4. 著作権は誰のもの? SNSをめぐる自己矛盾で思考停止に陥る瞬間
この心理的メカニズムと物理的な兆候が、最も鮮明な形で一つの事象に凝縮されたのが、自身のX(旧Twitter)アカウントをめぐる質疑応答でした。ここでは、論理的な矛盾を突きつけられた彼の思考が崩壊していく過程が、手に取るように観察されます。
- リスク評価: まず「Xアカウントの著作権は誰に帰属するか」と問われた知事は、非常にゆっくりと話し始めます。これは、この質問が自分に有利か不利か、ダメージがあるものかの判断がつかず、リスクを慎重に評価しようとしていたからです。彼は「私に帰属する」と回答します。
- 矛盾の罠: 菅野氏はすかさず「では、県職員がその『個人』のアカウントのために写真を撮影した場合、公的リソースの私的流用では?」と追及。ここで知事は罠にはまります。彼は守りに入り、写真は「県のPRのため」だと主張。これは「著作権は個人にある」という最初の発言と完全に矛盾します。
- 解離のスイッチ: この矛盾点を真正面から突かれた瞬間、彼の思考は限界を迎えます。観察によれば、この時、彼の瞳孔が開き、論理的思考が完全に停止。彼は「全く問題ない」という言葉を壊れたレコードのように繰り返すばかりになります。
- 思考停止と責任放棄: 最終的に、自分自身のアカウントのことであるにもかかわらず「県の方に聞いていただければと思います」と、意味不明な責任転嫁で応答を打ち切ります。「なんで斎藤元彦のアカウントについて県に聞かなあかんの?自分のもんや言うてんのに」——この呆れた問いがすべてを物語っています。
この一連の流れは、単なる質疑応答の下手さではありません。論理的な圧力に耐えきれなくなった精神が、自己防衛のために「シャットダウン」する——まさに解離のスイッチが入った瞬間を捉えた、生々しい記録なのです。
——————————————————————————–
結論
斎藤知事の一連の言動は、単なる一個人の資質の問題として片付けるべきではないでしょう。これは、極度の政治的プレッシャーに晒された人間の精神が、いかにして自己を守ろうとするのかを示す、恐ろしくも興味深いケーススタディです。
記憶の消去、声量の変化、瞳孔の開き、そして論理の破綻。これらはすべて、意識的な策略ではなく、無意識の領域で必死に自己を保とうとする防衛本能の表れなのかもしれません。
私たちがリーダーを観察するとき、常に見ているのは計算された戦略なのでしょうか。それとも時として、窮地に立たされた精神の、生々しく無意識な働きを目の当たりにしているだけなのでしょうか。
人気ブログランキング


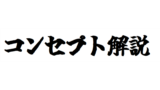
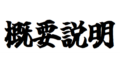

コメント