最近の政局をめぐるニュースの嵐に、辟易している人も少なくないだろう。連日メディアは誰が誰と組み、誰が誰を裏切ったかという話を大々的に報じている。しかし、その喧騒のなかで、私たちは何か大切なことを見失ってはいないだろうか。まるでタレントの熱愛報道でも見るかのように、政治が個人の人間関係の物語へと矮小化されていく。有権者が選挙で突きつけたはずの「本質的な問題」は、いつの間にか誰も語らなくなる。
この状況に、ある種の不満や違和感を抱えているのは、きっと私だけではないはずだ。なぜ政治報道はここまで浅薄になってしまったのか。その裏側で、本当に何が起きているのか。先日、この一連の騒動を深く掘り下げてみたところ、日本の政治とメディアの現状を浮き彫りにする、4つの驚くべき、あるいは皮肉な発見があった。この日曜日に考えたことを、ここに記録しておきたい。
1. なぜ政治ニュースは「誰と誰がラブホテルに行ったか」という話に成り下がるのか
今回の政局を象徴する共同通信の一本の見出しがある。「玉木氏、高市総裁と協力も 政策進めるため」というものだ。一見、普通の政治ニュースに見えるかもしれない。しかし、問題はここにある。なぜ「国民民主党が自民党と連携」ではなく、「玉木氏が高市総裁と」というように、すべて個人名で語られるのか。
これは、複雑な政策や党の方針をめぐる議論が、完全に個人の人間関係の物語にすり替えられていることを示している。メディアは「有権者はお前らだ。どうせ芸能ゴシップのような話が好きなんだろう」と、我々の知性を完全に見下している。政策の中身や手続きの正当性といった本来問われるべき論点は脇に置かれ、ただ誰と誰がくっつくか、離れるかという話だけが消費されていく。この現状に、あなたは苛立ちを覚えないだろうか。
これゴシップ記事でしょ これやってることは誰と誰がラブホテル行ったかって言うてる話と一緒やで これ
この報道スタイルは、政治家個人を目立たせたいという思惑と、有権者をゴシップ好きの観客と見なすメディアの姿勢が結びついた、極めて不健全な現象と言えるだろう。
2. 最も「民主的」な手続きを踏んでいるのは、皮肉にも共産党だった
驚くべきことに、今回の政局の渦中にあった自民党や日本維新の会といった政党は、連立交渉のような極めて重要な判断を、厳密な意味での党内手続きを経ずにトップダウンで進めていた。高市氏や吉村氏が下した判断は、党全体の意思を正式に反映したものとは言い難い。
その一方で、皮肉なことに、最も民主的な手続きを丁寧に踏んでいたのは、普段「民主集中制」という言葉で批判されがちな日本共産党だった。共産党、公明党、立憲民主党、社民党は、それぞれ党内できちんとした議論と意思決定のプロセスを踏んでいたのだ。特に公明党は全国の地方議員の意見を聞くために代表者を集めたり、Zoom会議を開いたりするほどの徹底ぶりで、共産党も代々木に党員を集めて議論を尽くしていた。
共産党の方が民主集中制でない自民党や国民民主党よりも民主的な理由にちゃんと代々木に集まって話してますからね みんなね
この事実は、政党のイメージやレッテルがいかに当てにならないかを示している。ガバナンスが問われるべきは、むしろ手続きを軽視した与党の方ではないだろうか。しかし、こうした手続き論以前に、政治家たちが無視している、より根本的な問題がある。それは、有権者が選挙で突きつけたはずの審判そのものだ。
3. 有権者が突きつけた「裏金問題」から、なぜか誰もが目をそらす
自民党が衆参両院で過半数を割り込んだ。この結果が何を意味するかは明らかだ。有権者が突きつけた答えは、シンプルに「裏金問題は許さない」というものだった。これこそが、今回の政局の出発点であったはずだ。
議席という形で出た答え なぜ自民党が少数与党になったかっていう理由 バーンって引いてマスで見た時の出た答えというのは裏金いらんという答えやんか
しかし、その後の権力闘争において、この選挙結果という民意からほとんどの政治家が目をそらし続けた。維新の吉村氏も、国民民主の玉木氏も、交渉の条件として裏金問題の解決を挙げることはなかった。「裏金問題が解決しない限り動かない」という姿勢を最も強く見せたのは公明党だったが、立憲民主党の安住氏が記者会見でポロッと口にした程度で、政局の中心議題となることはついになかった。
選挙で示された民意と、永田町で繰り広げられる権力ゲームの優先順位との間には、絶望的なほどの乖離がある。有権者の審判は、いとも簡単に忘れ去られてしまうのだ。
4. あなたの政治的スタンスは『アニー・ホール』でわかる?ダイアン・キートンが遺した価値観
最後に、一見政治とは無関係に思える、しかし本質的な価値観を問う発見があった。ある女優の訃報に触れたと勘違いしたことから、ふと彼女の文化的な重要性についての思索が始まった。その女優とは、ダイアン・キートンである。
彼女は、それまでの映画界が描いてきた女性像を根底から覆した存在だった。マリリン・モンローのような、美しく男性社会に媚びる「お人形さん」がいた。次に、オードリー・ヘプバーンが『ティファニーで朝食を』で自立しようと試みたが、社会の枠組みの中で見事に「失敗」し、そのキャリアを失速させた。しかしダイアン・キートンは違った。彼女はウディ・アレンの映画『アニー・ホール』などを通じて、初めて「独立した意志を持つ女性」という新しいアイコンを確立し、成功させたのだ。
ダイアン・キートンとウディ・アレンが作り上げたその世界観こそが、70年代以降の西側先進国の倫理観のベースになったと言っても過言ではない。彼女は、ある世代にとっての「世界の恋人」であり、その存在は私たちの社会のあり方を規定している。そして、ここに一つの大胆なリトマス試験紙を提示したい。映画『アニー・ホール』をどう感じるかが、その人の政治的スタンスを測る一つの指標になるのではないか、という仮説だ。
アニホール見て何とも思わんやつは多分賛成党に投票するよ
この映画が描く自立した個人や、カラッとした人間関係のあり方に共感できるか否か。それは、私たちがどのような社会を望み、どのような価値観を大切にしているのかを、鋭く映し出す鏡となるのかもしれない。
結論: 最後の考察
政治はゴシップとして消費され、選挙で示された民意は無視される。その底流にあるのは、個人が確立しておらず、手続きや本質を軽んじる、前時代的な価値観ではないか。その対極にあるのが、『アニー・ホール』が提示した、自立した個人のリアリズムと、見せかけを嫌う知性だ。
私たちが政治やメディアに求めるべきは、ゴシップ以上の「本質」であることは言うまでもない。そして、その「本質」を見抜くために、私たちは『アニー・ホール』が体現したような、自分自身の価値観をどれだけ大切にできているだろうか。ある日曜日の午後に考えたこれらのことは、その答えを探すための、ささやかな出発点に過ぎない。
人気ブログランキング



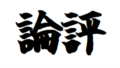
コメント