序章:一つの時代の終焉、一つの肖像の想起
ダイアン・キートンの訃報に接したとき、単に一人の偉大な女優がこの世を去ったという以上の、深い喪失感を覚えた。それは、ある種の時代の終わりを告げる鐘の音のようだった。彼女は、私たちの世代にとって、単なる映画スターではなかった。マリリン・モンローやオードリー・ヘプバーンといった先行するアイコンたちとは一線を画す、新しい女性像の象徴だったからだ。彼女は、いわば「世界の恋人」であり、その肖像は「自立した女性」という理想そのものであった。
モンローやグレース・ケリーが体現したのが、男性社会の価値観の中でその美しさを輝かせる、いわば「男の世界に媚びる」女性像であったとすれば、キートンは全く異なっていた。彼女は、男の世界の論理に迎合することなく、自身の足で立ち、自身の言葉で語る、自律した存在としての女性をスクリーンに焼き付けた。本稿は、ダイアン・キートンという文化的アイコンの不在を起点とし、彼女が体現した価値観の光に照らし出すことで、現代日本社会、とりわけその政治の風景に深く根ざす問題を考察する試みである。
——————————————————————————–
1. 『アニー・ホール』革命:家父長制の外に立つ女性像の誕生
ダイアン・キートンが映画史、ひいては現代文化に与えた影響は計り知れない。彼女がウディ・アレンとの一連の作品で確立した新しい女性像は、単なるキャラクター造形に留まらず、西側先進国の倫理観の基盤を形成するほどのインパクトを持っていた。それは、一つの文化的な革命であったと言っても過言ではない。
この革命の意義を理解するためには、彼女以前の女性像と比較するのが最も有効だろう。
マリリン・モンローやグレース・ケリーは、その圧倒的な美貌をもって男性社会を魅了する存在だった。その魅力は、あくまで伝統的な女性性の枠組みの中にあり、「美しく、男の世界に媚びる」という役割を引き受けることで成立していた。一方、オードリー・ヘプバーンが『ティファニーで朝食を』で見せた自由奔放な姿は、確かに新しい女性像への萌芽を感じさせるものだったが、それは「60年代の精一杯」の試みであり、時代に対してあまりにも早すぎた。当時のアメリカ社会は、まだ女性に「お人形さん」であることを求めていたのだ。
こうした流れの中に登場したのが、ダイアン・キートンだった。『ゴッドファーザー』でマフィアという究極の家父長制(パトリアーキー)の世界に懐疑的な眼差しを向ける役柄を演じ、そして決定的な一作『アニー・ホール』を通じて、彼女は「独立した女性」というアーキタイプを完全に確立した。彼女が演じた女性たちは、家族や結婚といった旧来の制度の外側に立ち、一個の人間として自己を確立しようともがく。それは、セルジュ・ゲンズブールとの関係性の中で輝いたジェーン・バーキンのような存在とも本質的に異なる。バーキンがいかに奔放に見えようとも、その反抗はあくまで家父長制の枠の中、つまり既存の社会構造の内部で許された「お天場娘」のそれに過ぎなかった。対照的に、ダイアン・キートンは、その構造そのものの外に立つことを選んだのだ。
この、家父長制の引力圏外に存在する自立した個人というコンセプトは、やがて「西側先進国の倫理観のベース」となった。個人の尊厳と自律を重んじるこの価値観は、普遍的なものとして共有されていく。しかし、その光が届かない場所がある。それこそが、我々の暮らす日本の社会であり、政治の風景なのである。
——————————————————————————–
2. 対極にある風景:日本の「湿った」政治とメディア
議論の舞台を日本に移すと、風景は一変する。欧米で確立された個人の自立や、理念に基づく合理的な対話といった価値観とは対極にある、ウェットで属人的な論理が支配する世界がそこにはある。特に、近年の政治とその報道のあり方は、この国の構造的な病理を色濃く反映している。
日本の政治報道は、政策や理念を巡る論争ではなく、人間関係のゴシップとして消費される傾向が著しい。その典型が、共同通信が配信した「玉木氏 高市総裁と協力も」という見出しの記事だ。この記事が問題なのは、政党間の政策協議を「国民民主党と自民党の連携」としてではなく、「玉木氏と高市氏」という個人間の関係性として描いている点にある。政治が、政策という公的な領域から引き剥がされ、属人的な人間関係の物語へと矮小化されているのだ。これはもはやゴシップ記事であり、その本質は「誰と誰がラブホテルに行ったか」という話と何ら変わらない。
このような報道がまかり通るのは、メディアが有権者をそのレベルで満足する存在だと見なしているからに他ならない。そして、このゴシップ的な政治状況の根源には、日本の社会に深く浸透した「男が作ったホモソーシャルな世界」が存在する。その世界を特徴づけるキーワードは、「陰湿」であり、「じとっとしてる」感覚であり、そして何よりもまとわりつくような「湿度」である。
この「湿度の高い」男性社会の論理は、メディア報道のみならず、政治のパフォーマンスそのものに現れる。政局の最中に配信された玉木雄一郎氏と榛葉賀津也氏のYouTube配信は、その象徴的な光景だった。そこには政策論争のカケラもなく、ただ内輪の論理と感情が「ベトベトじとじと」と渦巻いていた。それは、閉鎖的でウェットな男性共同体の論理が、いかに日本の政治を蝕んでいるかを物語っている。このような旧態依然とした男性中心の構造は、当然ながら、その中で生きる女性の役割をも規定し、歪めてきたのである。
——————————————————————————–
3. 失敗のケーススタディ:なぜ社会党は「山」を動かせなかったのか
日本のジェンダーポリティクスが抱える根深い問題を象徴する事例として、女性リーダーをいち早く擁立しながらも、歴史の舞台から姿を消しつつある社会民主党(旧社会党)のケースは避けて通れない。土井たか子というカリスマ的な党首を得て「山が動いた」とまで言われた党が、なぜこれほどまでに衰退したのか。
その原因は、村山富市氏を総理にしたといった個別の政治判断の失敗にあるのではない。問題は、より構造的で根源的な部分に横たわっている。党は土井たか子氏を党首に選出しながらも、結局彼女を「女としてしか扱わなかった」のだ。その党運営そのものが徹頭徹尾「おっさんドリブン」であり、結局のところ「男社会のそのもの」だったのである。
党は、女性リーダーという新しいシンボルを掲げながら、その内実は旧来の男性中心主義から何一つ変わっていなかった。この自己欺瞞こそが、党の活力を奪い、有権者の信頼を失わせた最大の要因である。深刻なのは、大椿裕子氏のような当事者や、上野千鶴子氏のようなフェミニズムの専門家でさえ、この核心にあるミソジニー(女性嫌悪)の構造を明確な言葉で指摘しきれていない点にある。問題の根深さは、まさにここにある。
この痛ましい失敗が示す教訓は明確だ。「女性をトップに据える」という形式的な操作だけでは、組織の根底に巣食う「湿った体質」は決して変わらない。社会党の衰退は、この「湿度」――すなわち、属人的で非合理的な人間関係が支配する男性中心文化――が、いかに進歩的な運動さえも内側から腐食させるかを示す、最たる実例と言えよう。真の変革は、組織文化そのものを根本から問い直すことからしか始まらない。そして、その構造的な課題を乗り越える可能性の光は、旧世代とは異なる資質を備えた、次世代の女性政治家たちの中に見出すことができるかもしれない。
——————————————————————————–
4. 「カラッとした」気配の胎動:日本政治における『アニー・ホール』の可能性
日本の陰湿で旧態依然とした政治風土に、わずかながら変化の兆しが見える。それは、これまでとは異なるタイプの女性政治家の出現である。彼女たちは、日本の政治がまとわりつかせる「湿度」とは無縁の、新しい可能性を感じさせる。
立憲民主党の西村ちなみ氏や石垣のりこ氏といった女性議員たちの中には、ある種の「アニホルっぽさ」とでも言うべき資質が見て取れる。この「アニホルっぽさ」とは、「湿度がない感じ」であり、「カラッとしてる」ことだ。それは、男性社会のルールに迎合したり、男性的な攻撃性を模倣したりすることなく、あくまで自然体で自立したスタイルを貫く姿勢を指す。
この「アニホルっぽさ」は、単なる個人のスタイルの問題ではない。日本の「陰湿でじとっとした」男性政治社会を打破するためには、不可欠な戦略的資質なのである。なぜなら、男が作ったホモソーシャルな世界は極めてじとっとしているため、それに対抗するには「極度にカラッとしてなきゃだめ」だからだ。
この洗練された「カラッとした」スタイルは、単なる美的嗜好ではない。それは、旧態依然とした地方の男性社会の価値観を打ち破るための、知的で強力な武器なのだ。ダイアン・キートンがスティーブン・コルベアの番組で見せたような、知性と気品に満ちた洒脱な雰囲気。まさに「この素敵さで田舎のおっさんを殴らんとダメ」なのである。この闘いにおいて必要なのは、『エイリアン』のシガニー・ウィーバーが見せたような戦闘的なスタイルでも、『プラダを着た悪魔』のメリル・ストリープのような権威的なスタイルでもない。まさに『アニー・ホール』のダイアン・キートンが体現した、知的で、軽やかで、そして何よりも自立したスタイルなのである。この「カラッとした」気配は、まだ萌芽的なものに過ぎないが、日本の政治風土を根底から変える可能性を秘めている。
——————————————————————————–
結び:50年後の『アニー・ホール』が私たちに問いかけるもの
ダイアン・キートンという、一つの時代の文化的象徴を失った今、私たちは改めて一つの現実に直面する。彼女が体現した「自立した女性」という理想像が、公開から約半世紀を経た現代日本の社会、特に政治の世界において、いまだ十分に根付いていないという厳しい現実だ。
『アニー・ホール』から50年、日本は一体何をしてきたのだろうか。この映画は、今なお現代日本社会を映し出す、極めて有効なリトマス試験紙として機能している。「アニホール見て何とも思わんやつは多分参政党に投票する」という挑発的な言葉は、この映画が内包する価値観――個人の自立、知的な会話、そしてウェットな共同体からの自由――が、現在の日本の政治的分断線と奇妙に重なっていることを鋭く指摘している。
なぜ日本では、世界中を魅了した「世界の恋人」としてのダイアン・キートンが生まれにくかったのか。なぜ、彼女が体現した「アニホルっぽさ」が、社会の主流になり得なかったのか。この問いは、単なる映画文化論に留まらない。それは、日本の近代化が抱え続けてきた、より根源的な文化的課題そのものを私たちに突きつけているのである。ダイアン・キートンの不在は、私たちがこれから何を獲得し、何を乗り越えていくべきなのかを、静かに、しかし厳しく問いかけている。
人気ブログランキング

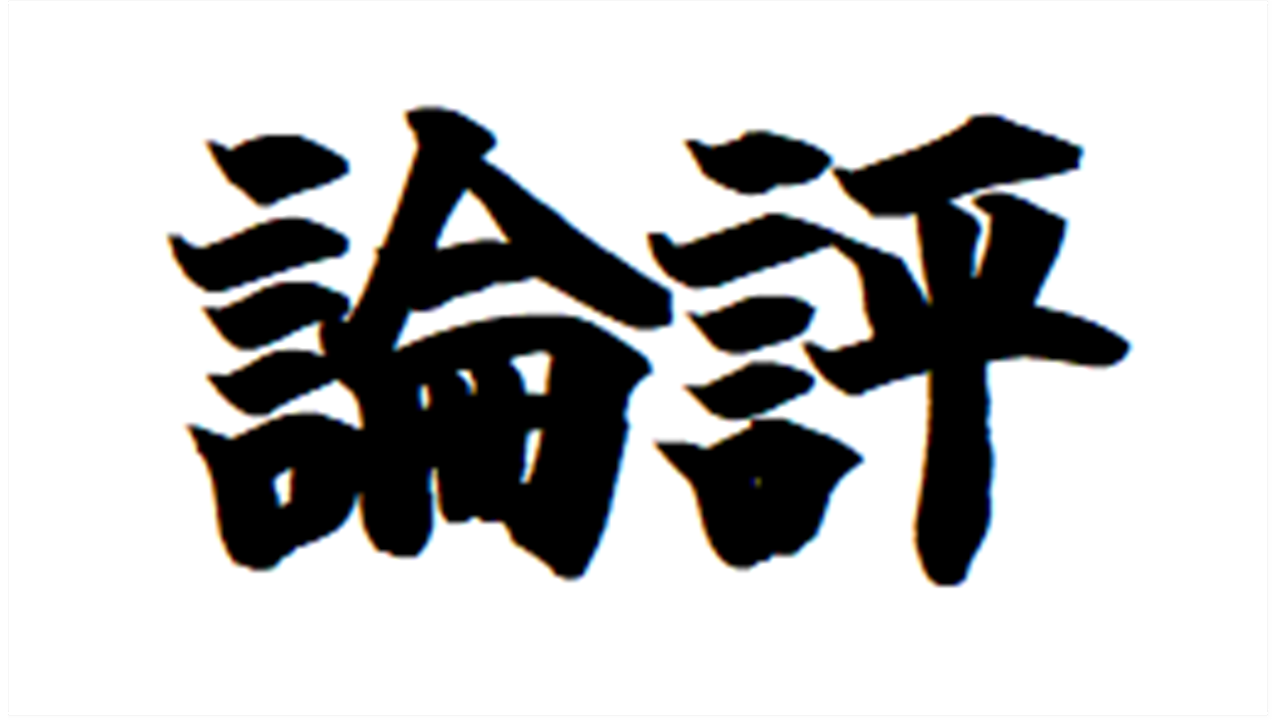
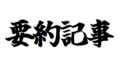
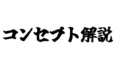
コメント